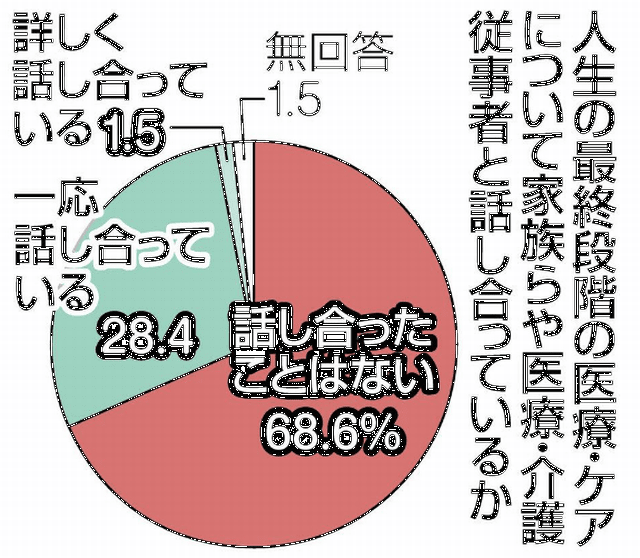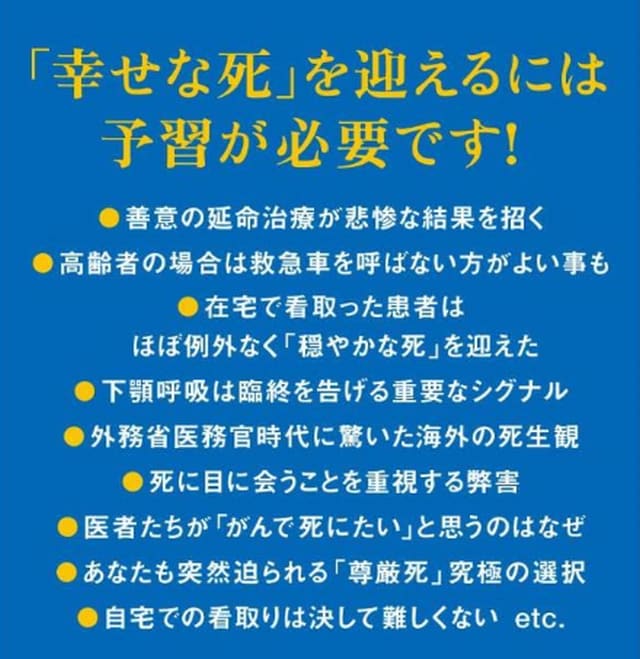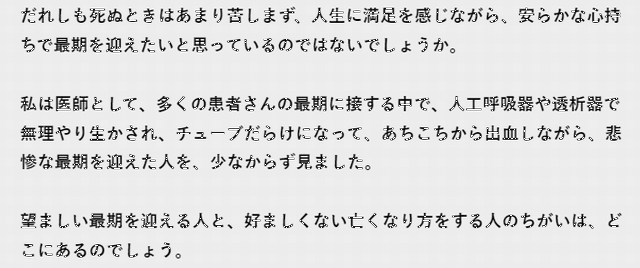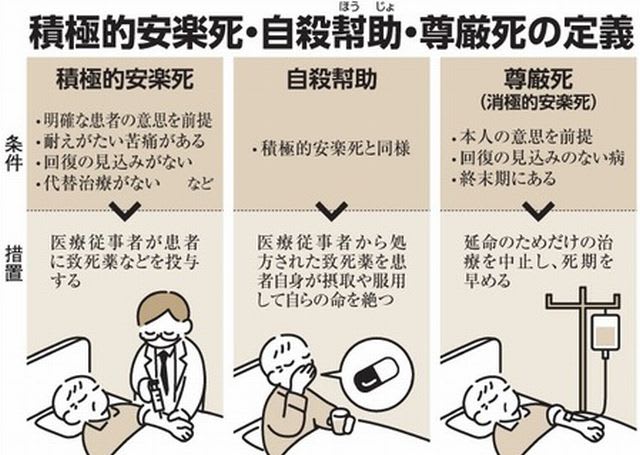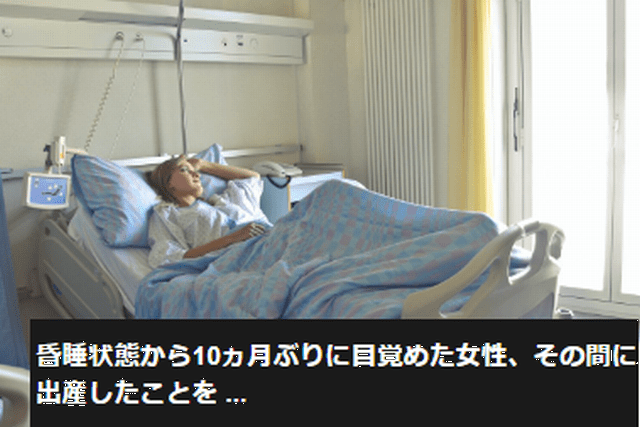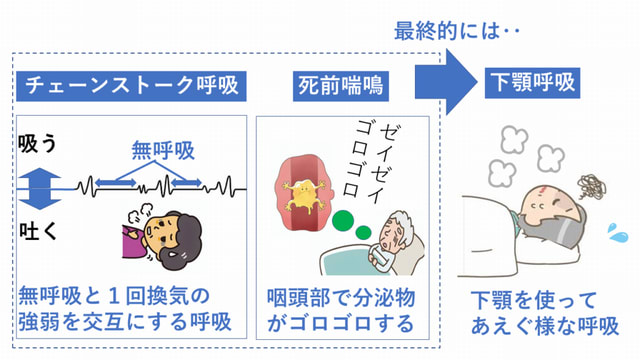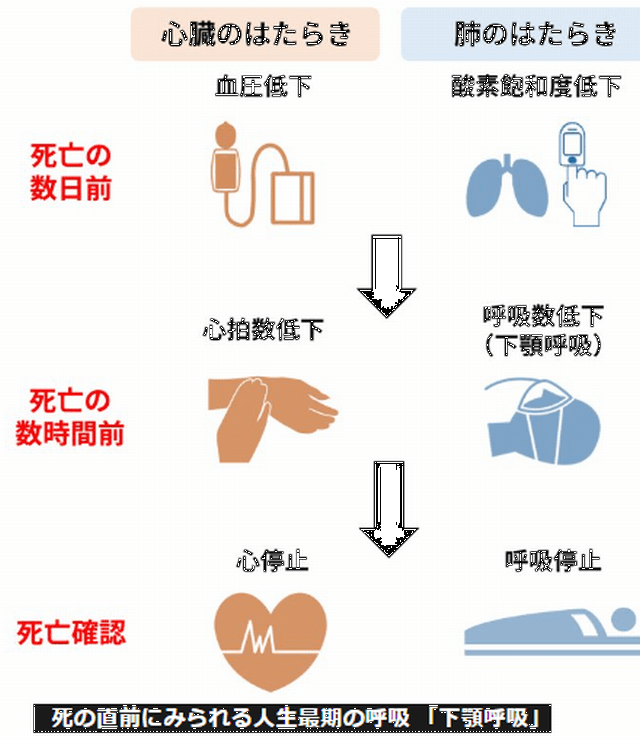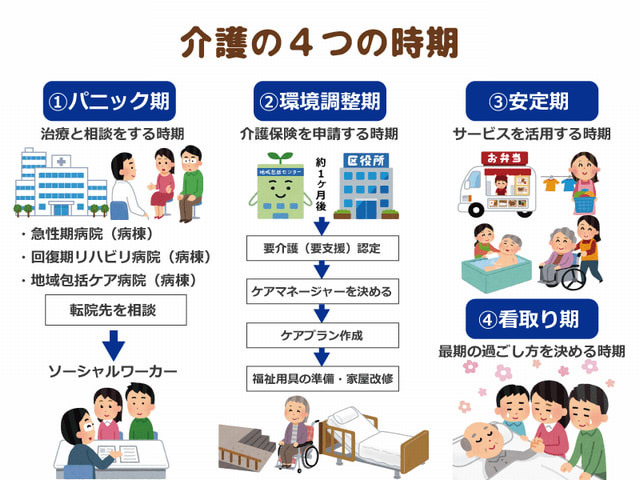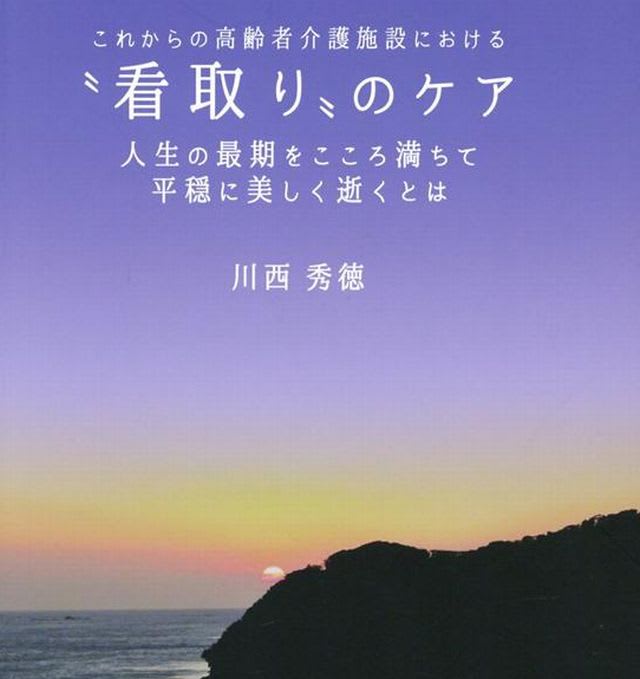🌸不愉快な事実は伝えないメディア
☆文字ばかりで恐縮ですが
*医師側から見た『看取り』の内容なので
☆何か『人間のライフクロック』を感じさせられます
⛳メディアウソは伝えないが、都合の悪いことも伝えない
☆不愉快な事実はだれも知りたがらない
*心地よい話はメディアにあふれている
☆不愉快な事実はだれも知りたがらない
*心地よい話はメディアにあふれている
*長寿社会の礼賛、医療の進歩、活き活きシルバーライフ、絆等
☆その為、準備を怠り、いざというときになり
*慌て、迷い、選択を誤る人が多いのは、しがたいこと
☆テレビや新聞で前向きな人を見ていて
☆テレビや新聞で前向きな人を見ていて
*そういう人も必要だろうけれど、そればかりでいいのかと
*いつも疑問に思っている
☆これは老いや死に関することばかりではない
☆これは老いや死に関することばかりではない
*犯罪の報道でも、凶悪な犯罪では被害者の側に立った視点で
*犯人の悪辣なことばかりが報じられる
*犯人の側に立つ報道は、まず皆無
☆メディアはウソは報じないが、都合のいいことしか伝えない
☆メディアはウソは報じないが、都合のいいことしか伝えない
*世間の共感を得て、メディアとしての信頼を高め
*メディアは、収益につなげることが目的だから
☆被害者のことを考えれば
☆被害者のことを考えれば
*加害者の言い分など聞きたくもないし、犯人の悪辣な情報を得て
*勧善懲悪の気分に浸っているほうが気持ちがいい
☆メディアも被害者のニーズに応えて
*仮に加害者側に致し方ない事情があっても闇に葬る
*報じられないことは、受け手からすればないのと同じ
☆老いと死に話に関しても
☆老いと死に話に関しても
*気持ちのいい情報ばかりで安心するのは危険
*不愉快なことでも知っておいたほうがいいこともある
*より成熟した人間としては、イヤなことにこそ目を向け
*しっかりと心の準備をしておくべきだ
⛳”人生百年時代”の意味
☆昨今、何が根拠かわかりませんが、「人生百年時代」に突入した
☆この言葉の真に意味するところは
⛳”人生百年時代”の意味
☆昨今、何が根拠かわかりませんが、「人生百年時代」に突入した
☆この言葉の真に意味するところは
*「百歳まで生きられる」ではなく、「百歳まで死ねない」ということ
☆高齢者医療の現場にいた筆者
*百歳近くまで生きて悲惨な状況の患者さんを間近に見て
*何度、長生きは考え物だと思つたかしれません
*生きすぎる長生きは不運以外の何ものでもない
*メデイアはそういう不愉快な事実はめったに伝えない
☆メデイアは、超高齢でも元気な人を採り上げ
*こんなに食欲旺盛だの、腕立て伏せができるだの
*今も仕事をしているだのと、その活躍ぶりを賞讃します
*見た人は感心し、いい気持ちになり
*無意識に自分もそうなれるのではないかと思ってしまう
☆それはフェアな報道ではない
☆それはフェアな報道ではない
*元気で活躍する超高齢者
*テレビに映る場面では笑顔でも、実際はあちこち痛かったり
*関節が曲がらなかったり、不眠と便秘と耳鳴りと頭痛に苦しんで
*顔をしかめているかもしれません
*おむつをつけていたり、尿漏れに悩んでいたり
*心不全、不整脈、肺気腫、腎機能障害等に怯えていたりと
*さまざまな老いの現実に苦しんでいるはずです
*不安定な状況はいっさいメディア伝えません
☆悲観的なことばかり思い浮かべて
*うつ病になってはいけませんが
☆楽観的なことばかり考えて、心の準備を怠ると
*現実の老いに直面したとき
*「こんなになるとは思わなかった」等
*余計な嘆きに苛まれることになります
☆長生きを目指すなら
☆長生きを目指すなら
*そういう不愉快な事実も視野に入れておく必要がある
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『人はどう死ぬのか』
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『人はどう死ぬのか』



『都合の悪い事伝えないメディア』『老いた肉体への心の備え必要?』
(ネットより画像引用)