100号記念の放送大学機関誌に200字程度で書けと言われた。200字ではとてもかけない。推敲したりして、ふたつつくってみた。
■自分自身の課題と重ねて書いたものが、以下のもの。
戦後も続いた就学猶予・免除制度の下で、障害のある人たちは学校教育から疎外されてきた。その人たちに、教育や学びの場の意味を考えさせられた。さらに成人教育等の中で学びを取り戻していくという教育学の課題も視野に入るようになってきた。放送大学での仕事は、このような自分自身の課題とも重なるものがある。高等学校の進学率が90%を越えたのが1974年のこと(ちなみに、大学進学率が50%を越えるのが2009年)。放送大学に来られた人たちの経歴や動機は様々であるのだろう。大学でのフレッシュな学生とは違った、人生の重みがかかった方々のこれまでの経験や学びの意欲に魅せられるという実感がある。成人期やシニアの時期に学ぶこと・学びなおすこと、学びの中で人との出会いやつながりをもち豊かさを蓄えていくことの意味は重い。
■自分自身の課題と切り離した文章が以下のもの。
高等学校の進学率が90%を越えたのが1974年のこと(ちなみに、大学進学率が50%を越えるのが2009年)。放送大学に来られた人たちの動機や経歴は様々であろう。大学でのフレッシュな学生とは違った、人生の重みがかかった方々のこれまでの経験や学びの意欲に魅せられるという実感がある。すべての人が、これまでの学びを振り返り、さらに学び直しをするという時代になってきたともいえる。その学び直しの経験が蓄積され、記録されていくなら、国民的な財産となっていくものと思う。成人期やシニアの時期に学ぶこと・学びなおすこと、学びの中で人との出会いやつながりをもち、豊かさを蓄えていくことの意味は重い。










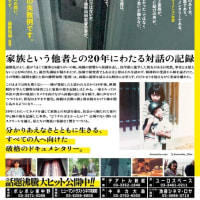




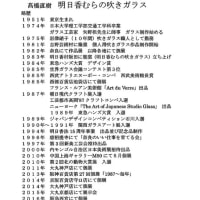

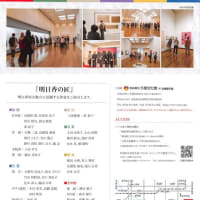


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます