新たなチャレンジとやり残していること
本年度から、新設された特別支援教育コースで、インクルーシブ教育原論、特別支援教育の教育課程論などを担当することになりました。1988年に着任して、学部・大学院修士課程を担当してきました。本学に、特別支援教育関係の養成課程ができてから今年で50周年になります。特別支援の担当の中では、一番古いのですが、今年からは新たなチャレンジとなります。
振り返って思い起こすのは、着任当時のことです。「障害児教育は若い学問分野だから、障害のある子どもの教育に関わるには、何でもできなければならない」と上司にいわれました。ようするに「何でもやれ!」ということで、「何でも屋」となったわけです。関連する福祉や外国の法制、発達診断、教育相談、授業研究などなど、いろいろやってきました。しかし、本来の専門は、近代児童問題史研究で、それだけはこの大学で深めることができなかったといわざるを得ません。
そろそろゴールも見えてきたところですので、教職大学院での新たな挑戦とともに、いまいちど、深めきれなかった歴史研究に戻ってやり残したことを埋めたいと思っています。奈良・京都・滋賀などの障害児教育を担った人たちの交流や連携に思いを馳せながら、戦時の野方達の創られた実践が記録されているフィルムや映像・音声、実践資料を掘り起こし、そのデジタル化を通して実践遺産の蓄積を行っています。現代的な機器とレトロな機器を使いながら、過去の子どもと教師の姿に、皆さんも触れてみませんか。
(ニューズレター)
本年度から、新設された特別支援教育コースで、インクルーシブ教育原論、特別支援教育の教育課程論などを担当することになりました。1988年に着任して、学部・大学院修士課程を担当してきました。本学に、特別支援教育関係の養成課程ができてから今年で50周年になります。特別支援の担当の中では、一番古いのですが、今年からは新たなチャレンジとなります。
振り返って思い起こすのは、着任当時のことです。「障害児教育は若い学問分野だから、障害のある子どもの教育に関わるには、何でもできなければならない」と上司にいわれました。ようするに「何でもやれ!」ということで、「何でも屋」となったわけです。関連する福祉や外国の法制、発達診断、教育相談、授業研究などなど、いろいろやってきました。しかし、本来の専門は、近代児童問題史研究で、それだけはこの大学で深めることができなかったといわざるを得ません。
そろそろゴールも見えてきたところですので、教職大学院での新たな挑戦とともに、いまいちど、深めきれなかった歴史研究に戻ってやり残したことを埋めたいと思っています。奈良・京都・滋賀などの障害児教育を担った人たちの交流や連携に思いを馳せながら、戦時の野方達の創られた実践が記録されているフィルムや映像・音声、実践資料を掘り起こし、そのデジタル化を通して実践遺産の蓄積を行っています。現代的な機器とレトロな機器を使いながら、過去の子どもと教師の姿に、皆さんも触れてみませんか。
(ニューズレター)










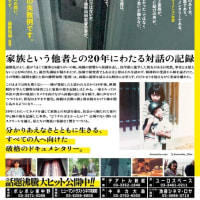




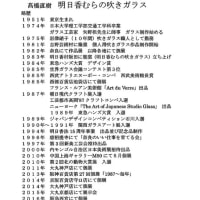

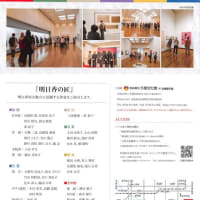


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます