鉛筆でかく映画
田村一二 伊丹万全集月報2 1951年3月
終戦の前の年だったと思う。その頃私は一週間か十日に一回くらいの割で京都の伊丹さんの家へ見舞いに行っていた。
石山寺の南の丘の上で、石山学園という小さな施設で十五名の男の精薄児と一しょに暮らしていた私は、毎日のようにB29が編隊ウオンウオンと唸りながら、上空をとんでいくのを見上げながら、横穴式防空壕を掘ったり、野菜をつんだり、藪を開墾したり、芋をつううったり、それで足りずに京都へ托鉢に出かけたり、夜は末つ子をせえなかにくりくくりつけt、園児くくりつけて、園児に学科を教えたり、在郷軍人の早期訓練に出たり、夜中に起きて園児たちのねごとをきき、屁のにおいをかぎながら原稿を書いたり、異赤ら考えるとようおあれだけ動いたと思うほどの忙しさの中から、なんとかやりくりして伊丹さんを見舞いにいったわけである。
わずかの野菜(そのことは貴重であった)を下げて木炭バスにのって、この野菜をみたら伊丹さんが喜ぶぞと、あのひげがニコッと動く顔をみるのが楽しみであった。
伊丹さんは大抵病床に仰臥したまま、私は枕元に座って話し合う小田が、その頃の伊丹さんの感じは映画人というよりも学者のようであった。それも恐ろしく趣味の広い学者である、話題は多岐にわたったが、映画、文学は勿論、洋画、俳句についても造詣が深く、硯についてもくわしかったのに驚いたことを覚えている。
その伊丹さんがある時いった。
「田村さん、あなたはいつも私の枕元のすぐそばに坐りますね、そして平気で茶をのみますね。しかし、そんな人はめつたにありませんよ、たいてい三尺以内にははいつて来ませんな、正確に」そういついて伊丹さんはわらつた。「お茶なんかまず手はつけませんね」そしてしばらく黙つてからいつた。「人間の幸福は何んといついても健康です、これは絶対です」
長い闘病生活から来た伊丹さんの深い淋しさがまつこうから吹きつけて来たようで私はしばらく顔があげられなかつた。
「手をつなぐ子等」の脚本を書いていた頃、あの中に出てくる氷すべり、草ぞり、土中に埋めこまれる場面などのことをよくきかれた。あれはみな私の子どもの頃の経験なのでくわしく話をすると伊丹さんは肯きながら、メモをとったり略図を書いたりしていた。
それから何日かたって見舞いにいった時、脚本を見せられておどろいた。ある場面場面が精密な鉛筆画になっていた。ちょうどフィルムの一コマ一コマを見る感じであった。こおまま放っておいたら伊丹さんは鉛筆で映画をかいてしまうっではないかと思ったほどである。
「ほんとうはこの映画は自分で監督したいんですが、この体ではとてもだめですから、せめて、まあ、こんなことでえもして慰めているんですな」
といって伊丹さんはあのひげをちょっとあげて自虐的にわらったが、それは単なる慰みごととは受け取れなかった。誰が監督をするにしても、自分のイメージをこわされたくない、こういう映画を作ってほしいという願い、その願いを通すために、文だけでなく絵にもかいておいて、のっぴきならぬものを監督につきつけようという、いわば映画に対する恐ろしいまでの執念が、病床でやせほそった手に鉛筆を握らせたのではないかと私はみている。
石山学園歌については、伊丹さんはひじょうに気持ちよくすらすらとできたといっていた。例の伊丹さんの便せんにきれいな字で書かれた歌が送られてきた時は思わず私はみとれてしまった。作曲が田辺一郎先生の手でできた時、われわれは伊丹さんの家でささやかな完成祝いをやった。
田辺さんは当時貴重なる配給の酒を持参し、伊丹さんの奥さんは加茂川の土手でつんで来た「なずな」をてんぷらにし、私はかつて伊丹さんが白いパンがいっぺん食べてみたいといっていたことを思い出して、小麦粉をもって京都の町の中のパン屋数軒をかけまわり、いありかえる主人を拝み倒してやっと手に入れた白いパンを持っていった。
伊丹さんも珍しく起きて、羽織をひっかけて長火鉢の前に坐り、何かと嘱託のせわなどを楽しげにしていた。
パンとなずなのてんぷらと配給の酒とではじまった宴のなかば、田辺さんが園歌を低い声でうたいはじめた。伊丹さんはじっと目をつぶっていたが、うたが終わると、
「いい曲ですね、ほんとうにいい曲だ、音域が広くないので子どもたちにはうたいやすいでしょうね」
といった。
この歌は石山学園解消と同時に近江学園の園歌となって、今日なお精薄児たちによって、朝夕したしまれ歌われているのである。















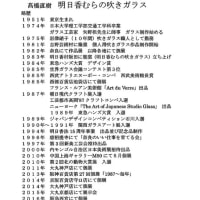




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます