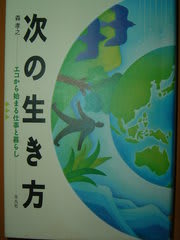これからのライフスタイルを考えるにあたって大いに影響を受けた著書2冊。
大量生産、大量消費を「発展」の推進力とする現代社会に対するアンチテーゼとしてのエコライフ。今でこそ巷ではエコの大合唱であるが、著者の優れるところはエコブームに乗っかるのでなく、バブルはるか以前からそれを孤高に実践してきたことにある。著者自身も著書の中でそのことに対する自負を述べている。ただ残念なのはそのことへの自負のあまり、著者や著者世代の幸運と言ってもよい社会的条件と、エコライフの声が高まれば高まるほどに逆に、特に若者をめぐるエコライフどころではない基本的生活そのものの困難さが増大している社会状況の変化に思い及んでいないところである。
ひたすら日本の戦後復興と経済発展のために邁進してきて、そこそこの蓄えと退職金があり、親世代が残してくれた土地があり、切り下げられる以前の比較的豊かな年金の恩恵にも浴することができる、いわゆる団塊世代以上の人達 ―全員がそうでないのは言うまでもない― に対して、経済至上主義の価値観とライフスタイルの「自己責任」による転換を訴える著者の提案は妥当性も高く確かに傾聴に値するだろう。
しかし、ワーキングプアという言葉に象徴される不安定な雇用と収入、年金を筆頭に切り下げられる社会保障で生活不安の増大する、特に30歳台以下の若者にとっては悠長にエコライフなどと言ってはいられないのだ。いやすでに貧乏生活を強いられている彼らこそ意識改革など求められるまでもなく、金を使わない(金が無い)生活と言う意味ではすでに「エコライフ」を実践している、いやせざるを得ないのだ。ただ彼らの「エコライフ」は著者の言う自然と共生した創造的で豊かなエコライフとはほど遠い。彼らの所得では「エコ」という付加価値で高値を付けられた「エコ商品」など買えるべくも無い。
著者の理想とするライフスタイルは、小金持ち以上の層、すなわち農的生活に適した広い土地を所有し、学齢期の子供と住宅ローンを抱えた生活費の心配も無く、比較的高価な「エコ」商品を購入でき、時間も自由になる恵まれた著者のような人達でなければ実現不可能だろう。私自身も著者には到底及ばないにしてもそこそこの退職金と蓄えと学齢期を終えた子供達という条件があったからこそ自分なりの「エコライフ」を目ざすスタートを切ることができたのだ。そうした弱点もあることを踏まえた上で読み解けば、著者の説くところには大いに啓蒙させられるところ大であり、なにより机上の論ではなく実践に基づく著者のライフスタイル論は強い説得力を持って迫ってくる。著者が「庭宇宙」と呼ぶ「アイトワ」へ。