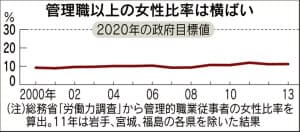愛知大学 京角 理恵
日本にとって中国はお隣の国であり、日本が最も影響を受けてきた国である。日本が初めて中国から影響を受けたのは、紀元前3~2世紀ごろに稲作が伝わったというところまでさかのぼる。
中国と日本は二千年にもおよぶ友好往来の歴史がある。しかし、近代百年の歴史はおおむね対立と抗争、侵略という暗い歴史である。
ここでは、日本が現代に入り明治政府が国を動かすようになった頃から1978年の日中平和友好条約を締結するまでと、現在の日中関係についてみていきたい。
1~7(略)
8、民間レベルでの交流の始まり
アメリカの強力な影響下に置かれていた日本の中華人民共和国との関係は民間レベルで突破口を見出す以外になかった。
1952年、高良富・帆足計・宮腰喜助の3人はソ連経由で中国を初めて訪問し、中国国際貿易促進委員会と第1次民間貿易協定を結び、民間レベルでの人的・経済的交流が開始された。
これは、日本人民の中国人民に対する感情がいかなる政治力でも左右できるものではないことを説明している。
その後も民間の交流はたえず拡大し、友好往来の発展は日中国交正常化への国民運動の発展につながった。注7
9、日中関係の危機
民間・人民の交流はさらに拡大発展していくように思われたが、1957年に岸信介内閣が成立し、日中関係は危機を迎えることとなる。
岸は反ソ反共・親米派の策謀家で、日本をアジアにおける反ソ反共の防波堤にしたいというアメリカの期待を一身に担って行動した。
一例をあげてみると、台湾・アメリカ・インド訪問の際の「中共非難」や「長崎国旗事件」注8である。陳毅副総理は「岸内閣の中国敵視はもはや我慢できない。
この結果についての責任はすべて日本政府にある。」と宣言し、この声明が合図となって、貿易関係機関はいっせいに日本側との契約を破棄し、ここ数年来民間方式によって積み重ねられてきた諸交流は、基本的に中断される事態となってしまった。注9
10、日中交流の再開
1959年から石橋湛山・松村謙三らの人々の絶えざる努力で、日中の友好は次第に回復した。
石橋・松村らが中国を訪問している間、日本国内は日米安保条約改定に反対する安保闘争が激化していた。
結果的に岸内閣は総辞職に追いこまれ、次いで池田勇人内閣が1960年に成立した。 池田政権のもとで、日中関係は順調に進んだ。
友好商社は増加し、取り引き物資を積んだ船の出港入港のたびに相互理解は深まり、「日中国交正常化せよ」という声は高まるばかりだった。
1962年には松村謙三と周恩来首相の会談が行われ、これを受けて高碕達之助の訪中と廖承志との間の協定によってLT貿易(両者のイニシャルをとってLT)が発足することになった。
LT貿易の発足は日中貿易の拡大のみならず、日中関係正常化にとっても大きな斬新であった。
これに対してアメリカは、「中国は膨張主義的好戦的共産主義権力である」と罵り、「これを封じこめるための日米の合作が必要である」と日本側の協力を求め、LT貿易などもってのほかであると内政干渉してきた。
しかし池田内閣は「倉敷」ビニロンプラント輸出に輸出入銀行の資金を使い、中国が日本からの輸入する最初のプラントとなることを正式に諒承し、アメリカの干渉にうちかってLT貿易は順調に発足した。注10
11、2度目の危機
LT貿易も発足し、日中国交回復も今度こそ遠からずと思われていた矢先、池田首相が病気で倒れ、次いで1964年佐藤栄作内閣が成立し事態は一変した。
佐藤は岸信介の実弟であり、日米安全保障条約に兄とともに狂奔した大の反ソ反中国のやり手だった。
佐藤首相は1965年に訪米し、米大統領ジョンソンと会談の際、日本が台湾の蒋介石グループを支持することを求められると、佐藤首相は即座に応じて、蒋介石と“正規の外交関係”を保持し、「中共に対しては政経分離の政策をとる」ことを言明した。
さらに2月には、池田内閣がせっかく開いたLT貿易への輸出入銀行融資による延べ払いの道を閉ざしてしまった。「LT貿易なぞつぶしても構わぬ」と佐藤首相は公言して憚らず、中国敵視政策を明確にした。
1967年に入ると、佐藤首相の中国敵視の言動はさらにエスカレートした。9月佐藤は人民の強い反対を顧みず、岸に倣って台湾を訪問した。
このことは、さらに日中関係を悪化させた。
1969年、ニクソン米大統領と佐藤首相との日米共同声明が華々しく「沖縄返還」をうたいあげた反面には、日本がアメリカから背負い込まれた重い荷物が隠されていた。それは、70年代において、日本がアメリカの核のカサの下で、米帝国主義の忠実な助手として、そのアジア支配の軍事的・経済的肩代わりを義務づけるものであった。注11
12、米中接近
佐藤内閣が「沖縄返還」を錦の御旗に軍備拡張、アジアにおけるアメリカの肩代わりと中国敵視政策でせっせとアメリカの点数稼ぎに懸命であった時、アメリカは密かに中国との接近を進めていた。
1968年アメリカ大統領に当選したニクソンは、大統領補佐官に任命したキッシンジャーと図って、新たな世界戦略をうち建てて、ベトナム戦争の泥沼から抜け出す道を求めていた。
中ソ対立を利用して、米中接近を図り、ベトナム戦争の解決に有利な条件を作りたいと考えていたのである。
1971年4月中国はピンポン外交を展開し、アメリカのピンポン・チームの訪中を歓迎した。これが米中接近のきっかけとなり、7月にはニクソン大統領の意を受けてキッシンジャー補佐官が極秘訪中した。
11月には中華人民共和国は台湾の国民政府に代わって、国連における合法的地位を回復した。
中国が国連の合法的地位を回復したことは、中国の平和共存の外交政策が世界のますます多くの国々の支持を得ていることを示すものであった。
1972年2月には、ニクソン大統領が中国を訪問し、共同声明を発表した。
ニクソン訪中と共同声明の発表は、日本政府に大きな衝撃を与えた。
佐藤首相らが忠実にアメリカに追随して、中国敵視政策をとってきたにもかかわらず、アメリカ政府が日本政府を親しいパートナーと見なさず、“頭越し外交”によって、日本と事前協議することなく、突然中米関係改善の行動をとったことは日本にとってショックだった。ア
メリカにべったり追随していても、日中国交正常化には何の利益も無く、かえって自分自身が孤立してしまうと認識したのであった。一刻も早い国交正常化にむけて努力することを日本は強く決心したのであった。注12
13、日中国交正常化
日中国交樹立の客観的条件が熟してきたその時に、日中友好を主張する田中角栄内閣が佐藤内閣の総辞職後登場したことは、日中両国の国交正常化に重要な促進材料となった。
1972年田中首相は大平正芳外相とともに北京を訪れ、周恩来首相ら中国側と話し合った。
この会談の中で中国が主張する「戦争状態」と日本が主張する「戦争は日華平和条約で終結した」という認識のズレは日中共同声明第1項の「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は終了する」という表現に落ち着いた。
ここに、日中国交正常化という歴史的意味が付加されたのである。
そして、中華人民共和国政府を唯一の合法政府とし、台湾が領土不可分の一部であるという中華人民共和国政府の表明を日本政府は理解し、尊重するということになった。
日中両国政府は共同声明により、戦争状態の終結を宣言した後、一連の協定を結んで、国交正常化を実現したが、法的手続きからいえば、声明や協定は条約にとって代わることはできない。
共同声明では、「日中双方が平和友好条約の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。」とあり、共同声明のこの精神に基づき、両国政府は締結に向けた交渉に着手した。注13
14、日中平和友好条約
スムーズにいくかと思われた交渉だが、交渉は難航した。中国側は共同声明第7項の「反覇権条項」を条約草案に盛り込むことを主張したが、日本側はこれに異議を唱えた。以後、「反覇権条項」の取扱いが双方の交渉の対立点となった。
中国政府は、平和友好条約が共同声明の基礎から後退するなら、締結の意義を失うと考えた。
本来、覇権主義反対の原則から言って、共同声明第7項をそのまま条約の成文に書き込むべきものであった。
日本は共同声明の第7項では覇権主義反対を書くことに同意しておきながら、なぜ平和友好条約では反覇権条項を入れることに躊躇するのか。
それはソ連が日本に圧力をかけ、牽制していることと関係していた。
中ソ対立が激しい当時、ソ連は日本が中国と友好関係になるのを恐れた。
ソ連は日中両国が反覇権を明記した条約を締結するならば、これに対応する措置として、ソ連は「対日政策を見直すことになろう」と述べたり、海軍を日本近海に出動させて武力威嚇を行ったりしてきた。日本は「日本が中ソ対立に巻き込まれれば、アジアの不安定化と緊張をもたらす」と考え、条約交渉を中断させた。
1978年、ようやく転機が訪れた。福田赳夫が三木武夫に代わり首相となった。福田が首相に就任後、日本国内では条約締結を求める呼び声が高まった。
アメリカ政府が友好条約に賛同したことがさらに拍車をかけ、ようやく再開にこぎつけ、合意に向かい日中平和友好条約が締結した。
日中平和友好条約の締結により、正式に法律上から1世紀もの二国間の不正常な状態を終結し、日中間の前途に輝かしい展望が切り開かれた。注14
15、現在の日中関係
日中国交回復から28年になるが、相互不信はかつてなく深刻な状況にある。経済関係の目覚しい発展にもかかわらず、政治面では摩擦が絶えず、最近は、両国民の間に相互嫌悪の感情さえ募っている。
<江沢民の歴史認識発言>
その最大要因の1つは歴史問題である。1998年11月、江沢民は日本政府の招きに応じて中国の元首として初めて日本を公式訪問した。
この時江沢民は、中国国内の世論を意識して歴史問題で日本の反省を迫り、圧力をかけた。
これに対し日本国内では、中国はまだ歴史問題を外交カードに使うのかと言う声が高まり、中国への政府開発援助(ODA)の見直し論が高まった。
以下略
感想
日中二千年の交流史中の最も悲惨なところである日中戦争のところを私がペンを進めていた時、自分が日本人であることが嫌になりそうなくらいの憤りを感じた。
日本は中国に対して、つぐなっても、つぐないきれないほどのことを中国にしたと思う。「日中共同声明」締結時に、周総理は「中国人民は賠償の苦しみを深く味わったことから、日本人民が同じ苦しみにあうことを希望しない。また中国は莫大な損失をこうむったが、これは日本軍国主義者が責めを負うべきであり、日本人民もまた被害者であり、両国人民永遠の友好のため戦争賠償要求を放棄する。」と明らかにした。
私は賠償請求しなかったことは知っていたが、周総理がどういう思いで賠償請求しなかったのか初めて知った。
このことを知った時、周総理の温かさ寛大さに大変驚いた。
そして、日本は周総理の寛大さにその後答えることができているのだろうかと考えさせられた。
日本は自国本位のところがあり、ご都合主義のところがあると思う。
もちろん自国は大切だが、歴史を踏まえつつさらに友好的になれたらいいと思う。
私は去年の夏、中国の北京へ旅行に行った。
その時はパスポートとビザで中国に出入国できることはあたりまえだと思っていたし、当然の権利であると思っていた。
しかし、出入国できなかった時代があり、今こうして当然と思えるようになるまでの日中国交回復には幾度もの波乱があり、なみなみならぬ努力のおかげでできることと知った。
これからはさらに日中がお互いの国を思い合って、相互信頼を築き上げ、発展していくことができたらすばらしいと思う。