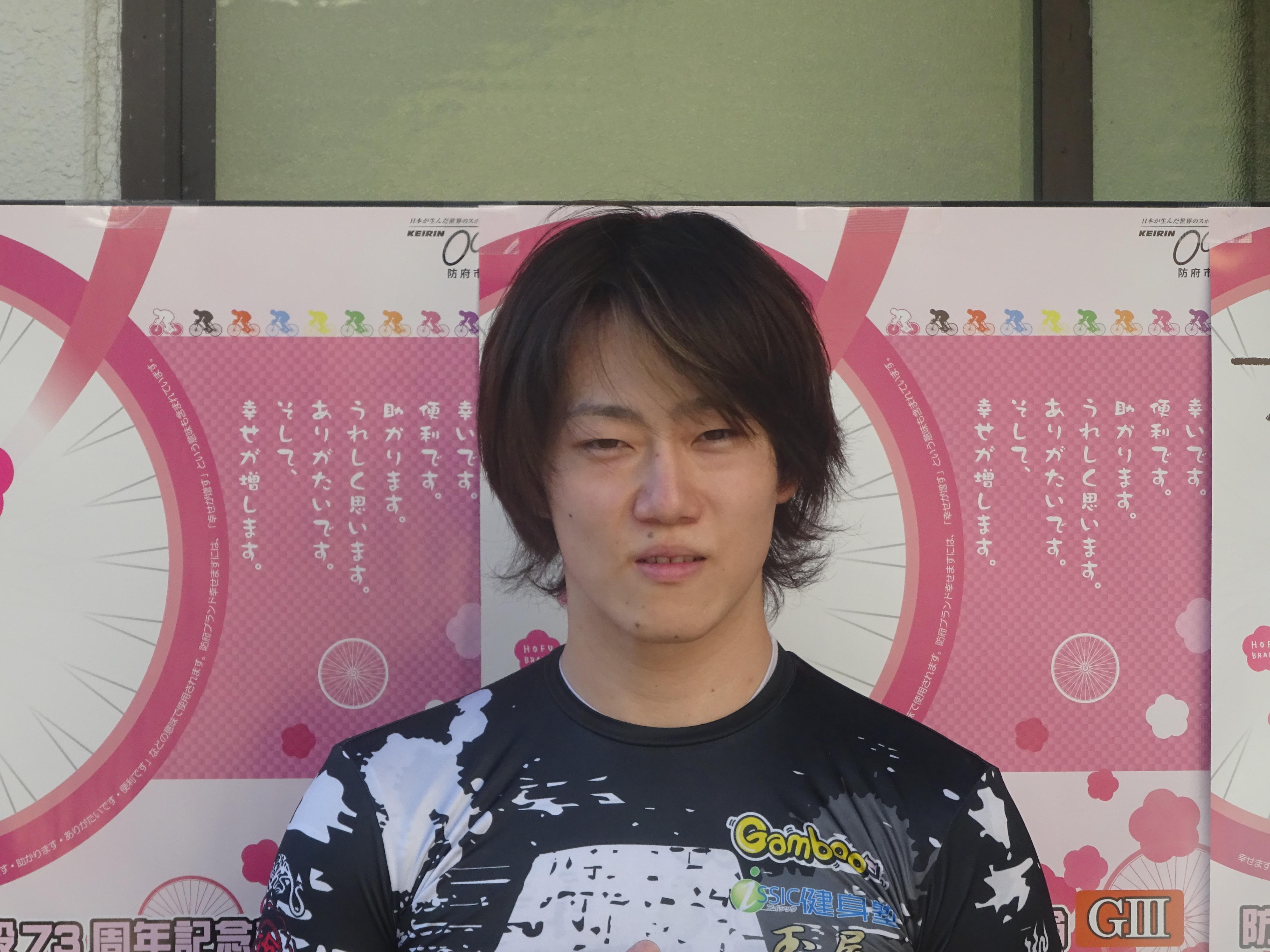八木誠一 (著)
理性と言語による現実把握の限界をどう超えるか。
ニーチェの生の哲学から実存主義、現象学、フロイト、ウィトゲンシュタイン、構造主義、さらには京都学派の哲学までを総覧し、それらを超えて現代人のための宗教に至る道筋を鮮やかに指し示す。
文庫化にあたり、著者による「補論 初版以後の展開」を付す。
-----------------------------------------------------------------
我々は、商品化以前の自然を見失ってはならないように、言語化以前の現実を見失ってはならない。……しかし、いったい言語化以前の現実などというものがあるのか、それはそもそも如何にして現前するのか。本書の全体はこの問いに――肯定的に――答えようとするのである。(本文より、略記)
何を神と呼ぶのか。理性と言語による現実把握の限界を超え、現代人のための宗教に至る道筋を示す。
「補論 初版以後の展開」を増補。
【目次】
文庫版への序
はしがき
第一章 現代思想の観点から
はじめに
第一節 実存主義(実存・存在・超越)
第二節 生の哲学と深層心理学
第三節 構造主義
第四節 現象学
第五節 言語哲学――ウィトゲンシュタインを中心として――
第六節 京都学派
付 論 滝沢克己と八木誠一
第二章 倫理の観点から
第一節 倫理とは何か
第二節 自我
第三節 自我とエゴイズムの諸相
第四節 個人倫理
第五節 対人倫理
第六節 社会倫理
第三章 宗教とは何か
第一節 神秘とその言語化――神について語るということ――
第二節 神秘と神・作用的一について
第三節 「神」を語る言葉について(1)――宗教と科学――
第四節 直接経験(1)
第五節 直接経験(2)
第六節 直接経験(3)
第四章 宗教の言語
第一節 通念的言語世界と直接経験A
第二節 通念的言語世界と直接経験B
第三節 通念的言語世界と直接経験C
第四節 記述言語 表現言語 要求・約束言語
第五節 「神」を語る言葉について(2)
第六節 宗教的自覚の言語化について
第五章 例証――イエスの言葉に即して――
はじめに
第一節 イエスにおける出会いの直接経験
第二節 イエスにおける自己
第三節 イエスにおける自然・神の支配・神
むすび
あとがき
補論 初版以後の展開
文庫版へのあとがき
文庫化にあたり、著者による「補論 初版以後の展開」を付す。
-----------------------------------------------------------------
我々は、商品化以前の自然を見失ってはならないように、言語化以前の現実を見失ってはならない。……しかし、いったい言語化以前の現実などというものがあるのか、それはそもそも如何にして現前するのか。本書の全体はこの問いに――肯定的に――答えようとするのである。(本文より、略記)
何を神と呼ぶのか。理性と言語による現実把握の限界を超え、現代人のための宗教に至る道筋を示す。
「補論 初版以後の展開」を増補。
【目次】
文庫版への序
はしがき
第一章 現代思想の観点から
はじめに
第一節 実存主義(実存・存在・超越)
第二節 生の哲学と深層心理学
第三節 構造主義
第四節 現象学
第五節 言語哲学――ウィトゲンシュタインを中心として――
第六節 京都学派
付 論 滝沢克己と八木誠一
第二章 倫理の観点から
第一節 倫理とは何か
第二節 自我
第三節 自我とエゴイズムの諸相
第四節 個人倫理
第五節 対人倫理
第六節 社会倫理
第三章 宗教とは何か
第一節 神秘とその言語化――神について語るということ――
第二節 神秘と神・作用的一について
第三節 「神」を語る言葉について(1)――宗教と科学――
第四節 直接経験(1)
第五節 直接経験(2)
第六節 直接経験(3)
第四章 宗教の言語
第一節 通念的言語世界と直接経験A
第二節 通念的言語世界と直接経験B
第三節 通念的言語世界と直接経験C
第四節 記述言語 表現言語 要求・約束言語
第五節 「神」を語る言葉について(2)
第六節 宗教的自覚の言語化について
第五章 例証――イエスの言葉に即して――
はじめに
第一節 イエスにおける出会いの直接経験
第二節 イエスにおける自己
第三節 イエスにおける自然・神の支配・神
むすび
あとがき
補論 初版以後の展開
文庫版へのあとがき
内容(「BOOK」データベースより)
理性と言語による現実把握の限界をどう超えるか。ニーチェの生の哲学から実存主義、現象学、フロイト、ウィトゲンシュタイン、構造主義、さらには京都学派の哲学までを総覧し、それらを超えて現代人のための宗教に至る道筋を鮮やかに指し示す。文庫化にあたり、「補論 初版以後の展開」を増補。
著者について
1932年生まれ。専攻、新約聖書神学、宗教哲学。
東京工業大学教授、ベルン大学(スイス、客員教授)、ハンブルグ大学(客員教授)、横浜桐蔭大学教授を経て、現在東京工業大学名誉教授、文学博士(九州大学)、名誉神学博士(ベルン大学)。
著書に『〈はたらく神〉の神学』『パウロ・親鸞*イエス・禅』など多数。
東京工業大学教授、ベルン大学(スイス、客員教授)、ハンブルグ大学(客員教授)、横浜桐蔭大学教授を経て、現在東京工業大学名誉教授、文学博士(九州大学)、名誉神学博士(ベルン大学)。
著書に『〈はたらく神〉の神学』『パウロ・親鸞*イエス・禅』など多数。

テリー・イーグルトン (著), 大橋洋一 (翻訳), 小林久美子 (翻訳)
内容(「BOOK」データベースより)
ドーキンスらの科学万能主義が蔓延する現代にあって、宗教はやはり阿片にすぎないのか。後期資本主義の格差・貧困を打開する可能性は、革命と救済を目指す宗教にあるのではないか。知の巨人・イーグルトンによる画期的宗教論。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
イーグルトン,テリー
1943‐。現代イギリスを代表するマルクス主義批評家、文化理論家のひとり。ケンブリッジ大学卒業後、オックスフォード大学特別研究員、同大学教授。その後マンチェスター大学教授(2008年退官)。現在、ランカスター大学教授
大橋/洋一
1953‐。東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は英文学、批評理論
小林/久美子
1978‐。ミシガン大学アナーバー校博士候補生、日本学術振興会特別研究員(PD)。東京大学大学院人文社会系博士課程満期退学。専門は米文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
1943‐。現代イギリスを代表するマルクス主義批評家、文化理論家のひとり。ケンブリッジ大学卒業後、オックスフォード大学特別研究員、同大学教授。その後マンチェスター大学教授(2008年退官)。現在、ランカスター大学教授
大橋/洋一
1953‐。東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は英文学、批評理論
小林/久美子
1978‐。ミシガン大学アナーバー校博士候補生、日本学術振興会特別研究員(PD)。東京大学大学院人文社会系博士課程満期退学。専門は米文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
内容(「BOOK」データベースより)
ドーキンスらの科学万能主義が蔓延する現代にあって、宗教はやはり阿片にすぎないのか。後期資本主義の格差・貧困を打開する可能性は、革命と救済を目指す宗教にあるのではないか。知の巨人・イーグルトンによる画期的宗教論。
神は妄想ではない
マルクス主義批評の大家によるキリスト教と宗教の弁証論。
世界的ベストセラー『神は妄想である』の著者であるリチャード・ドーキンズおよびネオコン・ジャーナリストのクリストファー・ヒッチンスによる反神学/宗教論を徹底的に批判するため、彼等の宗教に関する無知と欺瞞をユーモアと皮肉たっぷりの言語表現を駆使して叩きつつ、キリスト教を筆頭とする宗教の何たるかについて、鋭い洞察と深い思慮に満ちた議論が展開される。痛快きわまりない。
キリスト教を世界に関する誤謬だらけの説明モデルと理解する見解に対して、著者は、神学で問題となるのは、そもそも私たちはなぜ世界に関する説明を求めるのか、また一定の説明が可能だと信じられるのか、といった別次元の事柄である、という認識を示す。
キリスト教を世界に関する誤謬だらけの説明モデルと理解する見解に対して、著者は、神学で問題となるのは、そもそも私たちはなぜ世界に関する説明を求めるのか、また一定の説明が可能だと信じられるのか、といった別次元の事柄である、という認識を示す。
あるいは、信仰とは、特定の存在を信じるか否かの判断ではなく、参加と連帯の問題であり、虐げられた人を含め万人に対して、高質の人間関係を提供するために行動し、現状を変革することであると述べる。
信仰は理性に反すると考える素朴な思い込みに対しては、人間の「知」というものは何かに対する積極的な関与を前提としなければ成立せず、その関与を支えているのが信仰であると主張する一方、人間は理性だけでやっていけるという信念こそ一種の「狂信」に他ならないと論じる。
著者のキリスト教/宗教への根深い信頼とマルクス主義への揺るがぬ傾倒から、非常に興味深い見識が次々と開示されていく。
著者に言わせれば、こうした基本的な見識を持たないドーキンズらによる神学批判など「たとえば、小説を読んで、ここはすばらしい、またちょっとやばいところもあるが、最後は泣かせるという程度のコメントをして自分を専門家と思い込む人間の文学評論めいている」。浅はかなのだ。
著者に言わせれば、こうした基本的な見識を持たないドーキンズらによる神学批判など「たとえば、小説を読んで、ここはすばらしい、またちょっとやばいところもあるが、最後は泣かせるという程度のコメントをして自分を専門家と思い込む人間の文学評論めいている」。浅はかなのだ。
むろん、ドーキンズらは米国などにおける強烈なキリスト教熱を冷ますためにも反宗教論を展開しているのであって、そうした背景についてあまり言及をせず論敵を倒そうと躍起になっている著者のもの言いには多少の違和感がなくはない。
とはいえ、過去も現在も宗教が人間社会において果してきた重要な役割を知っているがゆえに、「神は妄想」という単細胞な割りには妙に人気のある理性(科学)主義的なお話には納得できない読者にとって、本書は大いなる魅力を放ち、そして厚い賢慮を提供してくれることだろう。
現代イングランドを代表するマルクス主義文芸批評家による、邦訳としては初めての宗教書です。
まず、本書は『宗教とは何か』と名付けられていますが、各宗派の教義・信仰形式に関する比較検証や、各派に共通する普遍的価値の解明などを主眼に置くものではありません。
本書の仕事は、「科学と宗教」・「学問と信仰」をそれぞれ切り離し独立させながら「科学の中の宗教的部分」や「学問の中の信仰的部分」を抽出し、反目しがちな「科学と宗教」・「学問と信仰」の架け橋を再構築することです。
それは以下の記述 「トマス・アクィナスは〔彼が行った神の存在〕証明によって神の存在が自明のものになるとは信じていなかった(p159)」 にも表れるように「神の存在肯定と信仰心」を区別することであり、別箇所の 「アブラハムは神に対する信仰を持っていたが、しかし、まずありえないことだが、神が存在しないという思いが彼の中に生じたとしても、おかしくはない(p145)」 という文にも認められます。
それは以下の記述 「トマス・アクィナスは〔彼が行った神の存在〕証明によって神の存在が自明のものになるとは信じていなかった(p159)」 にも表れるように「神の存在肯定と信仰心」を区別することであり、別箇所の 「アブラハムは神に対する信仰を持っていたが、しかし、まずありえないことだが、神が存在しないという思いが彼の中に生じたとしても、おかしくはない(p145)」 という文にも認められます。
これは科学〔絶対〕主義や信仰〔絶対〕主義から本来の宗教的なるものを取り戻す試みであると同時に、学究(学問、理性)と信仰が根源的に両立するという著者の強い信念の表れでもあり、特に後者は他の人文書籍がほとんど提供しない鋭い視点で新鮮に感じました。
私は未読ですが(本書が批判する)リチャード・ドーキンス『神は妄想である』を「心の底では神を信じきれない負い目を払拭する本」と措定できるなら、本書は「心のどこかで神を信じてしまう羞恥心をやわらげる本」と言えるでしょう。
私は未読ですが(本書が批判する)リチャード・ドーキンス『神は妄想である』を「心の底では神を信じきれない負い目を払拭する本」と措定できるなら、本書は「心のどこかで神を信じてしまう羞恥心をやわらげる本」と言えるでしょう。
日本人は信仰を持たない宗教音痴だという言葉を時折耳にしますが、キリスト(イスラム)教圏でも度合いは違っても私たちも共感できる内容を議論していることが伺える好著です。
ただ一方、本書はマルクス主義と社会主義に対する著者の信仰告白書でもあり、神学と政治的実践の結合を目指す内容にもなっています。
ただ一方、本書はマルクス主義と社会主義に対する著者の信仰告白書でもあり、神学と政治的実践の結合を目指す内容にもなっています。
そのため資本主義経済システムへの糾弾、ドーキンスとヒッチンス(併せてディチキンスと略されます)に代表される科学・合理主義イデオローグへの告発や人格攻撃が大部分を占めます。
著者の筆舌は快刀乱麻と評される以上に過度であるため、不必要な誤解・黙殺を引き寄せないことを祈るばかりです。
帯を取るとぐっと厳かな雰囲気になる表紙は、他の宗教書は勿論、ジャック・デリダやエマニュエル・レヴィナスへの追悼文集などにもおとらず落ち着きがあり、読者の政治的立場を問わない貴重な主張が本書に含まれていることの一端を表しているように感じました。詳細な索引有。
帯を取るとぐっと厳かな雰囲気になる表紙は、他の宗教書は勿論、ジャック・デリダやエマニュエル・レヴィナスへの追悼文集などにもおとらず落ち着きがあり、読者の政治的立場を問わない貴重な主張が本書に含まれていることの一端を表しているように感じました。詳細な索引有。
本書は神を信じないドーキンスやデネットの読者に向けて書かれたもの、と思いきやそうでもないようだ。
かといってプロヴィンシャルな宗教哲学者や哲学者に向けられたものでもない。
訳に関してはすべからくの誤用等も見られるが読みやすさは可もなく不可もなくといった所。
神を世界観として解釈する哲学に対し豊富な文学的修辞の宝庫として提示している。
だがアクィナスの世界誕生仮説と世界観の違いがさっぱりわからない。
アクィナスをどう解釈すればそう読めるのか。
ムージルにはそんなことは書いていない。
言語ゲームについて言及した2章でも宗教間の相互通約可能性について理解しているとは言い難い(これは彼の監修した映画ウィトゲンシュタインについても言えることだが)。
4章のマルクス主義が居場所をなくし移動した先が神学だったというのは大いに賛同できるし宗教学では常識に属することだが、ナンシーの仕事などをみるにつけむしろ先人が放棄しやり残した仕事を仕方なく行っているといった様子(ナンシーの仕事自体は評価できるがでは何故イーグルトンはそのような仕事を行わないのか)。
ただ結論で日本のスピリチュアルブームと同じく、人類が本来の姿をとりもどすと云々いったくだりには落胆の念を禁じ得ない。
宗教とは何かとのタイトルに惹かれて手に取るとがっかりさせられる本。
翻訳によるものか、原文が交錯してるためか不明だが、少なくとも宗教
に関する明確な論議がなされているとは感じられず、衒学的な記述の
羅列としかかんじられない。
に関する明確な論議がなされているとは感じられず、衒学的な記述の
羅列としかかんじられない。