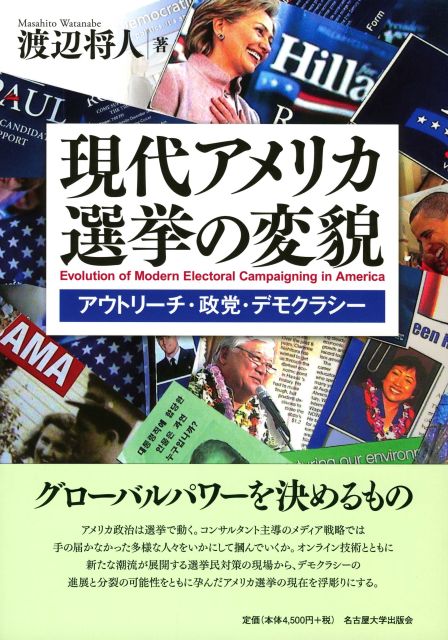「どうしても見せたいものがある」
そういって男性が連れてきてくれたのは、フロリダ州ペンサコーラにある全米屈指の航空博物館だ。見せたいものとは、そこに展示されている旧日本軍の戦闘機「ゼロ戦」だった。
「ゼロ戦と空中戦を戦ったアメリカ軍のパイロットは例外なく、その機体の高い運動性能を恐れていた」
美しい流線型の機体の説明書きにはそう記してあった。
だが私は、ゼロ戦を見るために首都ワシントンから出張してきたわけではない。目的は一つ。トランプ氏を熱狂的に支持した人たちが、選挙のあとどうしているかを知るために、会いに来たのだ。
アポイントをとった退役軍人の男性は、取材を快く引き受けてくれた。そのあとで、ぜひ見せたいものがあるという。
「私は湾岸戦争で、空母艦載機のパイロットをやっていたんだ」
コロナ禍で博物館が公開を制限する中、私が来るのに合わせて、中に入れるようわざわざ担当者に話をつけてくれていたのだ。
ゆっくり眺めていたい気持ちもあるものの、正直、それどころではないという気持ちの方が強かった。出張中に取材できる時間は限られている。博物館の見学よりも、ロケをしていたい。 しかし取材先の好意をむげにすることもできない。
実はトランプ支持者を取材していると、こうした身に余る「おもてなし」をしてくれる人に出会うことが少なくない。「軽い打ち合わせのため」と呼ばれていった自宅で、立派な夕食を用意してくれていた支持者もいた。
繰り返される「ありがとう」
私は去年、アメリカの首都ワシントンに赴任した。ホワイトハウスの担当となり、トランプ前大統領が退任するその日まで一挙手一投足をウォッチし続けた。
日本人の私からすれば、きわどい言動を続けたトランプ氏をなぜあれだけ多くの人が熱狂的に支持していたのかは、興味の尽きない取材テーマだった。
とにかく、彼らに直接会ってみることにした。そこで受けたのが、冒頭に書いたような「おもてなし」の数々だ。
そうした場で異口同音に聞かれるのは、
「自分たちの声に耳を傾けてくれてありがとう」
という感謝の言葉だ。
そして続くのが大手メディアに対する不満だ。
「メディアは自分たちの声に耳を傾けようとしない」
ニューヨーク・タイムズやCNNといったリベラルな主要メディアはもとより、地元のメディアでさえトランプ支持者である自分たちを取材せず、理解しようともしないという。話を聞きに来る私への歓迎は、メディアに対する強い不満と不信感の裏返しのようだ。
日本ではNHKも、そうした不信感を抱く人がいる主要メディアの1つだと口には出せず、私はいつも複雑な思いで話を聞くことになる。
なぜこれほど多くの人が、政府や裁判所がなかったとする、大統領選挙での大規模な不正を信じているのか。
その説明として、インターネットで自分が信じたい情報だけを得ているからだという指摘がある。私はことはそれほど単純ではないと思っている。
トランプ支持者からの「踏み絵」
トランプ支持者の取材では踏み絵を踏まされるような場面に出くわすこともある。トランプ支持者が集まるオンライン上の会合に参加すると、よくこう尋ねられるのだ。
「あなたはどちらを支持しているんだ」
「私は記者なので、どちらかを支持することはない」
そう答えるたびに、彼らの表情から読み取れるのは、なんとも言えないしらけた空気だ。
「なんだそれ?」
そういった声すら聞こえてきそうな表情だ。
保守かリベラルか、トランプ支持か反トランプか。深く分断されたアメリカで「どちらでもない」などという立場は考えられないからだ。
このしらけた表情を、私は過去に嫌と言うほど見てきている。
かつて特派員として暮らした中東のエルサレムでのことだ。出口の見えない紛争を続けるイスラエルとパレスチナの間の溝は限りなく深い。
双方の取材先から「あなたはどちらの側に立っているのか」と聞かれ、「記者なので中立だ」と答えるたびに、あのしらけた表情が返ってきていたのだ。
紛争地ほど「私は中立だ」という言葉がむなしく響く場所はない。誰もそんなことは信じない。相手側がひどいことをやっているのに中立だというのは加担しているのと同じだ、という意識があるからだ。
駐在した3年間、友人が増えるにつれて私がフェイスブックなどのソーシャルメディアに投稿する機会は減っていった。どのカフェに行くのか、どこで買い物をするのか、そうしたたわいない投稿の1つ1つが、それはイスラエル側なのかパレスチナ側なのかに分類されてしまい、「あなたはそっち側を好むのか」というメッセージとして受け止められてしまうからだ。
まさか同じ経験を「自由の国」アメリカでするとは思わなかった。アメリカでも私の投稿には逐一双方からコメントが書き込まれるようになり、次第に投稿は削除するようになった。まるで「2つの世界」が私のフィード上で衝突しているかのようだった。
「メディアが伝えない本当の現実」とは
この日、私はトランプ支持者が好む保守系メディアに向かった。もう1つの世界に足を踏み入れなければ、そちら側からの景色はわからない。
有力な保守系メディア「ワシントン・エグザミナー」の立ち上げに関わったマシュー・シェフィールドさんが取材に応じてくれた。
保守派メディアの創設者と聞いてどんな人物かと構えていたら、緩やかなパーマをかけた洗練された出で立ちで私たちを出迎えてくれた。
シェフィールドさんは、トランプ氏が支持者に対して自分の言うこと以外信じないよう仕向けてきたと指摘した。それは私自身も何度も経験した、トランプ氏が大規模な集会での演説で毎回繰り返してきたパフォーマンスだった。
「Turn the camera. Turn it.(カメラを振るんだ)」
トランプ前大統領は演説を撮影しているテレビカメラの放列に向かってこう発言する。
カメラを左右に振って会場を埋め尽くす支持者を撮影して、どれだけ多くの支持者が集まっているかを伝えるんだ、と要求するのだ。しかし、演説を取り逃すわけにはいかないメディアはカメラを動かさない。
そこで前大統領は「待ってました」といわんばかりにこう発言する。
「メディアはどれだけ人が集まっているか見せたくないんだ。とんでもないフェイクニュースだ」
支持者は大いに盛り上がる。
「なるほど、トランプの言うとおりなんだ。メディアは本当のことを伝えないんだな」
というわけだ。
そして、数千人規模の人々が一斉にテレビカメラの方に向いて顔を真っ赤にして「出て行け」と叫ぶ。カメラの脇に立っていた私は何度もその迫力に気圧されんばかりの感覚を覚えた。こうした手法を積み重ねて大統領はメディアへの不信感を植え付けてきたというのだ。
トランプ支持者が好む、「メディアが伝えない本当の現実」の構図が出来上がり、人々はそこに吸い寄せられていく。
「あなたたちは何もわかっていない」
シェフィールドさんの言葉に私は思わず面を食らった。
「事実かどうかは関係ないんだ」
自分の信じたい現実を否定する事実がどれだけ出てきても、支持者たちが立場を変えない理由を尋ねた時のことだった。
大統領選挙での大規模不正は何度も明確に否定されていた。不正を監視する政府機関も最高裁判所も、トランプ氏への忠誠心が厚いと言われた司法長官も大規模な不正を否定していたからだ。
彼の説明はこうだ。
メディアの人間は人々が報道で事実を知り、それを元に何が正しいのか判断すると思い込んでいるが、現実はその逆だという。分断されたアメリカではまず人々の立場があらかじめあり、その立場を守るための主張や言説を信じるというのだ。
「彼らにとって事実かどうかは関係ない。それよりも保守派の人々にとってはアメリカを変えようとするリベラル派を止めることの方が重要だからだ」
事実かどうかは関係ない?
報道とはファクトを伝えることが最も重要とたたき込まれてきた私にとっては、目からうろこの発言だった。その真意についてシェフィールドさんは次のような見立てを披露してくれた。
社会の価値観が急速に変化する中で、トランプ支持者の中には自分たちが慣れ親しんできたアメリカが急速に変わっていくことに焦りや不安を覚える人が少なくない。 白人主体の人種構成は移民によって大きく変わり、ジェンダーや家族のあり方も変化し、技術革新はフルスピードで社会を変容させている。
「アメリカを再び偉大に」
トランプ氏のスローガンが変化にとまどう人々の琴線に触れるのはそのためだ。
「みなさんが慣れ親しんだあの素晴らしい時代を取り戻そう」
というのだ。
変化が早い都市部にはバイデン支持者が多く、保守的な地方にトランプ支持者が多いことは偶然ではない。価値観が激しくぶつかる中で、トランプ氏の敗北を認めることは、自分の価値観、ひいては自分自身の否定につながってしまうというのだ。
事実が何なのかが関係ないのであれば、報道に身を置く私はどうしたらいいのか。途方に暮れながら彼の自宅をあとにした。
ファクトチェックは「検閲だ」
事実が意味をなさないという言葉のショックが覚めやらないまま、私はそれを裏付けるような場面に出くわすことになる。
いつものようにトランプ支持者が集まる会合に顔を出していたときのことだ。その日は、SNSが話題にのぼっていた。SNS各社が「選挙で大規模な不正が行われた」という真偽不明の投稿の表示を制限していることについてだった。
選挙の信頼性を損なうデマの拡散は危険なことだ。 真偽不明の情報の表示を制限することの何が問題なのか?
私がそう質問すると、即座に答えが返ってきた。
「彼らのファクトチェックは偏っているからだ。トランプ支持者の主張だけをブロックしようとしている。私たちは検閲には屈しない」
発信力の強い政治家の発言が事実でなくても拡散してしまったり、逆に発言の一部だけが都合よく切り取られてしまったりすることはあってはならない。そうしたことを確認する「ファクトチェック」はここ数年、メディアの世界で広く受け入れられている。ニューヨーク・タイムズなどは、大統領選挙後、選挙の信頼性を揺るがすデマのファクトチェックを懇切丁寧に行っている。
しかし結果としてトランプ氏に否定的となれば、支持者にとって目の敵である。メディアへの不信は根深い。実施する主体そのものへの不信があればファクトチェックの結果が「偏った検閲」とみなされてしまう。
これではファクトチェックは機能しない。自分の考えに近い情報だけに囲まれ、それを否定する情報に触れない状況は「フィルターバブル」と呼ばれる。彼らは偽情報のバブルに包まれているわけではない。驚くほど、主要メディアが報じる事実に基づく情報に精通している人も少なくない。にもかかわらず、それを信じていないのだ。
ファクトチェックによって偽の情報の拡散を防げると考えるのはあまりにナイーブな考えだと思い知らされる。彼らにとっては「選挙の不正」の投稿を表示させなくする設定の変更は、大手IT企業が、「真実を握りつぶそうとする」行為にほかならない。
もう1つの世界からの景色が少しずつ見え始めてきた私にとって、もはや驚きではなくなっていた。
「合わせ鏡の世界」
車社会のアメリカでは今もラジオは強力なメディアだ。トランプ支持者に絶大な影響力を持つ保守派の人気パーソナリティーも少なくない。
私はその日、現地の保守派のラジオ番組を取材していた。ホストとゲストの間で繰り広げられたのは、自分たちが見ている「現実」こそが、正しいとの主張だった。
ゲストはこう語った。
「(バイデン大統領の勝利を信じる)人々が偽の情報を信じるのは、それが自分たちが信じたい世界に都合よく当てはまるからだ。私たちは、まるでそれぞれが信じる現実に生きる『不思議の国のアリス』の世界に迷い込んだようだ」
偽の情報であっても、自分たちが信じたい世界に都合よく当てはまる情報だけを信じる、それは…
“それはあなたたちのことではないですか?”
思わずのど元まででかかった言葉を私は飲み込んだ。
「『不思議の国のアリス』の世界」というなんとも絶妙な表現を頭の中で何度も反すうした。
言うまでもなく選挙結果を受け入れないことは民主主義そのものの否定である。しかしトランプ支持者から見れば、不正があるのに見過ごすようなことこそ民主主義を損なうと映っているのだ。
1つしかない選挙結果をめぐって2つの世界が存在するアメリカ。
バイデン大統領就任の直前の世論調査で、バイデン氏を「正当な勝者」とみなす人は共和党支持者の19%にとどまっている。
彼らから見える世界と私から見える世界は、まるで合わせ鏡のようだった。
「合わせ鏡の世界」
それはファンタジーではなく、ついに現実世界に吹き出すことになる…
民主主義の象徴に、暴徒が乱入した
その光景を目にした時、私は最初、何が起きているのかわからなかった。
アメリカの民主主義の象徴とも言える連邦議会。そこに暴徒化したトランプ支持者が乱入したのだ。
議事堂前の広場を数千人の人々が身動きできないほど埋め尽くしている。大統領就任式の準備で立ち入りは禁止されているはずだ。数で圧倒され、なすすべもなく見守っていた警察を見て、当初は当局が立ち入りを許可したと勘違いしたほどだ。
いつも厳重な警備を敷くアメリカの警察は一体どこへ行ったんだ。
平時なら人をかき分けてでも前に進むが、マスクをしないトランプ支持者の海に突っ込んでいく勇気がなかなかわかない。アメリカのコロナの被害は世界最悪なのだ。
手元のスマホは一部の暴徒が議会に乱入し、女性が銃で撃たれたというニュースを断片的に伝えている。 しかし広場を埋め尽くす人々のせいか、携帯の電波はほとんどつながらず、SNSでの情報収集もままならない。
中の議場では大統領選挙の結果を確定させるために大勢の議員がいる。大規模な侵入が起きているなら、重装備の警察が発砲していてもおかしくない。でもそうした音は聞こえない。記者として恥ずかしいことだが、過激な支持者数人が侵入した程度なのかな、くらいしか頭が回らない。
おそるおそる前に進むが人が多すぎて議会に乱入しようとする最前列の人々の姿すら見えない。よもや、後に明らかになる、冒涜行為が議会内で行われているとは知るよしもない。
カメラマンと一緒だった私はテレビカメラ用の大型の三脚を持っている。2人してメディアの人間だとアピールしているようなものだ。「フェイクニュースは出て行け」との怒鳴り声がどこかから聞こえる。
トランプ支持者のメディア不信を考えれば、興奮した群衆に囲まれるのが安全でないのは、かつて3年間駐在した中東での取材経験でも身に染みている。長居は無用だ。
撮影できるものからするしかない。気持ちを切り替えて取材を続けていると、携帯が鳴る。
「90分後に現場から中継してくれ」
途切れ途切れの電話で聞こえたのは、東京からのリクエストだった。最近の中継は携帯のデータ通信を使って行う。そのためには電波が十分届くところまで移動しなければならない。後ろ髪を引かれる思いでいったん引き下がる。
「選挙を盗むのはやめろ」というトランプ支持者の大合唱だけが、いつまでも耳に響いていた。
「あなたをjudgeしない」
トランプ支持者のメディア不信に触れるたびに、私は記者として反省を迫られる気持ちにもなる。不信感の理由には正当な批判も多くあるからだ。
彼らの不満はエスタブリッシュメント(既成勢力)と呼ばれる政治や金融、メディアなど社会に強い影響力を及ぼす組織や人々に向けられている。
都市部に住み、自分たちとは異なる価値観を持ち、時には上から目線のようにも見え、自分たちの声に耳を傾けようとしないエリートたちに対するフラストレーションだ。
地方で暮らす人が多いトランプ支持者にとって、自分たちを理解しようとしないエリートやメディアを一刀両断するかのようにふるまってきたトランプ氏は頼もしく映る。既成勢力を破壊せんばかりの言動に留飲を下げてきた人も少なくない。
“We are finally heard.”(ようやく声が届いた)
トランプ支持者と話していてよく耳にするフレーズだ。誰も耳を傾けなかった自分たちの声をようやく代弁してくれる大統領が出てきたというのだ。
「メディアは人々の声に十分耳を傾けてこなかった」
その批判が的を射たような出来事が、2016年に起きたブレグジットとトランプ大統領を誕生させた選挙だ。世界に衝撃を与えたどちらのケースも、主要メディアは予見できなかった。原動力となった地方で暮らす人々の心情を都市に住む記者たちが理解できていなかったことが原因の1つとされている。
翻って自分はどうか。
市民の声に、真摯に耳を傾けてきたのだろうか。
物事を理解しているというおごりはなかったか。
トランプ支持者のメディア不信は、私自身への批判として心に突き刺さる。
私は今もトランプ支持者の取材を続けている。彼らの声を理解しようとせず、「事実から目を背ける人たち」と片付けてしまうことこそがメディア不信を招いていると思うからだ。
一連の取材で事態の深刻さを目の当たりにした私が、少しだけ希望を感じていることがある。今も週に何度となく、私とトランプ支持者との間でやりとりができていることだ。
彼らから私のスマホに届くのは、バイデン政権がすすめる政策への反発や今になっても選挙の不正を訴えるメッセージだ。私からはバイデン政権が矢継ぎ早に打ち出す政策についてどう思うかを尋ねる。 こうしたやりとりのほとんどすべては、お互いに同意することはない。
それでも当初あった、立場の違う人間に対して、話し始める前から相手を否定し、相手の主張は聞き流し、次にどう反論するかだけを考える、今の分断されたアメリカの姿はそこにはない。
私の仕事は取材先を説得することではなく、立場の異なる人々の意見に耳を傾けることだ。自分の意見を求められても、「あなたの主張はわかるが、私はこう考えている」と控えめに答えるだけにとどめている。
英語には「あなたをjudgeしない」と言うフレーズがある。相手の立場や考えを否定せず、ありのまま受け止める、という意味で使われる。2つの世界を行き来する際に、私はこの言葉を大切にしている。
大統領選挙の大規模不正という、事実とは異なる言説を振りまいたトランプ大統領は退任した。だが、合わせ鏡の危うい状況は当面改善されそうもない。
それでも、そこから抜け出す第一歩は対話だ。
今も続く私たちの会話。
「2つの世界」が少しだけ交わり始めている。
辻 浩平 国際部 ワシントン支局
鳥取局、エルサレム支局、盛岡局(震災担当)、政治部などを経てワシントン支局。オックスフォード大学ロイタージャーナリズム研究所では客員研究員としてメディアのあり方などを研究。取材で忘れられない瞬間は、パレスチナ難民に、「私たちの力になりたいと思って取材しているのか、飯のタネとして取材しているのか、どちらなのか」と問われたとき。占領下で土地や家族を奪われた男性の射貫くような視線に、「どちらもだ」という言葉は軽すぎて、何も言えなかった。取材で大切にしているのは「想像力の射程を伸ばす」こと。相手の立場に身を沈めるくらいでないとなかなか理解できない。アメリカでの趣味は田舎町のダイナーめぐり。