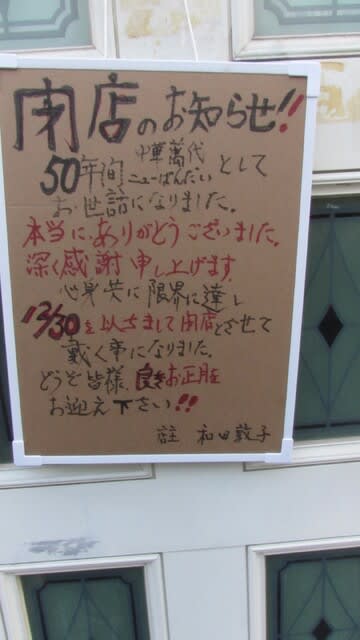12月9日午前4時からCSテレビのブービープラスで観たが、気分が悪くなる映画だった。
白黒画面が続き、突然カラー画像になるのだが・・・奇想天外の展開の連続。
スウィーニー・トッド(Sweeney Todd)は、19世紀中頃の様々なイギリスの怪奇小説に登場する架空の連続殺人者であり、ロンドンのフリート街に理髪店を構える悪役の理髪師である。
トッドの理髪店の椅子には仕掛けがしてあり、裕福な人物を地下に落として殺害し、身に着けていた金品を奪い取る。また、得物として用いる剃刀で被害者の喉を掻っ切ってとどめを刺す。
物語のバージョンによっては、トッドの愛人あるいは友人か共犯者であるパイ屋の女主人(ラベット、マージョリー、サラ、ネリー、シャーリー、クローデット等の様々な名を持つ)が死体を解体してトッドの犯罪を隠匿し、その肉をミートパイに混ぜて焼き上げ、何も知らない客に売りさばく。
トッドはトビアス・ラッグという名の若者も見習いに雇っており、トッドの犯罪に気付いていなかったラッグは物語の後半でトッドの犯罪の暴露に一役買うことになる。
物語のほとんどのバージョンで、トッドは若い婦人ジョアンナ・オークリーと船員マーク・インジェストリー(ミュージカルと2007年の映画ではトッドの娘ジョアンナ・バーカーとアンソニー・ホープ)の駆け落ちに協力するか妨害(時にはその両方)を行う。
トッドは全く架空の人物というわけではない可能性があり、恐怖小説や殺人小説を多く手がける作家ピーター・ヘイニング(英語版)は、2冊の著書[1][2]においてトッドが1800年頃に犯罪に手を染めた実在の人物であると主張している。
しかし、ヘイニングの引用について検証を試みた他の研究者らは、ヘイニングが主張の裏付けとしている出典の中にその論拠を見出せなかった[3][4][5]。
しかしながら、フランスではパリのラルプ通りで起きたというトッドの物語に似た言い伝えが存在する。
経緯
トッドが最初に登場したのは、1846年11月21日の日付が付されたイギリスの犯罪雑誌『ピープルズ・ピリオディカル』第7号であったと思われる[5]。
この雑誌の中でトッドが登場する物語は『The String of Pearls: A Romance』[6]と題され、著者は多数の恐ろしい悪役の生みの親であるトーマス・ペケット・プレストであった。プレストは恐怖物の一部を実話に基づいて執筆する傾向があり、しばしばタイムズ紙の実際の犯罪記事から着想を得ていた。
より初期には、1825年にロンドンで出版された『ザ・テリフィック・レジスター』誌のある号に掲載された、パリのとあるペリュキエ(理髪師)と協力者のブーランジェリー(パン屋)の物語がある[7]。
この物語では、二人の紳士が大事な仕事の途中で髭を剃るために寄り道をし、先に髭を剃り終えた一人目の紳士は、友人を残して仕事のために先に行く。
紳士が友人を迎えに戻ってくると、理髪師は友人はもう行ったと答えた。
しかし奇妙なことに、友人の飼い犬はその場で主人を待ち続けていた。
そして最後に飼い犬のおかげで、理髪師の家の地下に友人の死体が隠されている事が明らかになる。
その地下は隣のパン屋と繋がっており、これが理髪師とパン屋の犯した最初の殺人でないことが示される。
パン屋は定期的に死体の肉からパイをこしらえていたのである。殺人が行われていた場所の上に慰霊碑が立てられた事を告げて、物語は締め括られる。
イギリスの物語によれば、トッドはオールドベイリーで審問を受け、1802年の1月にタイバーンで群集の見守る中絞首刑に処せられたと伝えられている。
しかし、オールドベイリーの裁判記録やニューゲート監獄記録にはそのような法廷の記録は見当たらず、それらの裁判や死刑を報じるいかなる当時の報道記事も存在しない。
加えて、既に18世紀の終わりにはタイバーンで絞首刑は行われていなかった。
早くも1878年にはロンドンの学術雑誌『ノーツ・アンド・クエリーズ』のある寄稿者が、トッドの処刑は現実の出典を欠いている事を指摘している。
『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』 - 復讐に燃える殺人鬼をジョニー・デップが歌って熱演?
知っていれば作品が10倍楽しめる(?)スウィーニー・トリビア
余談だが、2番目のポイントを読んで、ジョニー・デップって以前にも猟奇殺人事件の映画に出ていたんじゃない? と思った人がいたら、それは2002年公開の『フロム・ヘル』のこと。ちょうど同じ時期公開の正月映画で、舞台は同じく19世紀末のロンドン。売春婦などが残忍なやり方で複数殺された、いわゆる「切り裂きジャック」の物語である。ちなみにそのときは捜査官役であった。
さて、次はポイント3と5について。"事実は小説より奇なり"というが、人はフィクションより実話に心ひかれる場合が多いのではないだろうか。また、復讐劇は見ている人間を爽快な気分にさせる。スクリーンの中では、観客が納得できる恨みや憎しみがあれば、殺人も容認され、なおかつ犯人に全面的に肩入れすることが認められているからだ。
 |
|
にっくきターピン検事を追い詰め悪魔の笑みを浮かべる
|
じつは、スウィーニー・トッドについては実在しなかったという主張もある。また、通説のほうを見ても、現在のミュージカルや本作で語られるトッド像とは少し異なる。18世紀のロンドンで、窃盗の罪で監獄へ送られ、そこで理髪師の仕事と解剖学、そして、理髪店の客のポケットから金を盗む技を身につける。出獄後、理髪店を開くが、世間への不満、嫉妬、怒りが連続殺人へと彼を駆り立てていった、というものだ。パイ店のミセス・ラベットと160人以上もの人間を殺したとされるが、この物語を伝えたのは当時のタブロイド紙。記者たちは読者が望むからと、虚実織り交ぜて記事を書いたようだ。最高のネタとなったスウィーニー・トッドは都市伝説化され、結局、トッドが実在したという正確な記述は残っていない。
そして、伝説は19世紀半ばに小説となり、さらに戯曲となって人々の人気を得る。現在の物語、つまり、ターピン判事という復讐の対象が作り上げられたのは、なんと1970年代のことである。
こんな話を聞くと少しがっかりした感も否めないが、より人の心を動かすものにするには、改ざん、改良は大いにやるべし、である。「見たい」と思わせる要素としては断然ノンフィクションのほうが有効であるが、だからといって本当のことが必ずしも感動的とは限らない。センセーショナルな元ネタに多くの人間が味付けをして、よく練られた物語なのである。
ホラー作品という点においても、まさに痛快の一言である。剃刀が当てられた首筋は血を吹き、死体は一瞬にして階下へ転落。そのスプラッター的明快さ、スピード感もこの映画の魅力のひとつであろう。ただ、スプラッター・ムービーを好んで見ない人にとっては、たびたび上がる血しぶきにげんなりしてしまうだろう。
ジョニーの歌声やいかに
そして特筆すべきは7番目。いよいよ本作のミュージカル要素について語ろう。ジョニー・デップはオファーがあったとき、本当に自分が歌えるかを判断するため、昔のバンド仲間に連絡し、曲を研究し、スタジオでのレコーディングに立ち会ってもらったそうだ。本人曰くそれは「かなり奇妙で怖い体験だった」そうだ。
作品の最初から歌う、青ざめたジョニー・デップには正直驚いた。決して下手ではない。ラフに言うと、なーんだ、うまいじゃん、という感じである。それは、ヘレナ・ボナム=カーターしかり、ターピン判事役のアラン・リックマン(『ハリー・ポッター』シリーズでもおなじみ)しかりである。
楽曲は舞台バージョンに変更を加えたもの、新たに作ったものがある。これは映画の上映時間やストーリー展開のスピードを考えてのこと。スティーブン・ソンドハイムが作った歌の世界のすばらしさは、映画でも充分楽しめる。普通の芝居では味わえない、歌のパワーは否定できない。
ただ、私が最もパワーを感じたのは、トッドの娘・ジョアナを愛するアンソニー役のジェイミー・キャンベル・バウアーとパイ店で働き、ミセス・ラベットを慕うトビー少年役のエドワード・サンダースである。とくにジェイミー・キャンベル・バウアーは本作がデビュー作。彼の歌うジョアナへの愛は、切なく胸に残る。彼はとても清潔感のある利発な雰囲気をもっており、これからの活躍が楽しみである。
この作品には、物乞い女役のローラ・ミシェル・ケリーを除いてはプロの歌手は一人もいない。ジョニー・デップを主役に据えることが決まった時点で、その方向性が同時に決まったのではないだろうか。ジョニーから最も歌のパワーを感じることができなかったのがとても残念だし、また、プロではないのだから仕方がないか、とも思ってしまう。結局、ミュージカル好きな人にもホラー好きな人にも不満がでてしまうような気がする。
スティーブン・ソンドハイムがこう語っている。「多くの意味で、彼(バートン監督)にとって最もシンプルで、最も単刀直入な映画になるだろう。だが本当に好きな物語を語る彼を見ることができるはずだ。物語自体が事件性に溢れているから、余分なものを創り出す必要がない。熱意を持って作品に臨み、ただまっすぐに"喉元を突く"だけでいいんだ」。 舞台版と映画版の両方に携わった人間として、彼のこの表現は非常に的確だと思う。この言葉を頭に入れて映画館に行けば、より「スウィーニー・トッド」の世界を堪能できるはずだ。
トッドはスコットランドのフォレスに逃げ延びて、そこで死んで現地の墓地に埋葬されたとの噂もある[8] 。
「スウィーニー・トッド」の名がいつ現れたにせよ、ミートパイを用いた証拠隠滅は19世紀初めの都市伝説であった。1843年のチャールズ・ディケンズの小説『マーティン・チャズルウィット』には、登場人物の一人トム・ピンチが「その界隈が田舎者の屠殺に使われていた事を知らされて、ひどく心を痛めた」とのくだりがある。
ピーター・ヘイニングはトッドが実在の人物であったと主張している[2]が、検証可能な出典は提出していない。
ヘイニングの主張は概ね以下の通りである。トッドは母親から愛される一方で、父親からは虐待され無視されていた。母の愛はトッドへの感化をもたらさなかった。
トッドは法廷で「俺は愛撫され、キスされ、かわいい子と呼ばれた。けれども、後には俺が母を絞め殺せるぐらい強かったらと思うようになった。一体何の因果で、俺は息子に人生を楽しませるだけの財産も持っていない母親の子に生まれたんだ?」と証言したという。