認知症の患者さんは話しかけても返事をしない。
返事があってもトンチンカン。
つまり、会話が成り立たない。
行動も考えていることも予測できない上に、あっと言う間に行方がわからなくなる。
拘束しておかないと家族も社会も迷惑する。
本当に厄介な存在にしか見えないけれども、きっとご本人も苛立っているのだろう。
思う通りにしゃべれない。
思う通りに身体が動かない。
思ってもいないことばかりやってしまう。しゃべってしまう。
だから口をつぐんでいよう。
だからただひたすらじっとしていよう…。
でも、そんなことよりもなんでみんな本当の私を見ようとはしないんだろう?
毎日、メディアで認知症のことが話題にならない日はない。
7年間も行方不明の人がテレビの報道で見つかったり、徘徊の末に鉄道事故を起こしその損害倍賞を遺族が請求されたり、今や、この病気のおかげで誰でもが「加害者」になり誰でもが「被害者」になってしまう世の中になってしまった。
どうしたら認知症になるのを防げるか?
どうしたら徘徊しないようになるのだろうか?
ふと三十年前に読んだある本のことを思い出した。
パトリシア・ムーアというアメリカ人が書いた『Disguised~A true story変装~私は三年間老人だった』だ。
当時若干26歳だった工業デザイナーのムーア氏が、バリアフリーデザインのリサーチのために八十代の老婆に変装して三年間もの間「老い」とは何かを探し求めたというのがこの本の内容だ。
彼女は、この体験をきっかけに老人用デザインというジャンルを開発し専門の会社を作りさまざまなバリアフリー商品を作りだしていった。
私が思い出したのは、この本に書かれたさまざまな出来事ではなく、この本の最後に引用されているある「詩」だ。
この「詩」は、この著作の出版後、介護とか看護の基本的心構えの「規範」としていろいろなところで引用されているので、この詩の存在を知っている人も多いかもしれない。
ケアする人とケアされる人が同じ目線に立たなければならないという認知症ケアメソッド<ユマニチュード>の基本的なアプローチが、「ケアされる人」の視点から書かれているとても良い詩だ。
この「詩」に書かれた老人の心情はきっと三十年前からほとんど変わっていないはずだし、認知症患者だけでなく介護問題を考える上で「絶対に忘れてはいけない」内容だ。
訳本からの引用ではなく原著から自分で訳してみた(日本語としての理解を深めたいという意味で)
「イギリス・アシュルティ病院の老人病棟で一人の老婦人が亡くなりました。
彼女の持ち物を調べていた看護士が、彼女の遺品の中から 彼女が書いたと思われる詩を見つけました。彼女は重い認知症でした」
~『目を開けて、もっと私を見て』~
何を見ているの 看護婦さん あなたは何を見ているの
きっとあなたは私のことをこう思っているんでしょう
あんまり利口じゃない 目はうつろで ノロノロしていて
食べものもボロボロこぼして ロクすっぽ返事もしない
大声で「お願いだからやってみて」といっても 気づかない
靴下や靴はしょっちゅうなくすし なんでも人の言うなり
あり余る一日の時間を満たそうとお風呂に入ったり 食事しているだけの
気難しいおばあさん
これがあなたの考えていることなの? 本当にそれがあなたの見ている私なの?
もしそうだとしたら あなたは私のこと何も見てはいませんよ
もっと目をちゃんと開けて見てごらんなさい
私が誰なのかおしえてあげましょう
ここにじっと座っているこの私が
あなたの命ずるままに動く この私が誰なのかを。
私が10歳の時
私には、父がいて 母がいて 兄弟・姉妹がいて 私たちは皆愛し合っていました
16歳の少女だった私は 足に羽が生えたようにうかれ
もうすぐ恋人に出会えることを夢みていました
20歳で花嫁になった私の心は踊り
約束した誓いを胸に刻みながら毎日を暮らしました
25歳で 私は子どもを産みました
私は子らのために 安心して暮らせる幸福な家庭を作りました
30歳 子どもはみるみる大きくなりました
親子の絆は永遠に続くと信じながら
40歳 子供たちは成長し 家を出ていきました
しかしそれでも夫は 私を優しくそばで見守ってくれました
50歳 再び赤ん坊が 私の膝の上で飛び跳ねました
夫と私は またもや子どもに出会ったのです
でも、つらい日々が訪れました 夫が死んだのです
私は、先のことを考え 不安で震えました
子供達は まだまだ自分たちの生活でいっぱいだったからです
私は 愛にあふれた過去を思い日々を過ごしました
いま私はおばあさんと呼ばれるようになりました
自然は残酷です
老人をまるで何もできない馬鹿のようにしかみせません
体はボロボロ 優美さも気力も失せ
嘗てはこころがちゃんとあったはずなのに 今そこにあるのは石ころだけです
それでも この肉体にはまだ少女の残骸が残っていて
いくどもいくども私の心をふくらまそうとします
私は あまりにも早く過ぎ去ってしまった
喜びや苦しみの日々を思い出し
人生をもう一度愛そうと試みます
そして 永遠なものは何もないという現実に気づくのです
だからちゃんと目を開けて見てください 看護婦さん
私は気難しいおばあさんなんかじゃありませんよ
もっと近づいて もっと私を良く見てください!
(訳:みつとみ俊郎)
返事があってもトンチンカン。
つまり、会話が成り立たない。
行動も考えていることも予測できない上に、あっと言う間に行方がわからなくなる。
拘束しておかないと家族も社会も迷惑する。
本当に厄介な存在にしか見えないけれども、きっとご本人も苛立っているのだろう。
思う通りにしゃべれない。
思う通りに身体が動かない。
思ってもいないことばかりやってしまう。しゃべってしまう。
だから口をつぐんでいよう。
だからただひたすらじっとしていよう…。
でも、そんなことよりもなんでみんな本当の私を見ようとはしないんだろう?
毎日、メディアで認知症のことが話題にならない日はない。
7年間も行方不明の人がテレビの報道で見つかったり、徘徊の末に鉄道事故を起こしその損害倍賞を遺族が請求されたり、今や、この病気のおかげで誰でもが「加害者」になり誰でもが「被害者」になってしまう世の中になってしまった。
どうしたら認知症になるのを防げるか?
どうしたら徘徊しないようになるのだろうか?
ふと三十年前に読んだある本のことを思い出した。
パトリシア・ムーアというアメリカ人が書いた『Disguised~A true story変装~私は三年間老人だった』だ。
当時若干26歳だった工業デザイナーのムーア氏が、バリアフリーデザインのリサーチのために八十代の老婆に変装して三年間もの間「老い」とは何かを探し求めたというのがこの本の内容だ。
彼女は、この体験をきっかけに老人用デザインというジャンルを開発し専門の会社を作りさまざまなバリアフリー商品を作りだしていった。
私が思い出したのは、この本に書かれたさまざまな出来事ではなく、この本の最後に引用されているある「詩」だ。
この「詩」は、この著作の出版後、介護とか看護の基本的心構えの「規範」としていろいろなところで引用されているので、この詩の存在を知っている人も多いかもしれない。
ケアする人とケアされる人が同じ目線に立たなければならないという認知症ケアメソッド<ユマニチュード>の基本的なアプローチが、「ケアされる人」の視点から書かれているとても良い詩だ。
この「詩」に書かれた老人の心情はきっと三十年前からほとんど変わっていないはずだし、認知症患者だけでなく介護問題を考える上で「絶対に忘れてはいけない」内容だ。
訳本からの引用ではなく原著から自分で訳してみた(日本語としての理解を深めたいという意味で)
「イギリス・アシュルティ病院の老人病棟で一人の老婦人が亡くなりました。
彼女の持ち物を調べていた看護士が、彼女の遺品の中から 彼女が書いたと思われる詩を見つけました。彼女は重い認知症でした」
~『目を開けて、もっと私を見て』~
何を見ているの 看護婦さん あなたは何を見ているの
きっとあなたは私のことをこう思っているんでしょう
あんまり利口じゃない 目はうつろで ノロノロしていて
食べものもボロボロこぼして ロクすっぽ返事もしない
大声で「お願いだからやってみて」といっても 気づかない
靴下や靴はしょっちゅうなくすし なんでも人の言うなり
あり余る一日の時間を満たそうとお風呂に入ったり 食事しているだけの
気難しいおばあさん
これがあなたの考えていることなの? 本当にそれがあなたの見ている私なの?
もしそうだとしたら あなたは私のこと何も見てはいませんよ
もっと目をちゃんと開けて見てごらんなさい
私が誰なのかおしえてあげましょう
ここにじっと座っているこの私が
あなたの命ずるままに動く この私が誰なのかを。
私が10歳の時
私には、父がいて 母がいて 兄弟・姉妹がいて 私たちは皆愛し合っていました
16歳の少女だった私は 足に羽が生えたようにうかれ
もうすぐ恋人に出会えることを夢みていました
20歳で花嫁になった私の心は踊り
約束した誓いを胸に刻みながら毎日を暮らしました
25歳で 私は子どもを産みました
私は子らのために 安心して暮らせる幸福な家庭を作りました
30歳 子どもはみるみる大きくなりました
親子の絆は永遠に続くと信じながら
40歳 子供たちは成長し 家を出ていきました
しかしそれでも夫は 私を優しくそばで見守ってくれました
50歳 再び赤ん坊が 私の膝の上で飛び跳ねました
夫と私は またもや子どもに出会ったのです
でも、つらい日々が訪れました 夫が死んだのです
私は、先のことを考え 不安で震えました
子供達は まだまだ自分たちの生活でいっぱいだったからです
私は 愛にあふれた過去を思い日々を過ごしました
いま私はおばあさんと呼ばれるようになりました
自然は残酷です
老人をまるで何もできない馬鹿のようにしかみせません
体はボロボロ 優美さも気力も失せ
嘗てはこころがちゃんとあったはずなのに 今そこにあるのは石ころだけです
それでも この肉体にはまだ少女の残骸が残っていて
いくどもいくども私の心をふくらまそうとします
私は あまりにも早く過ぎ去ってしまった
喜びや苦しみの日々を思い出し
人生をもう一度愛そうと試みます
そして 永遠なものは何もないという現実に気づくのです
だからちゃんと目を開けて見てください 看護婦さん
私は気難しいおばあさんなんかじゃありませんよ
もっと近づいて もっと私を良く見てください!
(訳:みつとみ俊郎)















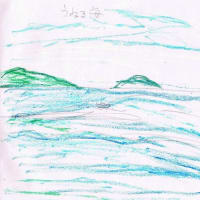


みつとみさんが訳した『目を開けて、もっと私を見て』という詩は、まさに「これだなあ」と思います。やっぱり私の感じていたことを、このご老人が感じていたのです。どんな人にも必ず、若い時があって、恋をして、素敵な人生を送ったり、一生懸命に生きて来た歴史があります。現在の老いた姿でしか判断できない想像力の無さ、本当に情けない限りです。きっと、こういう風に扱われている誰しもが感じているのかもしれません。ただ、「仕方ない」と思い、黙ってそれを受け入れている振りをしているのだと思います。いちいち主張するのも「めんどくさい」ですし…。
どんなに痴呆症になっていろいろなことができなくなっている人でも、自分を表現できないだけで、きっと頭の中ではいろんなことを感じたり考えたりしているのではないでしょうかー。そんなふうに思えてなりません。この詩は、そんなふうに感じていた私に、「やっぱり」という思いを強くさせてくれました。
看護や介護、医療に携わる方々すべての人たちがこういうことを念頭に置きながら仕事をしてくれたならば、患者も、「尊重されている」と、心が満たされるのではないかと思います。「やってあげている」という上から目線ではなく、対等の立場で医療などが受けられたら、どんなにか素晴らしい!
うまく表現できないですが、みつとみさんのこのブログと氏訳の詩に感動しました。