小さい頃,目の前にアメリカがあった。
後年そこに住みそこの大学で勉強することになるとはまったく想像もしていなかった国が,幼い頃の私の目の前に大きく存在していた。
家の回りにはまだバラックすら存在していた。
そんな時代に、いやそんな時代だからこそ、「アメリカ」はそこにあったのかもしれなかった。
現在のNHK放送センターから代々木公園、青少年オリンピック記念センターまでの全てを含む広大な敷地は、ワシントンハイツと呼ばれた「アメリカ」だった。
金網で四方を囲まれた「アメリカ」には青々とした芝生が一面に敷き詰められていた。
ただ、そこがいわゆる「基地」ではなく、米軍のおエライさんたちの宿舎だということを知ったのはもう少し後になってからのことだった。
幼い私の頭の中にあったのは、ごくごく近所にある「未知の世界」であり、日本でありながら日本ではない土地が金網の向こうにあるという感覚だけだった。
それだけでも,少年の気持ちをワクワクさせるには十分だった。
同級生たちもきっと同じ感覚だったのだろう。
いつしか、私たちは当然のごとくそのアメリカに不法「侵入」するようになっていた。
アメリカと日本の「国境」には小学生にとってはとてつもない高さの金網が張り巡らされていたが、な~に,子供は遊びにかけては天才だ。
誰かが金網の破れ目を見つけると私たちは国境を越えやすやすとアメリカへ侵入して行った。
子供たちには,金網をよじ登ることも割れ目から侵入することも造作もないことだった。
私たちは,毎日のように放課後「外国」に行き野球をした。
バットとボールさえあればグローブなど必要ない。
適当にベースを作り野球が始まる。
学校帰りの少年たちにこれ以上の遊びはなかった。
とはいっても,そこが「外国」であることに変わりはない。
不法侵入しているという意識は小学生の私たちにもちゃんとあった。
だから、誰かが訳知り顔でこんな話をする。
「この前AちゃんがMP につかまって一晩泊められたんだってヨ…」。
それを聞いてまわりのガキ共も「ふう~ん、そうなんだ。気をつけなくっちゃ」とわかったような顔をして相槌を打つ。
そんなことはあり得ないことだということが理解できるまでにはまだほんの少し時間が必要だった。
私たちは真顔で「MP につかまらないようにしようね」とお互いの顔を見合わせた。
だから、私たちの野球には必ず「見張り」が必要だった。
見張りが「MPが来たぞ」と大声で叫ぶと私たちは一斉にバットやボールをかき集めて一目散に「日本」へと脱出した。
日本へ戻ってくれば安心。
そんな気持ちを誰もが持っていたからだ。
ただ、実をいうと,私は同級生たちほどMPを怖がってはいなかった。
というのも、私の家にはこのワシントンハイツに勤務する本物のMP(ミリタリーポリス),アメリカの兵隊さんが一人下宿していたからだ。
彼の名前はヘイスさん。
黒人だった。
その頃,アメリカ式のファーストネームだとかラストネームだとかいった区別をまったく知らなかった私にとってその名前が名字だったのか名前だったのかはわかっていなかったし、そんなことはどうでも良かった。
いつもニコニコして私たち兄弟や近所の友達と一緒に遊んでくれる「気のいい外人」が一人家の中にいたという事実だけで私の虚栄心は十分満たされていた。
オレは違うんだゾ。ウチには外人がいるんだゾ。本物のMPが住んでいるんだゾ。
そんな気持ちが,ある日恐怖に変わった。
世の中が安保騒動で騒然としていた昭和35年(1960年)のある日、いつもはニコニコしているはずのヘイスさんが鬼のような形相で家に帰ってきた。
ある事件があった日だった。
毎日のようにデモ隊の警備で出かけ「ヤンキー,ゴーホーム」と学生やデモ隊からののしられてもそれほど顔色を変えることのなかった彼がその日だけは小学生の私が恐怖を覚えるほどの形相と大声で荒れまくっていた。
東大生の樺美智子さんが亡くなる事件の数日前のことだった。
アイゼンハワー大統領の先遣隊として来日しようとした大統領補佐官のハガティ氏の来日を阻止しようとするデモ隊と衝突したその日だった。
ハガティ事件として歴史にも刻まれたその日の彼はまったくの別人の顔を私に見せていた。
彼と私の家で同棲していた日本人女性マリコさんの顔も青ざめていた。
彼はマリコさんに繰り返し尋ねていた。
「なんで,何で?」
絶対に手をあげないと思っていた彼の手がマリコさんの顔を直撃した。
米兵の現地妻として日本人から「オンリー」と差別され後ろ指をさされていたマリコさんを私たち家族は常にかばい続けてきた。
「あいのこ」とか「オンリー」といった今では絶対に使えないような差別用語が巷に氾濫していた時代でもあった。
氾濫していたというよりも,戦争に負けた敵国への好意と憎しみの屈折した感情をそんな「ワード」としてぶつけていただけなのかもしれなかった。
なんでもかんでもアメリカが「ウェルカム」だったわけではない。
ちょうど折悪しく「安保」が格好の標的になっただけなのかもしれなかった。
ヘイスさんもアメリカ人としての職務を全うしているだけなのに「なんで日本人は私たちに悪口を言うのか」ときっと理解できなかったに違いない。
あの日の彼の鬼のような形相にはそんな憤りの気持ちがあったのだろう。
マリコさんは,それを身体を張って受け止めた。
それから数年して私が中学になったある日,その「アメリカ」は本当に「日本」に戻ってきた。
ずっと「アメリカ」として目の前にあったその場所は,ある日突然まったく別のショックを私に与えてくれた。
金網はすっかりはずされ自由に行き来できるようになったその芝生の上に,今度はまったく見慣れない黒人たちがたむろしていた。
ヘイスさんをはじめアメリカの黒人の顔はかなり見慣れていたはずだった。
しかし,「その黒人」の顔は,それまで見た黒人とはまったく違っていた。
「え~? なんなのこの色は? この人たちは一体何なの?」
東京オリンピックのためにワシントンハイツは日本に返還され,その敷地はすべて選手村にあてられていた。
私の見た「黒人」は,アフリカから来た陸上競技の選手だったのだ。
ヘイスさんの「黒」も大半のアメリカ黒人の「黒」も、このアフリカの人たちの「黒」色に比べれば「黒なんかじゃ決してない」。
ただの「褐色」にしか過ぎない。
本当の黒人というのは,こういう人たちのことを言うんだ。
そんな「当たり前のような」事実を,私は,かつて外国だったあの芝生の上で生まれて初めて学習したのだった。
後年そこに住みそこの大学で勉強することになるとはまったく想像もしていなかった国が,幼い頃の私の目の前に大きく存在していた。
家の回りにはまだバラックすら存在していた。
そんな時代に、いやそんな時代だからこそ、「アメリカ」はそこにあったのかもしれなかった。
現在のNHK放送センターから代々木公園、青少年オリンピック記念センターまでの全てを含む広大な敷地は、ワシントンハイツと呼ばれた「アメリカ」だった。
金網で四方を囲まれた「アメリカ」には青々とした芝生が一面に敷き詰められていた。
ただ、そこがいわゆる「基地」ではなく、米軍のおエライさんたちの宿舎だということを知ったのはもう少し後になってからのことだった。
幼い私の頭の中にあったのは、ごくごく近所にある「未知の世界」であり、日本でありながら日本ではない土地が金網の向こうにあるという感覚だけだった。
それだけでも,少年の気持ちをワクワクさせるには十分だった。
同級生たちもきっと同じ感覚だったのだろう。
いつしか、私たちは当然のごとくそのアメリカに不法「侵入」するようになっていた。
アメリカと日本の「国境」には小学生にとってはとてつもない高さの金網が張り巡らされていたが、な~に,子供は遊びにかけては天才だ。
誰かが金網の破れ目を見つけると私たちは国境を越えやすやすとアメリカへ侵入して行った。
子供たちには,金網をよじ登ることも割れ目から侵入することも造作もないことだった。
私たちは,毎日のように放課後「外国」に行き野球をした。
バットとボールさえあればグローブなど必要ない。
適当にベースを作り野球が始まる。
学校帰りの少年たちにこれ以上の遊びはなかった。
とはいっても,そこが「外国」であることに変わりはない。
不法侵入しているという意識は小学生の私たちにもちゃんとあった。
だから、誰かが訳知り顔でこんな話をする。
「この前AちゃんがMP につかまって一晩泊められたんだってヨ…」。
それを聞いてまわりのガキ共も「ふう~ん、そうなんだ。気をつけなくっちゃ」とわかったような顔をして相槌を打つ。
そんなことはあり得ないことだということが理解できるまでにはまだほんの少し時間が必要だった。
私たちは真顔で「MP につかまらないようにしようね」とお互いの顔を見合わせた。
だから、私たちの野球には必ず「見張り」が必要だった。
見張りが「MPが来たぞ」と大声で叫ぶと私たちは一斉にバットやボールをかき集めて一目散に「日本」へと脱出した。
日本へ戻ってくれば安心。
そんな気持ちを誰もが持っていたからだ。
ただ、実をいうと,私は同級生たちほどMPを怖がってはいなかった。
というのも、私の家にはこのワシントンハイツに勤務する本物のMP(ミリタリーポリス),アメリカの兵隊さんが一人下宿していたからだ。
彼の名前はヘイスさん。
黒人だった。
その頃,アメリカ式のファーストネームだとかラストネームだとかいった区別をまったく知らなかった私にとってその名前が名字だったのか名前だったのかはわかっていなかったし、そんなことはどうでも良かった。
いつもニコニコして私たち兄弟や近所の友達と一緒に遊んでくれる「気のいい外人」が一人家の中にいたという事実だけで私の虚栄心は十分満たされていた。
オレは違うんだゾ。ウチには外人がいるんだゾ。本物のMPが住んでいるんだゾ。
そんな気持ちが,ある日恐怖に変わった。
世の中が安保騒動で騒然としていた昭和35年(1960年)のある日、いつもはニコニコしているはずのヘイスさんが鬼のような形相で家に帰ってきた。
ある事件があった日だった。
毎日のようにデモ隊の警備で出かけ「ヤンキー,ゴーホーム」と学生やデモ隊からののしられてもそれほど顔色を変えることのなかった彼がその日だけは小学生の私が恐怖を覚えるほどの形相と大声で荒れまくっていた。
東大生の樺美智子さんが亡くなる事件の数日前のことだった。
アイゼンハワー大統領の先遣隊として来日しようとした大統領補佐官のハガティ氏の来日を阻止しようとするデモ隊と衝突したその日だった。
ハガティ事件として歴史にも刻まれたその日の彼はまったくの別人の顔を私に見せていた。
彼と私の家で同棲していた日本人女性マリコさんの顔も青ざめていた。
彼はマリコさんに繰り返し尋ねていた。
「なんで,何で?」
絶対に手をあげないと思っていた彼の手がマリコさんの顔を直撃した。
米兵の現地妻として日本人から「オンリー」と差別され後ろ指をさされていたマリコさんを私たち家族は常にかばい続けてきた。
「あいのこ」とか「オンリー」といった今では絶対に使えないような差別用語が巷に氾濫していた時代でもあった。
氾濫していたというよりも,戦争に負けた敵国への好意と憎しみの屈折した感情をそんな「ワード」としてぶつけていただけなのかもしれなかった。
なんでもかんでもアメリカが「ウェルカム」だったわけではない。
ちょうど折悪しく「安保」が格好の標的になっただけなのかもしれなかった。
ヘイスさんもアメリカ人としての職務を全うしているだけなのに「なんで日本人は私たちに悪口を言うのか」ときっと理解できなかったに違いない。
あの日の彼の鬼のような形相にはそんな憤りの気持ちがあったのだろう。
マリコさんは,それを身体を張って受け止めた。
それから数年して私が中学になったある日,その「アメリカ」は本当に「日本」に戻ってきた。
ずっと「アメリカ」として目の前にあったその場所は,ある日突然まったく別のショックを私に与えてくれた。
金網はすっかりはずされ自由に行き来できるようになったその芝生の上に,今度はまったく見慣れない黒人たちがたむろしていた。
ヘイスさんをはじめアメリカの黒人の顔はかなり見慣れていたはずだった。
しかし,「その黒人」の顔は,それまで見た黒人とはまったく違っていた。
「え~? なんなのこの色は? この人たちは一体何なの?」
東京オリンピックのためにワシントンハイツは日本に返還され,その敷地はすべて選手村にあてられていた。
私の見た「黒人」は,アフリカから来た陸上競技の選手だったのだ。
ヘイスさんの「黒」も大半のアメリカ黒人の「黒」も、このアフリカの人たちの「黒」色に比べれば「黒なんかじゃ決してない」。
ただの「褐色」にしか過ぎない。
本当の黒人というのは,こういう人たちのことを言うんだ。
そんな「当たり前のような」事実を,私は,かつて外国だったあの芝生の上で生まれて初めて学習したのだった。















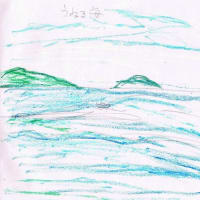


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます