というニュースを聞いてまた「メディアの勘違い」と思ったのだが、私自身もこれまでこうしたメディアに近いところで何十年も仕事をしてきたので、この業界で仕事をしている人たちが陥り易い「思考の罠」が何なのかはよくわかっているつもりだ(もちろん肯定しているわけではなく)。
要するに、ある種の「特権」意識なのだろうと思う。
「自分たちは特別なことをしている。それができない一般大衆の代わりに番組を作ったり、ニュースを伝えたり、文化を作っているんだ」という意識はメディアの世界で働いている人のほとんどが持つ「思考の罠」だ。
今回の熊本のように、地震などの災害の報道も「自分たちがやらなくて誰がやる」ぐらいの気持なのだろうが、今どきスマホ動画で送られる情報の方がよっぽど役に立ったりするし、マスメディアの「あらかじめ結論を決めつけた、上から目線」で編集された報道よりよっぽど「被災者目線」の情報が得られるような気がする。
おそらく、災害時に被災者の気持を一番逆撫でしているのは報道関係者だという自覚はまったくないから、このニュースのように「俺たちが先にガソリン入れて当たり前」的な行動に出られるのだろうと思う。
このメディア人の「奢り」と「勘違い」は今に始まったことではないが、この勘違いは、気をつけないと私たちの誰もが陥る「思考の罠」だ。
音楽家も例外ではない。
音楽家が楽器を演奏できたり歌を上手に歌えたりすることを「特技」と勘違いしている人が多いが、それが大きな「勘違い」につながる。
音楽家がやっていることは、他の人たちと比べて格別優れたことでもないし、「特別な能力」を持っているわけでもない。
もし、私たち音楽家に「何か」が与えられているとしたら、それこそが「才能(ギフト)」なのであって、それが「(天から与えられた)ギフト」であるという自覚さえあれば、そのギフトを使って社会や世の中のために役立てることが音楽家のやるべき仕事だという結論に行き着くはずなのだが、そんな意識で音楽活動を行っている人は少ない。
ある意味、突き抜けた才能を持っている人たちは、自分たちに与えられた「才能(ギフト)」の意味とその使い道をよく知っている。
彼ら彼女らは、それを惜しみなく与え、私たちもその「ギフト」を余すところなく享受する。
この「ギフト」によるコミュニケーションが自然にできる人たちだからだ。
問題は、ハンパにしか音楽を理解せず、ハンパな技術しか持ち合わせない人たち。
勘違いのタネは、そんなところから生まれる。
私たちがメディア人たちの「勘違い」を非難するのは簡単だが、どんな世界でもどんな場面でもハンパな理解やハンパな技術は、取り返しのつかない「勘違い」を産み、世の中をけっして良い方向には導かない。















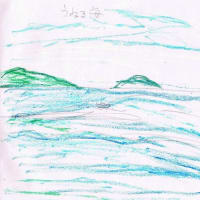


メディア、音楽家に限らず日常いろんな所で感じた疑問が
この勘違いによっておきていることに気づかせて頂きました。わが身に省みなくてはと思います。
今日は外は曇っていますがこころは晴々爽やかになりました。ありがとうございます。
益々のご活躍祈念いたします。