
「やっと布団が干せる」といさんで布団干しにかかる。
これってひょっとして「主婦の感覚?」と思ってしまうが、ここ数日の寒さと天気の悪さに掃除も洗濯もさぼり気味だったのが、天気がよくなった途端急に掃除を始めている自分がいる。
昔から、「俺って主婦だったらパーフェクトかも?」と思うことがしばしば。
学生時代、親友(既に故人なのだが)とその彼女(彼女も私の親友)が駆け落ちして(駆け落ちも死語かナ?)子供を産んだ時、彼女の入院中、その親友の彼の家にいて主婦の代わりをやってあげたことがある(笑)。
大学を中退してもう既に働き始めていた彼が勤めにいっている最中、せっせと掃除をしたり洗濯をしたり炊事をしたりと日常のハウスキーピングをこなす自分がけっこう楽しかった。
まあ、まだ学生という気楽な身分だったからできたことなのかもしれないが、今でも、こうしてハウスキーピングが楽しいという感覚が残っているところをみると、やはり「俺って主婦向きかも?」と思ってしまう(笑)。
今年中に本をまた2冊出版する予定であれこれ調べものをしている。
主に読んでいる本は、音楽と脳の関連についての著作なのだが、これがけっこう面白い。
脳科学者によると、「音楽は、脳のあらゆるレベルの神経構造を使って相互作用による結びつきを促すこと」ということになるらしいが、これだけだとちょっと難しくて「それって何のこと?」だ。
要は、音やことばなどにあわせて自分の身体を動かすことということらしい。
つまり、音を出すことは、他人の身体を動かすことであり、自分自身の身体も自分が出す音によって動いている、ということになる。
だから、音楽と踊りというのは基本的に同じものということにもなってくる。
自閉症の患者の人たちは、この「正常な相互作用の同時性を保てない」ということであるらしい。この同時性というのは、他人と一緒にできない、ということ。
だから、自分勝手な動きをしたり奇声を発したりする症状も現れる。
でも、この著書の定義が一番役に立つのは「だから音楽が自閉症の治療に有効」というポイントだ。
音楽は相互作用による結びつきを高めてくれるのだから、音楽は自閉症にはとっても有効な治療薬になるはずなのだ。
このように、音楽というのは本来、人間生活や社会の根幹に関わるレベルのものだったはずなのだけれども、だんだんと「鑑賞」対象になってしまいそうした視点から音楽を見ることはなくなってきている。
別に、音楽療法という風に見なくても、音楽を聞いて「ガン細胞が減った」なんて事例はけっこうあるし、だからこそそうしたことを真剣に研究している人たちもいるのだと思う。
別の本にはこんな面白い記述もあった。
「新生児は幅広い範囲の声を聞き分けることができる。ところが、6ヶ月ぐらいまでにこの範囲はどんどん狭まってくる」という例として日本の赤ちゃんのことが例として取り上げられている。
「日本の新生児はRとLを聞き分けられるが普通は何ヶ月もするとこの能力を失う」とその本にはある。
要するに、日本の赤ちゃんたちは、自分たちの耳に聞こえてくる音に RとLの区別がないのでその「相互作用」をどんどん捨てていってしまう、のだ。
ことばは、頭で学習するのではなく、環境で学習するのがやはり一番近道、ということか。
これってひょっとして「主婦の感覚?」と思ってしまうが、ここ数日の寒さと天気の悪さに掃除も洗濯もさぼり気味だったのが、天気がよくなった途端急に掃除を始めている自分がいる。
昔から、「俺って主婦だったらパーフェクトかも?」と思うことがしばしば。
学生時代、親友(既に故人なのだが)とその彼女(彼女も私の親友)が駆け落ちして(駆け落ちも死語かナ?)子供を産んだ時、彼女の入院中、その親友の彼の家にいて主婦の代わりをやってあげたことがある(笑)。
大学を中退してもう既に働き始めていた彼が勤めにいっている最中、せっせと掃除をしたり洗濯をしたり炊事をしたりと日常のハウスキーピングをこなす自分がけっこう楽しかった。
まあ、まだ学生という気楽な身分だったからできたことなのかもしれないが、今でも、こうしてハウスキーピングが楽しいという感覚が残っているところをみると、やはり「俺って主婦向きかも?」と思ってしまう(笑)。
今年中に本をまた2冊出版する予定であれこれ調べものをしている。
主に読んでいる本は、音楽と脳の関連についての著作なのだが、これがけっこう面白い。
脳科学者によると、「音楽は、脳のあらゆるレベルの神経構造を使って相互作用による結びつきを促すこと」ということになるらしいが、これだけだとちょっと難しくて「それって何のこと?」だ。
要は、音やことばなどにあわせて自分の身体を動かすことということらしい。
つまり、音を出すことは、他人の身体を動かすことであり、自分自身の身体も自分が出す音によって動いている、ということになる。
だから、音楽と踊りというのは基本的に同じものということにもなってくる。
自閉症の患者の人たちは、この「正常な相互作用の同時性を保てない」ということであるらしい。この同時性というのは、他人と一緒にできない、ということ。
だから、自分勝手な動きをしたり奇声を発したりする症状も現れる。
でも、この著書の定義が一番役に立つのは「だから音楽が自閉症の治療に有効」というポイントだ。
音楽は相互作用による結びつきを高めてくれるのだから、音楽は自閉症にはとっても有効な治療薬になるはずなのだ。
このように、音楽というのは本来、人間生活や社会の根幹に関わるレベルのものだったはずなのだけれども、だんだんと「鑑賞」対象になってしまいそうした視点から音楽を見ることはなくなってきている。
別に、音楽療法という風に見なくても、音楽を聞いて「ガン細胞が減った」なんて事例はけっこうあるし、だからこそそうしたことを真剣に研究している人たちもいるのだと思う。
別の本にはこんな面白い記述もあった。
「新生児は幅広い範囲の声を聞き分けることができる。ところが、6ヶ月ぐらいまでにこの範囲はどんどん狭まってくる」という例として日本の赤ちゃんのことが例として取り上げられている。
「日本の新生児はRとLを聞き分けられるが普通は何ヶ月もするとこの能力を失う」とその本にはある。
要するに、日本の赤ちゃんたちは、自分たちの耳に聞こえてくる音に RとLの区別がないのでその「相互作用」をどんどん捨てていってしまう、のだ。
ことばは、頭で学習するのではなく、環境で学習するのがやはり一番近道、ということか。















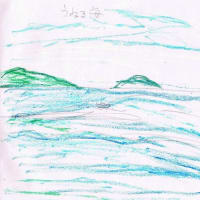


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます