恵子が脳卒中で倒れてはじめて気がついたのは、私自身がこの病気について何も知らなかったということだった。
病気についての認識や知識など、「なってみて初めてわかる」部分がとても多いので、自分の身内である恵子が病魔に襲われて初めてその恐ろしさに気づかされたのも無理からぬことだとは思う。
しかし、ある程度この病気に対する知識が増えてくるにしたがってまた別のことが見えてきたことも事実。
つまり、それは世の中の人が、脳卒中ということば、脳梗塞ということば、そして恵子が罹患した脳溢血(脳出血)ということばの区別をかなり曖昧に使っているということだ。
ある意味、「まったくわかっていない」という人も案外多いのだ。
果たして、脳卒中ということばが、脳梗塞と脳溢血という病気の総称だということを明確に認識している人がどれだけいるだろうか。
脳梗塞は、何らかの原因で脳の血管が詰まること。脳溢血(脳出血と同じ)は何らかの原因で脳の血管が破れ出血してしまうこと。そして、この二種類の脳の病気を総称して脳卒中と呼ぶという初歩的な定義すら世の中ではそれほど共有されているわけではない(脳卒中という病気と脳梗塞という病気が別々にあると思っている人もいる)。
と、ここまでは単なることばの定義だけれども、問題はその中身だ。
脳梗塞と脳出血ではその後遺症の出方はかなり違う。
脳梗塞の発作を何度も何度も繰り返し起こす人がいる。
つまり、詰まってはまた詰まりを繰り返す人だ。
ところが、脳出血はそう簡単には繰り返せない。
詰まったモノならば早い段階で薬で溶かしたりカテールで除去したりはできるけれども、血管がいったん破けてしまったものを修復することは不可能だ。
だから、脳出血とは違い、脳梗塞の場合、発症から処置までの時間が問題になってくる。
つまり、「詰まってから処置までの時間」にどれだけ脳に送る酸素の供給が途絶えるかで後の後遺症、つまり麻痺の程度を左右するからだ。
脳自体にダメージが及ばないうちに血管の詰まりを解決できる可能性のある脳梗塞と違い、いったん破けてしまって脳の一部に酸素が供給されないようになる脳出血がどれだけヤバイ病気なのかは、恵子の麻痺の状態を見てもよくわかる(脳出血患者の後遺症は脳梗塞患者のそれよりも概して重い)。
リハビリによって少しずつ右半身の機能が回復してきているとはいっても、その度合いはミクロレベルだ。
目に見える回復などはそう簡単には望めない。
それでも最後まで「諦めない」ことが患者やその家族にとっての唯一の希望なのだが、そういう病気に対する基礎知識を意外と医療関係者、介護関係者が持っていないことに気づき時折愕然とする。
ある介護施設でお年寄りの身体の一部が痺れて一時的に動けなくなったことがあったそうだ。
それを発見した若い介護士が施設長にこの入居者の処置の判断を仰ぐと「たいしたことないかもしれないから様子を見なさい」と言われたという。
この話、さらっと聞くと、「あ、そうですか」と簡単に受け流してしまいそうな話だが、身体の痛みや痺れというのは明らかに「身体の異常」の危険信号だ。
しかも、このお年寄り、以前にも同じ症状を訴えていたという。
にもかかわらず、この相談を受けた施設長は(病気に対する知識も痺れという症状に対する意識もまったく欠けていたようで)「適当に」処理をしようとしていることがよくわかる。
ことの重大さをまったく認識しようとしていなかったのだ。
心配になった介護士は同じ施設の看護士に相談する(介護士は、概して医療的な判断を許されていない場合が多い)。
看護士は、さすがに痺れが脳疾患の前兆だと見て病院に連れて行った方がよいと判断するが、そのアドバイスも施設長は拒否して「様子を見る」ことに固執したという。
結果としてこの時点では何事も起こらなかったから良かったものの、このお年寄りはいつ何時恵子と同じように倒れてしまうかもしれない。
そうした認識をまったく持たない件の「施設長」は、自分のまわりで「事」が起こって欲しくない一心で「なにごともないことをひたすら願った」だけのような気がしてならない。
本当の「ことなかれ主義」というのは、「ことが起こったら大変だからことを起こさないように万全の処置をする」ことを言うはずなのだが、今の介護の現場には「事件,事故が何も起こらないように」とただただ必死に願うだけで事象に対する判断や処置能力が欠けているのではないかと危惧する。
問題は、「ひとの命」がかかっていることだ。
おそらく、この施設長には自分がひとの命を預かっているという認識が欠けていたのではないだろうか。
もちろん、自分の回りでお年寄りが「徘徊」して欲しくはないだろうし、病気で倒れて欲しくもないだろう。
しかし、相手がお年寄りである以上、そうした「リスク」は常にある。
それをいかにコントロールしてスタッフを上手に使っていくかが施設長たる人間のマネージメント能力なはずなのだが、そうした管理能力のある施設長は案外少ない。
それに、本当に必要なのは、この施設長のように「自分の責任」とか「自分の立場」とかではなく、当事者であるお年寄りの立場にたって物事を判断する「目線」なのではないかと思う。
病院は、健常者(医師、看護士などの病院スタッフ)が病人のお世話をするところ。介護施設は、健常者(介護スタッフ)が身体的、精神的体力の衰えたお年寄りのお世話をするところ。
この関係のままでは、「対等なコミュニケーション」は望めない。
どうしたってスタッフの方がハンデがない分「上から目線」になってしまいがちになる。
だからこそ、「同じ目線で患者を介護しなければならない」というユマニチュードなる「教え(介護/看護メソッド)」が必要になってくるのではないのか。
私も恵子も、「上から目線」の物言いしかできない医師や看護士に何度傷つけられたことか。
医療スタッフに必要なのは、「知識」「技術」だけではなく、「患者と同じ目線」でコミュニケーションを取ることのできる「会話術」も必要なのではとつくづく思う。
それができない人たちがなんと多いことか。
ちょっとだけ、「リケン」という組織のことを思い出した。
私は門外漢なので、単なる「感想」しか言えないが、あの何とか細胞の問題は、ソシキ(しかも、国立の大きな組織だ)を守るために「割烹着理系女子」なる得体の知れないアイコンを作りだして、問題が発覚すると「知らぬ存ぜぬ」でひたすら「ことなかれ主義」を貫こうとする悪しき「官僚主義(=上から目線意識)」の典型なのかなとも思ったりする。
私個人は、問題の「女子」には何の思い入れも見解もないが、やはり、ここで一番私が気になるのは「組織」対「個人」の関係だ。
組織が大きくなればなるほどそこにいる人の立ち位置はどんどん高いところに上っていく。
すると、自然にそこにいる人たちは自分たちの目線の高さに気づかなくなってくる。
自分では相手と同じ目線でモノを話しているつもりがいつの間にか「上から目線」になってしまっているのだ。
組織対個人ではなくても、この目線の問題はあらゆるジャンルのプロとそうでない人との間でも起こることがある。
プロは、案外先入観でモノを判断しがちだ。
(プロであるという)プライドもあるからだ。
先入観や前例、(単なる統計的な)エビデンスだけでモノを判断せずに、ひとりひとりの人間と向き合って「同じ目線」でコミュニケーションを取ることがどれだけ大事なことかと思う。
無知と偏見と傲慢は、時として人の命を平気で奪ってしまう。
「リケン」というソシキでは既に犠牲者が出ている。
件の介護施設に犠牲者が出ないことを切に願うばかりだ。
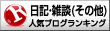
日記・雑談(その他) ブログランキングへ
病気についての認識や知識など、「なってみて初めてわかる」部分がとても多いので、自分の身内である恵子が病魔に襲われて初めてその恐ろしさに気づかされたのも無理からぬことだとは思う。
しかし、ある程度この病気に対する知識が増えてくるにしたがってまた別のことが見えてきたことも事実。
つまり、それは世の中の人が、脳卒中ということば、脳梗塞ということば、そして恵子が罹患した脳溢血(脳出血)ということばの区別をかなり曖昧に使っているということだ。
ある意味、「まったくわかっていない」という人も案外多いのだ。
果たして、脳卒中ということばが、脳梗塞と脳溢血という病気の総称だということを明確に認識している人がどれだけいるだろうか。
脳梗塞は、何らかの原因で脳の血管が詰まること。脳溢血(脳出血と同じ)は何らかの原因で脳の血管が破れ出血してしまうこと。そして、この二種類の脳の病気を総称して脳卒中と呼ぶという初歩的な定義すら世の中ではそれほど共有されているわけではない(脳卒中という病気と脳梗塞という病気が別々にあると思っている人もいる)。
と、ここまでは単なることばの定義だけれども、問題はその中身だ。
脳梗塞と脳出血ではその後遺症の出方はかなり違う。
脳梗塞の発作を何度も何度も繰り返し起こす人がいる。
つまり、詰まってはまた詰まりを繰り返す人だ。
ところが、脳出血はそう簡単には繰り返せない。
詰まったモノならば早い段階で薬で溶かしたりカテールで除去したりはできるけれども、血管がいったん破けてしまったものを修復することは不可能だ。
だから、脳出血とは違い、脳梗塞の場合、発症から処置までの時間が問題になってくる。
つまり、「詰まってから処置までの時間」にどれだけ脳に送る酸素の供給が途絶えるかで後の後遺症、つまり麻痺の程度を左右するからだ。
脳自体にダメージが及ばないうちに血管の詰まりを解決できる可能性のある脳梗塞と違い、いったん破けてしまって脳の一部に酸素が供給されないようになる脳出血がどれだけヤバイ病気なのかは、恵子の麻痺の状態を見てもよくわかる(脳出血患者の後遺症は脳梗塞患者のそれよりも概して重い)。
リハビリによって少しずつ右半身の機能が回復してきているとはいっても、その度合いはミクロレベルだ。
目に見える回復などはそう簡単には望めない。
それでも最後まで「諦めない」ことが患者やその家族にとっての唯一の希望なのだが、そういう病気に対する基礎知識を意外と医療関係者、介護関係者が持っていないことに気づき時折愕然とする。
ある介護施設でお年寄りの身体の一部が痺れて一時的に動けなくなったことがあったそうだ。
それを発見した若い介護士が施設長にこの入居者の処置の判断を仰ぐと「たいしたことないかもしれないから様子を見なさい」と言われたという。
この話、さらっと聞くと、「あ、そうですか」と簡単に受け流してしまいそうな話だが、身体の痛みや痺れというのは明らかに「身体の異常」の危険信号だ。
しかも、このお年寄り、以前にも同じ症状を訴えていたという。
にもかかわらず、この相談を受けた施設長は(病気に対する知識も痺れという症状に対する意識もまったく欠けていたようで)「適当に」処理をしようとしていることがよくわかる。
ことの重大さをまったく認識しようとしていなかったのだ。
心配になった介護士は同じ施設の看護士に相談する(介護士は、概して医療的な判断を許されていない場合が多い)。
看護士は、さすがに痺れが脳疾患の前兆だと見て病院に連れて行った方がよいと判断するが、そのアドバイスも施設長は拒否して「様子を見る」ことに固執したという。
結果としてこの時点では何事も起こらなかったから良かったものの、このお年寄りはいつ何時恵子と同じように倒れてしまうかもしれない。
そうした認識をまったく持たない件の「施設長」は、自分のまわりで「事」が起こって欲しくない一心で「なにごともないことをひたすら願った」だけのような気がしてならない。
本当の「ことなかれ主義」というのは、「ことが起こったら大変だからことを起こさないように万全の処置をする」ことを言うはずなのだが、今の介護の現場には「事件,事故が何も起こらないように」とただただ必死に願うだけで事象に対する判断や処置能力が欠けているのではないかと危惧する。
問題は、「ひとの命」がかかっていることだ。
おそらく、この施設長には自分がひとの命を預かっているという認識が欠けていたのではないだろうか。
もちろん、自分の回りでお年寄りが「徘徊」して欲しくはないだろうし、病気で倒れて欲しくもないだろう。
しかし、相手がお年寄りである以上、そうした「リスク」は常にある。
それをいかにコントロールしてスタッフを上手に使っていくかが施設長たる人間のマネージメント能力なはずなのだが、そうした管理能力のある施設長は案外少ない。
それに、本当に必要なのは、この施設長のように「自分の責任」とか「自分の立場」とかではなく、当事者であるお年寄りの立場にたって物事を判断する「目線」なのではないかと思う。
病院は、健常者(医師、看護士などの病院スタッフ)が病人のお世話をするところ。介護施設は、健常者(介護スタッフ)が身体的、精神的体力の衰えたお年寄りのお世話をするところ。
この関係のままでは、「対等なコミュニケーション」は望めない。
どうしたってスタッフの方がハンデがない分「上から目線」になってしまいがちになる。
だからこそ、「同じ目線で患者を介護しなければならない」というユマニチュードなる「教え(介護/看護メソッド)」が必要になってくるのではないのか。
私も恵子も、「上から目線」の物言いしかできない医師や看護士に何度傷つけられたことか。
医療スタッフに必要なのは、「知識」「技術」だけではなく、「患者と同じ目線」でコミュニケーションを取ることのできる「会話術」も必要なのではとつくづく思う。
それができない人たちがなんと多いことか。
ちょっとだけ、「リケン」という組織のことを思い出した。
私は門外漢なので、単なる「感想」しか言えないが、あの何とか細胞の問題は、ソシキ(しかも、国立の大きな組織だ)を守るために「割烹着理系女子」なる得体の知れないアイコンを作りだして、問題が発覚すると「知らぬ存ぜぬ」でひたすら「ことなかれ主義」を貫こうとする悪しき「官僚主義(=上から目線意識)」の典型なのかなとも思ったりする。
私個人は、問題の「女子」には何の思い入れも見解もないが、やはり、ここで一番私が気になるのは「組織」対「個人」の関係だ。
組織が大きくなればなるほどそこにいる人の立ち位置はどんどん高いところに上っていく。
すると、自然にそこにいる人たちは自分たちの目線の高さに気づかなくなってくる。
自分では相手と同じ目線でモノを話しているつもりがいつの間にか「上から目線」になってしまっているのだ。
組織対個人ではなくても、この目線の問題はあらゆるジャンルのプロとそうでない人との間でも起こることがある。
プロは、案外先入観でモノを判断しがちだ。
(プロであるという)プライドもあるからだ。
先入観や前例、(単なる統計的な)エビデンスだけでモノを判断せずに、ひとりひとりの人間と向き合って「同じ目線」でコミュニケーションを取ることがどれだけ大事なことかと思う。
無知と偏見と傲慢は、時として人の命を平気で奪ってしまう。
「リケン」というソシキでは既に犠牲者が出ている。
件の介護施設に犠牲者が出ないことを切に願うばかりだ。
日記・雑談(その他) ブログランキングへ


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます