が話題になっているけれども、私は開会式のあの映像を見た瞬間から口パクだとは思っていたし(っていうか口パクに決まってるじゃんと逆に信じて疑わなかったけど)、いろいろな民族衣裳着た人たちがたくさん出てきた時も「こんなもん誰が着たってわかりゃしないじゃない」と思っていたので、このことがそれほど重大な問題だとは思ってはいない。
それどころか、これって単にオリンピックがどうのこうのとか国としての威信とか政治とかいった問題でもまったくないと思っている。
むしろ、音楽だとか舞踊だとか、あの開会式のようなエンタテインメント(あえてエンタテインメントだと言い切ってもいいと思う。だからこそ、演出を映画監督が仕切っていたわけだろうし)といったプレゼンテーション(=表現)を受け手がどう見るかといったコミュニケーションの問題でしかないのでは?と思う。
ロサンゼルス・オリンピックでの開会式の場面が今でも思い出される。何百台ものピアノが並びそれが一斉に演奏される。人間ロケットのようなものが飛ばされる。けっこう度胆を抜かれた演出だったが、この開会式にはわりと好感を持てたのはそこに「生身の人間」がいたから(ピアニストが何百人もいたし)。今回の北京では、それが「やらせ」で、実際はCGだったり口パクだったことが判明して非難されているようだけど、それを最初からCGだとか口パクだと承知していれば見方もまったく変わってくるだろうと思う。
世界中のTVのほとんどの音楽番組の「音」は事前にとられている(「ミュージックステーションは、バックミュージシャンだけあてぶりで、歌は「生」という変則スタイルだが)。これを承知している関係者は「そういうものだよ」と理解するけれども、それが実際にその場で演奏されたり歌われていると思い込んでいる視聴者にはそれがそうではなかった時に「裏切り」とうつる。これって、単にコミュニケ-ションが不足していただけの問題じゃないの?と思ってしまう。
お芝居の舞台には「かきわり」という絵や舞台装置であたかも現実の背景や自然、セットが作られているが、観客のすべてはそれが「ウソ」だということを承知して見ている。それでも、それがあたかも「ホント」のように自分自身を思い込ませお芝居の中に感情移入しようとする。そして、役者をお客の感情移入の手助けをする。
これがエンタテインメントの基本だし、舞台と観客の間のコミュニケーションの基本なのでは?と思う。これは、オペラだろうが歌舞伎だろうが、ミュージカルだろうがギリシャ悲劇だろうが基本的に変わるところはない。なぜそれと同じ目線でオリンピックの開会式を見れないのだろうか?オリンピックの開会式にだけ何か特別な「真実」がなければいけないとでも言うのだろうか?
そういうエンタテインメント、ショーとして見れば北京オリンピックの開会式はハリウッド映画以上のエンタテインメントだったろうと思う。おそらくハリウッド映画が何本もとれるようなお金をかけていたのだろうから。それでもそこに批判が集まるというのは、もっと別の理由。つまり、中国という覇権主義の大国に対する周りからの思惑と非難以外の何ものでもない。実際、それ以上でもそれ以下でもないのだ。
私は、あの開会式でピアノを弾いていたランランの横で座って鼻をほじっていた少女を興味深く見ていた。まったく自分がどこにいて何のためにピアノの椅子に座っているかをまったく理解していないような「あの少女の仕種」が開会式の中では一番面白かった。
あの少女は、今頃なにを思っていて、十年後には何を思うのだろうか?
それどころか、これって単にオリンピックがどうのこうのとか国としての威信とか政治とかいった問題でもまったくないと思っている。
むしろ、音楽だとか舞踊だとか、あの開会式のようなエンタテインメント(あえてエンタテインメントだと言い切ってもいいと思う。だからこそ、演出を映画監督が仕切っていたわけだろうし)といったプレゼンテーション(=表現)を受け手がどう見るかといったコミュニケーションの問題でしかないのでは?と思う。
ロサンゼルス・オリンピックでの開会式の場面が今でも思い出される。何百台ものピアノが並びそれが一斉に演奏される。人間ロケットのようなものが飛ばされる。けっこう度胆を抜かれた演出だったが、この開会式にはわりと好感を持てたのはそこに「生身の人間」がいたから(ピアニストが何百人もいたし)。今回の北京では、それが「やらせ」で、実際はCGだったり口パクだったことが判明して非難されているようだけど、それを最初からCGだとか口パクだと承知していれば見方もまったく変わってくるだろうと思う。
世界中のTVのほとんどの音楽番組の「音」は事前にとられている(「ミュージックステーションは、バックミュージシャンだけあてぶりで、歌は「生」という変則スタイルだが)。これを承知している関係者は「そういうものだよ」と理解するけれども、それが実際にその場で演奏されたり歌われていると思い込んでいる視聴者にはそれがそうではなかった時に「裏切り」とうつる。これって、単にコミュニケ-ションが不足していただけの問題じゃないの?と思ってしまう。
お芝居の舞台には「かきわり」という絵や舞台装置であたかも現実の背景や自然、セットが作られているが、観客のすべてはそれが「ウソ」だということを承知して見ている。それでも、それがあたかも「ホント」のように自分自身を思い込ませお芝居の中に感情移入しようとする。そして、役者をお客の感情移入の手助けをする。
これがエンタテインメントの基本だし、舞台と観客の間のコミュニケーションの基本なのでは?と思う。これは、オペラだろうが歌舞伎だろうが、ミュージカルだろうがギリシャ悲劇だろうが基本的に変わるところはない。なぜそれと同じ目線でオリンピックの開会式を見れないのだろうか?オリンピックの開会式にだけ何か特別な「真実」がなければいけないとでも言うのだろうか?
そういうエンタテインメント、ショーとして見れば北京オリンピックの開会式はハリウッド映画以上のエンタテインメントだったろうと思う。おそらくハリウッド映画が何本もとれるようなお金をかけていたのだろうから。それでもそこに批判が集まるというのは、もっと別の理由。つまり、中国という覇権主義の大国に対する周りからの思惑と非難以外の何ものでもない。実際、それ以上でもそれ以下でもないのだ。
私は、あの開会式でピアノを弾いていたランランの横で座って鼻をほじっていた少女を興味深く見ていた。まったく自分がどこにいて何のためにピアノの椅子に座っているかをまったく理解していないような「あの少女の仕種」が開会式の中では一番面白かった。
あの少女は、今頃なにを思っていて、十年後には何を思うのだろうか?















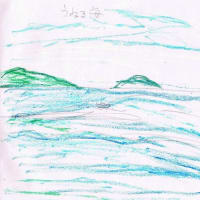


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます