 会員の丸井一郎です。
会員の丸井一郎です。食べる日々(5)
前回までは、
一見同類の食材も、
風土によって性質が異なることを
紹介してきた。
現代のように食材の流通が発達し、
ほぼ全てが商品化される事態は
人類史の中では例外である。
地球上のどこでも、
人類は基本的に
その地で採れる材料で生き延びてきた。
この点で環境へのヒトの適応力は
非常に大きいと言える。
最近の研究では、
先輩格のネアンデルタール人も、
個々の環境に適応して
食生態を発達させたらしい。
通俗的なイメージのように、
頑丈な体格で獣を狩っていたのは、
特定の環境条件に生きる集団であって、
木の実やキノコ類を多食する菜食中心の集団や、
魚類を多量に摂取する集団もあったとされる。
重要なことは、
遺伝子的には同一のヒト達が、
異なる環境の中で、
多様な適応方法を編み出し、
その結果として、
身体的にもそれなりの差異を
発生させたことである(小進化という)。
その適応の結果が
普遍的かつ明確に観察されるのは、
腸内の微生物叢(micro biomミクロ/マイクロ ビオーム/バイオーム)である。
本来不消化の海藻を処理するのは、
お腹の中の特定の微生物である。
それどころか、
狭い意味で「含有する栄養素」には無いはずの
有益な成分(ビタミン、アミノ酸、脂肪酸など)を、
腸内微生物のおかげで摂取できているらしい。
大腸の微生物叢は、
免疫の仕組みや脳の働きにも
関連していることが分かってきた。
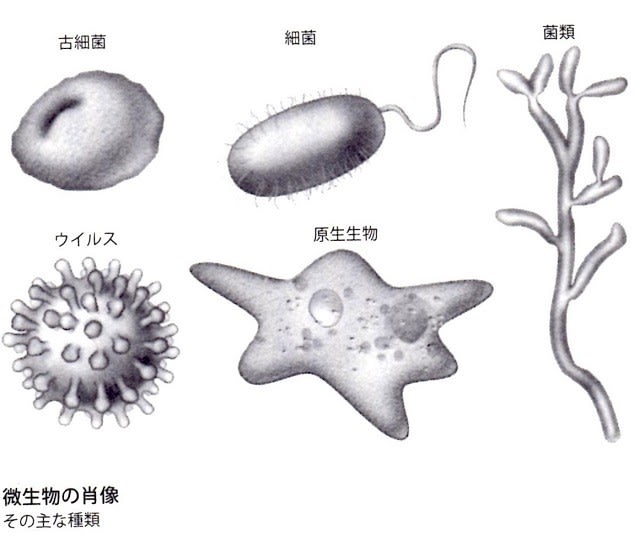
(このイラストは、『土と内臓 微生物がつくる世界』p.26より転載)
(D・モントゴメリー/A・ビクレー著、片岡夏実訳)
(D・モントゴメリー/A・ビクレー著、片岡夏実訳)
※ この記事は、NPO法人土といのち『土といのち通信』2023年11月号より転載しました。

















