
香南市香我美町の月見山のふもとにある旬彩料理「つきみ」です。
皆さまのお役に立ちそうなことを紹介していきます。
★ 大根 ★
これから寒くなる季節に食べたい、おでんサイズの大きな大根を
コトコトと長時間煮るついでに、おいしい大根粥もいただく手順です。

大根は、皮をむき、面取り、隠し庖丁を入れておきます。
皮と面取りしたときに出た大根の切れ端はとっておきます。


むいた大根の皮を厚手の鍋(土鍋がおすすめ)の底に外側を下にして敷き詰めます。
皮を敷き詰めると、焦げ事故防止になり、大根の味もしっかり出ます。
その上に主役の大根を並べます。
大根がしっかり浸かるぐらいの量の水を入れます。

ご飯をひとつかみ、

に加えて火にかけます
(米のデンプンが、大根のアクをとり、甘味を増し、味の浸透を良くする)。
火加減は沸騰直前までは中火、それ以降は弱火で、アクをとりながら、
ときどき上下を返しつつ、大根がフワーっと浮いてくるようになったら下煮完了。
このころにはご飯はお粥になっています。
火からはずし、大根に傷がつかないように慎重にザル上げします。
大根の皮もザル上げしておきます。
鍋の中に残ったお粥と煮汁は欲しい量だけとっておきます。
手で触れるぐらいまで冷まして
大根と大根の皮についたお粥を大根に傷をつけないよう、やさしく洗い流します。

鍋をしっかり洗い、大根の皮を鍋底に初回同様に
敷き詰めて大根を並べ、好みの出し汁を入れてコトコト煮ます。
アクをとりながら沸く寸前まで火を入れたらそのまま自然に冷まし、
また火入れするという作業を3回ぐらい繰り返すと中まで味が入ります。
焦げ被害のない大根の皮は食べやすい大きさに刻んでいただいてください。


大根を出し汁でコトコト煮る長い待ち時間の間に、

でとっておいたお粥と煮汁を温めなおして大根粥をいただきます。
お粥の量が足りない場合はご飯を足します。
あれば、おぼろ豆腐やこんがり炙った厚揚げも入れてコトコト温めます。

器に盛り付け、刻み葱、生姜のすりおろし、すりごま、

の面取りしたときに出た大根を食べやすく切ってトッピング。
醤油をひとたらし、好みでラー油も点々と垂らして熱いうちにどうぞ。
※ この記事は、NPO法人土といのち『お便り・お知らせ』2018年11月号より転載しました。
 梼原町 谷川農園の谷川徹です。
梼原町 谷川農園の谷川徹です。


















 酒かすのプレッツェルは・・・
酒かすのプレッツェルは・・・














 左の第3世界ショップの干しイチジク(ドライフィグ)は・・・・
左の第3世界ショップの干しイチジク(ドライフィグ)は・・・・

 香南市香我美町の月見山のふもとにある旬彩料理「つきみ」です。
香南市香我美町の月見山のふもとにある旬彩料理「つきみ」です。 大根は、皮をむき、面取り、隠し庖丁を入れておきます。
大根は、皮をむき、面取り、隠し庖丁を入れておきます。
 むいた大根の皮を厚手の鍋(土鍋がおすすめ)の底に外側を下にして敷き詰めます。
むいた大根の皮を厚手の鍋(土鍋がおすすめ)の底に外側を下にして敷き詰めます。 ご飯をひとつかみ、
ご飯をひとつかみ、 鍋をしっかり洗い、大根の皮を鍋底に初回同様に
鍋をしっかり洗い、大根の皮を鍋底に初回同様に
 大根を出し汁でコトコト煮る長い待ち時間の間に、
大根を出し汁でコトコト煮る長い待ち時間の間に、 器に盛り付け、刻み葱、生姜のすりおろし、すりごま、
器に盛り付け、刻み葱、生姜のすりおろし、すりごま、



 おつまみ三品
おつまみ三品
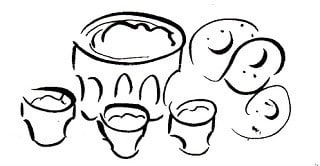

 津野町 天竺舎の山下幸一です。
津野町 天竺舎の山下幸一です。





