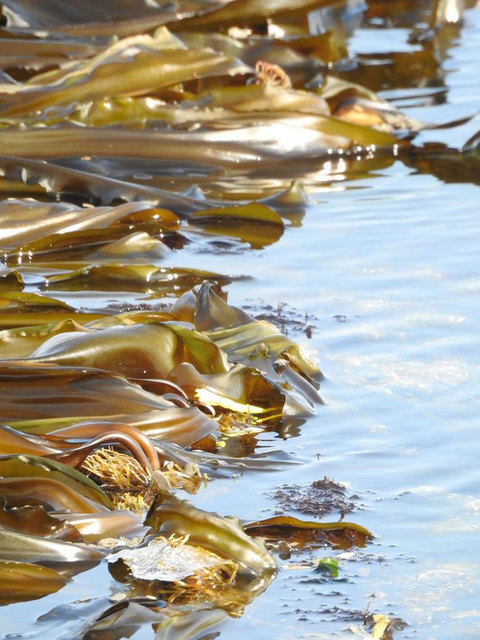安い焼酎は 砂糖を採った後の「廃糖蜜」から作る。
まず 大よそ日本は砂糖全供給量の6~7割以上を 原料になる「粗糖」という形で輸入しています。
「粗糖」というのは サトウキビの生産地である程度不純物を取り除いた濃度の薄い黄褐色の結晶です。
(ちなみに甜菜糖の場合は、ほとんどが生産地で精製まで行われるので、一般には粗糖は作られません。また 余談ですが 輸入された甜菜糖は ほとんど遺伝子組み換えです)
それら「粗糖」を日本国内の製糖会社で精製して砂糖を作ります。
出来る順番としては 最初にグラニュー糖 次が白砂糖 そして三温糖です。
その都度 煮詰め濃縮します。
最終的に 3回程度 煮詰めることから
「三・温・糖」と言います。
三温糖の色は白砂糖が煮詰まり焦げた色なんです。
だから「三温糖を白くしたのが白砂糖」ではなく「白砂糖をとった残りの糖液からできるのが三温糖」であり、基本的な製法は同じです。
(ただし近年は白砂糖にカラメル色素等で着色している三温糖も多い)
そこまで行くと まだ糖分はあるのですが 原料は真っ黒でドロドロの液体「廃糖蜜」というものになります。
その「廃糖蜜」は製糖会社としてはゴミにしかなりませんが それらを有効に使う会社があります。
大手醸造会社や化学調味料の会社がそうです。
醸造会社では 廃糖蜜に残った糖分を原料に アルコールを作ります。
これが醸造用アルコールになり それらを調整して商品化したのが 焼酎甲類 俗にホワイトリカーなどと言われる製品になります。
その他には 清酒に使われる 醸造用アルコールになります。
俗に言う「アル添」の酒。
焼酎でも 乙類は イモや麦 米等から作るのですが 甲類はこれらから出来るものが多いのです。(物によっては米 麦 トウモロコシなどもあります)
化学調味料の会社は 廃糖蜜をバクテリアに与え 化学的な処理をして 最終的に化学調味料を作ります。(これは別ページで紹介)
結局 アル添の酒に入れるアルコールも 焼酎も 化学調味料も 大半の物は 砂糖を作った後の「廃糖蜜」から作られているのです。
a seedプロデューサー