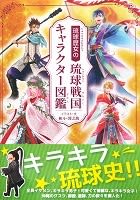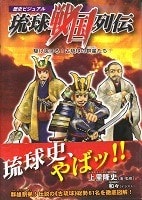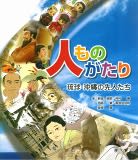途端、漏刻門の太鼓が申の刻を告げる。
連動して首里の寺が一斉に鐘を撞く。

たちまち王都が深錆色の重厚な波紋に包まれた。
「テンペスト(下)」より

首里城の松明に明かりが灯ると、真紅の宮殿はその本来の美しさを見せる。
昼間は華美で豪奢に振舞う役者なのに、
夜になると物憂げな女の眼のようにぼうとその姿を闇に浮かばせる。

宴をそっと抜け出して夜風に吹かれる貴婦人。
それが夜の首里城だ。
「テンペスト(上)」より

王宮には二つの顔がある。

昼間は政治の中枢として知的な顔つきをしているが、
夜は紅をさす貴婦人に変わる。
もともと王宮は男装の麗人なのだ。
女が男に化けていると思えば、いろいろなことが腑に落ちる。

世界の宗教建築にも匹敵する華麗な装飾、
幾重にも着飾った過剰な色彩感覚、
そして美と教養のみに特化した頭脳。
智恵と論理で競い、風流を作法の中にしみこませた役人達は美の僕だ。

しかし、誰がこの美と教養の王国に嵐が襲い来ると思ったであろう。
尚氏開闢から五百年。
文化が爛熟した王国に翳りが差し始めていた。

その翳りさえも美にしてしまうのは神から愛された故だろうか。
男装の麗人から貴婦人に戻った王宮は、
メランコリーに耽っているように映る。
やがて散る身を憂えながらも最新のファッションをさりげなく着こなしてみせる。
これこそが美学だとでもいうように。
「テンペスト(上)」より

はいっ!
ながら~くお伝えしました、写真と文章でたどるテンペスト行脚レポート。
(昨日の前半戦と、今日の後半戦(笑)。全15記事っ
 )
)
一応、これでラストです。
首里城、他にも木門とか西のアザナとか龍譚池とか継世門とか玉陵とか
もうちょっとロケ地があるんですが、
タイムオーバーと言うことで撮れませんでした。
(9時過ぎまで粘ってましたが10:00から美の壺手ぬぐい特集だったから帰らなきゃ…だったのです )
)
また機会があればシリーズ化したいです
同じくタイムオーバーで行けなかった福州園にも行きたいぞー!
一連のレポートは、リンクしている文章を探すのはそんなに難儀じゃなかったです。
もうだいたいあの辺にこの記述があったな~と覚えていたので。
(写真の整理のほうが難儀だったー。何百枚撮ってたんだろう?)
ただ、ワタシがチョイスした文章がベストかどうかは別(笑)
抜粋しました文章は、テンペストという物語の見せ場ではありません。
本当にドキドキワクワクする見せ場はこれ以外に山ほどあります。
是非、この機会にご一読をオススメいたします
あ、そうそう、
以前、記事にした「泊外人墓地」とか「識名園」とかもテンペストロケ地なので
よかったら覗いてみて下さい