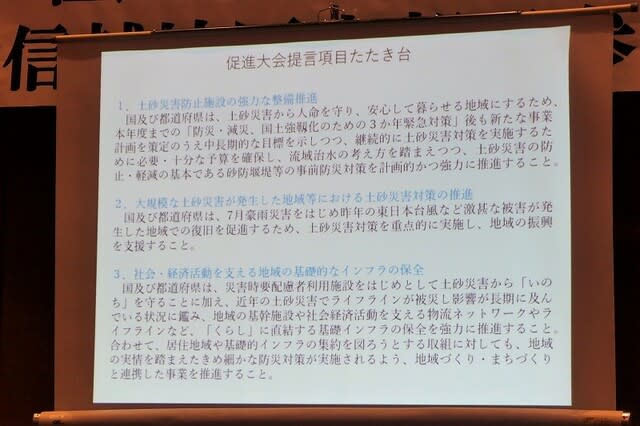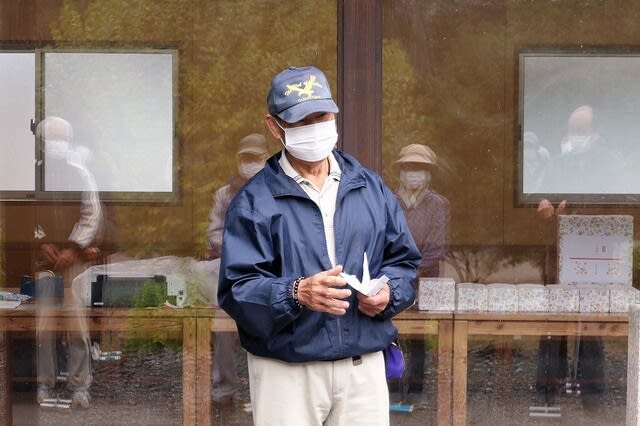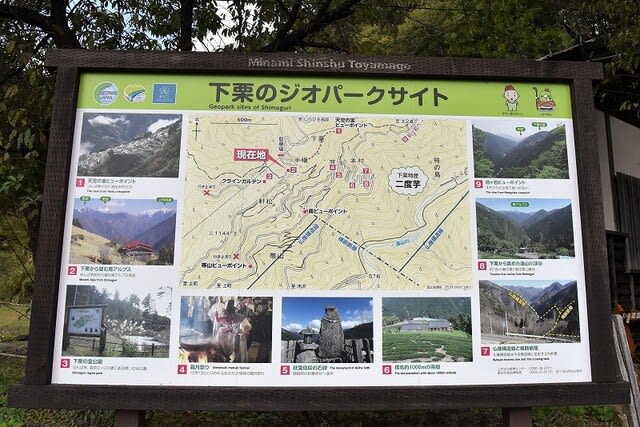22日(木)は雲が多く、夕方以降は雨が降りだし、夜遅い時間ほど本降りになりました。

▽ 毎朝恒例の写真は、視察中ですので、18日(日)に撮影した古坂区方面の風景です。
古坂区方面の風景

視察研修2日目は、早朝に和歌山の高野山、滋賀県の比叡山と並んで日本三大霊場と呼ばれています、恐山に寄りました。


恐山は、カルデラ湖である宇曽利山湖を囲む外輪山と円錐形の火山との総称であり、下北半島の中央部に位置する活火山で、宇曽利山湖の湖畔には、日本三大霊場の一つである恐山菩提寺があります。


霊場内に温泉が湧き、共同浴場としても利用されていて、恐山を中心にした地域は下北半島国定公園に指定されています。


この世のものとは思えない、むき出しの岩が広がる日本屈指のミステリアスな異空間で、例年は観光客も多いですが、やはりコロナ禍と早朝ということもあり、とても少なかったです。


天台宗の円仁(慈覚大師)の開山で古くから霊場として知られ、故人に会うため全国から人が集まります、参拝者が後を絶たないパワースポットとのことでした。



次ぎに青森県下北郡大間町に伺いました。金澤町長さんは、本日がどうしても都合が付かないと昨日ご挨拶に来られ、視察は菊池副町長さん、総務課 傳法参事さん、企画経営課 寺岡参事さん、産業振興課 田中課長さんにご対応をしていただきました。

最初に役場で、菊池副町長さんの歓迎のご挨拶、羽田町村会長さんの視察対応等に対しての御礼の挨拶があり、出席者の紹介で始まりました。



寺岡参事さんから、大間原子力発電所と地域振興のご説明をいただきました。大間原子力発電所は、敷地面積が約130万㎡、原子炉型式が改良型沸騰水軽水炉(ABWR)、燃料が濃縮ウラン及びMOX、出力が138万3千kWであり、工事進捗状況は、令和2年9月現在で37.6%とのことでした。

昭和51年4月に大間町商工会が関連企業の誘致と地場産業の開発振興の観点から、大間町議会に対し原子力発電所設置に係る環境調査の実施を請願し、昭和57年8月に原子力委員会において電源開発株式会社を新型転換炉ATR実証炉の建設、運転の実施主体と決定しました。

昭和59年12月に大間町議会では環境調査終了を踏まえ「原子力発電所誘致」を決議し、平成7年8月に原子力委員会はフルMOX―ABWRを建設する方針を決定し、電源開発は地元町村、青森県へ計画変更を申し入れ、平成12年2月に建設準備工事に着手しました。

平成20年4月に経済産業省が原子炉設置を許可し、工事計画(第1回)を認可し工事に着工しましたが、平成23年3月東日本大震災に伴い原子力発電所本体建設工事を休止し、24年10月に工事が再開するも、25年7月に原子力規制委員会の新規制基準が施行され、工事が休止し、4回の工事再開時期延伸があり、工事再開時期を令和4年後半と見込んでいるとのことでした。

大間原子力発電所に対する交付金及び補助金(電源立地地域対策交付金9種類の交付金・補助金と電源立地等推進対策交付金2種類の交付金)を活用して、北通り種苗育成センターを、全額交付金で建設し、大間町水産振興計画の中核的事業及び大間原子力発電所の地域共生施設の一環として、エゾアワビ種苗生産・育成業務及び漁業者への栽培漁業の技術指導など人材研修により、北通り地域の水産振興を図っているとのことで、漁獲量・漁獲高が順調に推移しており、成果が上がっているとのことでした。
介護福祉振興として、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・デイサービス・訪問入浴介護・訪問介護・地域包括支援センター・配食サービスの業務を行っている、大間町老人福祉施設「くろまつ」は、総工費 908,691千円に対し、各交付金充当額 899,826千円と一般財源8,865千円で平成10年4月開所したとのことで、管理運営方法は、社会福祉法人大間町社会福祉協議会と指定管理料なしの指定管理協定を締結していて、総職員数77名が働いていて、両事業とも各種電源立地等交付金が殆ど充当されていて驚きました。
次ぎに「大間まぐろ」ブランド化の経緯として、津軽海峡付近は、対馬暖流や黒潮の暖流と親潮の寒流がぶつかりあうことでプランクトンが沢山発生し、多様な魚が集まる豊かな漁場を形成していて、昭和30年代になって漁船の大型化や漁具の進歩と相まって豊漁を続け、作家吉村昭の小説「魚影の群れ」で全国的に脚光を浴びました。

大間のマグロは、大間﨑沖1~3kmで釣れる近海物だけに、東京築地市場でも値が高く、外国産の冷凍マグロが1キロ当たり7,000円前後に比べ、軽く数万円の値がつき、高値のため大物は殆ど大市場へ直送され、「地元で美味しいマグロが捕れるのになかなか口に入らない」と嘆く声もあるとのことです。
大間町の年別マグロ漁獲と主な出来事として、昭和58年に映画「魚影の群れ」が放映されましたが、その頃から平成4年まで不漁が続き漁価も低迷しました。平成6年440kgのマグロが水揚げされ、大間町では過去最大を記録し、本州最北端にあるモニュメントのモデルになり、平成10年に完成しました。平成13年築地市場初競りで202kgのマグロが2,020万円(10万円/kg)で落札され、当時の最高値を記録しました。

平成12年のNHK朝の連続テレビ小説「私の青空」から色々な番組で放送され、平成19年の石原プロダクション新春スペシャルドラマ「マグロ」が放送され、さらに有名にあり、大間漁協が「大間まぐろ」として地域団体商標登録をしました。
平成25年には、222kg、15,540万円(70万円/kg)で初めて億超えをしましたが、平成27年には、太平洋クロマグロ小型漁(30kg未満)の漁獲規制が始まり、30年には大型漁漁獲規制も始まり、大型マグロが捕れる時期に漁をする様にしているとのことでした。
平成31年には、豊洲市場初競りで278kg、33,360万円(120万円/kg)の史上最高値で落札されました。

今では「マグロ」といえば「大間産」とすぐに出てくるほど「大間まぐろ」はブランドとして広く認知されるようになり、漁業者の意識が向上し、漁獲後の取り扱いが丁寧になり高品位化され、マグロを求めて多くの人が大間町を訪れるようになり貴重な観光資源になっているとのことでした。


役場の屋上から、大間町内、建設中の大間原子力発電所、北海道函館市方面を眺めながら説明を聞き、大間役場前で記念撮影をして、北通り総合文化センター「ウイング」に向かいました。




ウイングは、大間町、風間浦村、佐井村の3町村からなる北通りの人々を対象にした「文化」「教育」「健康」及び原子力に係る知識向上をめざす複合型文化施設とのことです。


多目的ホール(固定席/287席、可動席465席)、図書室(蔵書数/約2万冊)、屋内運動場(1,300㎡)、室内温水プール(25m×5コース/幼児用プール)、展示コーナー、展望室などがあり、森ねぶた絵師・竹浪比呂夫さんによる、平成26年度知事賞最優秀製作者賞の「大間の天妃神 千里眼と哪吒」の天妃神ねぶたも展示され、下北ヒバを使いチェーンソーで彫り上げた向井勝實さんの玄関前モニュメント「家族 森呼吸」もありました。とても素晴らしい施設で羨ましく感じました。






次は、本州最北端の地「大間崎」に行き、ここは津軽海峡をはさんで、函館市汐首岬までの距離はわずか17.5キロメートルで、天気が良かったので、対岸の北海道を見渡すことができ、函館市内や函館山なども肉眼で確認できました。

大間町の漁師に一本釣りされた440キロのマグロがモデルになっているモニュメントのところで、みんなで記念写真を撮っていただき、津軽海峡と函館市方面の眺望を視察しました。






大間漁協荷捌き場には巨大マグロの水揚げに出会えるかもしれませんでしたが、漁から戻る時間でなく、昨日冷凍庫にあった大型マグロも大市場に直送された後で見ることはできませんでしたが、漁港では多くの漁船を見ることができました。



緊急を要さない疾病やショッピングなどは、距離の近い中核市である函館市を利用する場面が多く、函館市は生活圏の一部ともなっています。各都市圏に移動する場合も、対岸の函館空港を利用した方が、便が良い場合もあり、大間町は函館との航路を維持するためフェリー1艘を無償譲渡するなど、津軽海峡フェリーの支援も行っているとのことでした。

我々がフェリーに乗船して、函館市に向かって出港したとき、大間町の菊池副町長さんはじめ多くの職員の皆さんと公式キャラクター「かもまーる」ちゃんが「へばの~!」「へばの~!」と叫びながら大漁旗を振り、見えなくなるまでお見送りをしていただき感動しました。
大間町の職員の皆さん、関係の皆さんに大変お世話になり素晴らしい視察研修ができましたことに感謝申し上げます。


その後、10月臨時役員会は、協議事項として、長野県市町村職員共済組合の議員等候補者の推薦について協議し、原案通り承認し、報告事項として、長野県自治体労働組合連合からの要請、県への要望運動を含んだ11月役員会の日程、全国町村会の動向等について報告を受け協議をし、それぞれ了承しました。

▽ 毎朝恒例の写真の続きで古坂区方面の風景です。


その他生坂村では、保育園で焼き芋会・園庭開放、小学校で校内教育支援委員会・マラソン事前健診(低学年)、なのはなで焼き芋会、保育園打合せ、民生児童委員協議会などが行われました。

▽ 毎朝恒例の写真は、視察中ですので、18日(日)に撮影した古坂区方面の風景です。
古坂区方面の風景

視察研修2日目は、早朝に和歌山の高野山、滋賀県の比叡山と並んで日本三大霊場と呼ばれています、恐山に寄りました。


恐山は、カルデラ湖である宇曽利山湖を囲む外輪山と円錐形の火山との総称であり、下北半島の中央部に位置する活火山で、宇曽利山湖の湖畔には、日本三大霊場の一つである恐山菩提寺があります。


霊場内に温泉が湧き、共同浴場としても利用されていて、恐山を中心にした地域は下北半島国定公園に指定されています。


この世のものとは思えない、むき出しの岩が広がる日本屈指のミステリアスな異空間で、例年は観光客も多いですが、やはりコロナ禍と早朝ということもあり、とても少なかったです。


天台宗の円仁(慈覚大師)の開山で古くから霊場として知られ、故人に会うため全国から人が集まります、参拝者が後を絶たないパワースポットとのことでした。



次ぎに青森県下北郡大間町に伺いました。金澤町長さんは、本日がどうしても都合が付かないと昨日ご挨拶に来られ、視察は菊池副町長さん、総務課 傳法参事さん、企画経営課 寺岡参事さん、産業振興課 田中課長さんにご対応をしていただきました。

最初に役場で、菊池副町長さんの歓迎のご挨拶、羽田町村会長さんの視察対応等に対しての御礼の挨拶があり、出席者の紹介で始まりました。



寺岡参事さんから、大間原子力発電所と地域振興のご説明をいただきました。大間原子力発電所は、敷地面積が約130万㎡、原子炉型式が改良型沸騰水軽水炉(ABWR)、燃料が濃縮ウラン及びMOX、出力が138万3千kWであり、工事進捗状況は、令和2年9月現在で37.6%とのことでした。

昭和51年4月に大間町商工会が関連企業の誘致と地場産業の開発振興の観点から、大間町議会に対し原子力発電所設置に係る環境調査の実施を請願し、昭和57年8月に原子力委員会において電源開発株式会社を新型転換炉ATR実証炉の建設、運転の実施主体と決定しました。

昭和59年12月に大間町議会では環境調査終了を踏まえ「原子力発電所誘致」を決議し、平成7年8月に原子力委員会はフルMOX―ABWRを建設する方針を決定し、電源開発は地元町村、青森県へ計画変更を申し入れ、平成12年2月に建設準備工事に着手しました。

平成20年4月に経済産業省が原子炉設置を許可し、工事計画(第1回)を認可し工事に着工しましたが、平成23年3月東日本大震災に伴い原子力発電所本体建設工事を休止し、24年10月に工事が再開するも、25年7月に原子力規制委員会の新規制基準が施行され、工事が休止し、4回の工事再開時期延伸があり、工事再開時期を令和4年後半と見込んでいるとのことでした。

大間原子力発電所に対する交付金及び補助金(電源立地地域対策交付金9種類の交付金・補助金と電源立地等推進対策交付金2種類の交付金)を活用して、北通り種苗育成センターを、全額交付金で建設し、大間町水産振興計画の中核的事業及び大間原子力発電所の地域共生施設の一環として、エゾアワビ種苗生産・育成業務及び漁業者への栽培漁業の技術指導など人材研修により、北通り地域の水産振興を図っているとのことで、漁獲量・漁獲高が順調に推移しており、成果が上がっているとのことでした。
介護福祉振興として、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・デイサービス・訪問入浴介護・訪問介護・地域包括支援センター・配食サービスの業務を行っている、大間町老人福祉施設「くろまつ」は、総工費 908,691千円に対し、各交付金充当額 899,826千円と一般財源8,865千円で平成10年4月開所したとのことで、管理運営方法は、社会福祉法人大間町社会福祉協議会と指定管理料なしの指定管理協定を締結していて、総職員数77名が働いていて、両事業とも各種電源立地等交付金が殆ど充当されていて驚きました。
次ぎに「大間まぐろ」ブランド化の経緯として、津軽海峡付近は、対馬暖流や黒潮の暖流と親潮の寒流がぶつかりあうことでプランクトンが沢山発生し、多様な魚が集まる豊かな漁場を形成していて、昭和30年代になって漁船の大型化や漁具の進歩と相まって豊漁を続け、作家吉村昭の小説「魚影の群れ」で全国的に脚光を浴びました。

大間のマグロは、大間﨑沖1~3kmで釣れる近海物だけに、東京築地市場でも値が高く、外国産の冷凍マグロが1キロ当たり7,000円前後に比べ、軽く数万円の値がつき、高値のため大物は殆ど大市場へ直送され、「地元で美味しいマグロが捕れるのになかなか口に入らない」と嘆く声もあるとのことです。
大間町の年別マグロ漁獲と主な出来事として、昭和58年に映画「魚影の群れ」が放映されましたが、その頃から平成4年まで不漁が続き漁価も低迷しました。平成6年440kgのマグロが水揚げされ、大間町では過去最大を記録し、本州最北端にあるモニュメントのモデルになり、平成10年に完成しました。平成13年築地市場初競りで202kgのマグロが2,020万円(10万円/kg)で落札され、当時の最高値を記録しました。

平成12年のNHK朝の連続テレビ小説「私の青空」から色々な番組で放送され、平成19年の石原プロダクション新春スペシャルドラマ「マグロ」が放送され、さらに有名にあり、大間漁協が「大間まぐろ」として地域団体商標登録をしました。
平成25年には、222kg、15,540万円(70万円/kg)で初めて億超えをしましたが、平成27年には、太平洋クロマグロ小型漁(30kg未満)の漁獲規制が始まり、30年には大型漁漁獲規制も始まり、大型マグロが捕れる時期に漁をする様にしているとのことでした。
平成31年には、豊洲市場初競りで278kg、33,360万円(120万円/kg)の史上最高値で落札されました。

今では「マグロ」といえば「大間産」とすぐに出てくるほど「大間まぐろ」はブランドとして広く認知されるようになり、漁業者の意識が向上し、漁獲後の取り扱いが丁寧になり高品位化され、マグロを求めて多くの人が大間町を訪れるようになり貴重な観光資源になっているとのことでした。


役場の屋上から、大間町内、建設中の大間原子力発電所、北海道函館市方面を眺めながら説明を聞き、大間役場前で記念撮影をして、北通り総合文化センター「ウイング」に向かいました。




ウイングは、大間町、風間浦村、佐井村の3町村からなる北通りの人々を対象にした「文化」「教育」「健康」及び原子力に係る知識向上をめざす複合型文化施設とのことです。


多目的ホール(固定席/287席、可動席465席)、図書室(蔵書数/約2万冊)、屋内運動場(1,300㎡)、室内温水プール(25m×5コース/幼児用プール)、展示コーナー、展望室などがあり、森ねぶた絵師・竹浪比呂夫さんによる、平成26年度知事賞最優秀製作者賞の「大間の天妃神 千里眼と哪吒」の天妃神ねぶたも展示され、下北ヒバを使いチェーンソーで彫り上げた向井勝實さんの玄関前モニュメント「家族 森呼吸」もありました。とても素晴らしい施設で羨ましく感じました。






次は、本州最北端の地「大間崎」に行き、ここは津軽海峡をはさんで、函館市汐首岬までの距離はわずか17.5キロメートルで、天気が良かったので、対岸の北海道を見渡すことができ、函館市内や函館山なども肉眼で確認できました。

大間町の漁師に一本釣りされた440キロのマグロがモデルになっているモニュメントのところで、みんなで記念写真を撮っていただき、津軽海峡と函館市方面の眺望を視察しました。






大間漁協荷捌き場には巨大マグロの水揚げに出会えるかもしれませんでしたが、漁から戻る時間でなく、昨日冷凍庫にあった大型マグロも大市場に直送された後で見ることはできませんでしたが、漁港では多くの漁船を見ることができました。



緊急を要さない疾病やショッピングなどは、距離の近い中核市である函館市を利用する場面が多く、函館市は生活圏の一部ともなっています。各都市圏に移動する場合も、対岸の函館空港を利用した方が、便が良い場合もあり、大間町は函館との航路を維持するためフェリー1艘を無償譲渡するなど、津軽海峡フェリーの支援も行っているとのことでした。

我々がフェリーに乗船して、函館市に向かって出港したとき、大間町の菊池副町長さんはじめ多くの職員の皆さんと公式キャラクター「かもまーる」ちゃんが「へばの~!」「へばの~!」と叫びながら大漁旗を振り、見えなくなるまでお見送りをしていただき感動しました。
大間町の職員の皆さん、関係の皆さんに大変お世話になり素晴らしい視察研修ができましたことに感謝申し上げます。


その後、10月臨時役員会は、協議事項として、長野県市町村職員共済組合の議員等候補者の推薦について協議し、原案通り承認し、報告事項として、長野県自治体労働組合連合からの要請、県への要望運動を含んだ11月役員会の日程、全国町村会の動向等について報告を受け協議をし、それぞれ了承しました。

▽ 毎朝恒例の写真の続きで古坂区方面の風景です。


その他生坂村では、保育園で焼き芋会・園庭開放、小学校で校内教育支援委員会・マラソン事前健診(低学年)、なのはなで焼き芋会、保育園打合せ、民生児童委員協議会などが行われました。