
2015年12月にアップしていた1ページを、もう一度、ここにアップします。
ーーー
12月16日(水)、雨模様。
今は夜明け前。
暖かです。
ーーーー
映像は「錦旗」のルーツの駒。
長く、大橋家に後水尾天皇の真筆駒として伝わっっていたもの。
つまり「伝・後水尾天皇真筆駒」と呼ばれた駒。
材は桑木、漆の書き駒。
それを豊島龍山が写して売り出したのが「錦旗」なのです。
駒は、昭和15年頃、木村名人が買い取って、60年に将棋博物館に寄託されて、写真はその時、当方が撮影した半切のパネル。
ミニ博物館でもある小生の仕事場に掲げているものです。
その直前に、木村名人家(3男・義徳さん)から小生に、その駒の鑑定要請があり、茅ヶ崎の木村名人家に伺いました。
名人ご夫妻はご健在で、駒は10組近くを拝見。
昼食には、名人、義徳さんとともに、大好物のうな重をいただきました。
目的の駒は、大橋家から名人が買い取った「後水尾天皇真筆の駒」。
「錦旗」のモデルの駒です。
当時、将棋博物館副館長の木村義徳さんから「本当に、大橋家の伝承どおり後水尾天皇の筆跡かどうか、鑑定して欲しい」とのことでした。
後水尾天皇は子供たちに「芸能と囲碁将棋はしてはいけない」と、訓戒書を残しているにもかかわらず、自分自ら駒を書くなんておかしいな。
と思っていました。
現物を見た結果、鑑定結果、筆跡はまぎれもなく水無瀬兼成そのものでした。
恐る恐るそのことを木村家の人たちに説明すると「そうだろうな・・。とにかく箔をつけたがる。世の中で良くある話」と。
御両人は納得されて、当方はホットしました。
鑑定結果は「将棋世界・博物館だより」にレポート。
つまり「錦旗」は、後水尾天皇の筆跡ではなく、兼成さんが遺した水無瀬駒であったことを、初めて明らかにした次第。










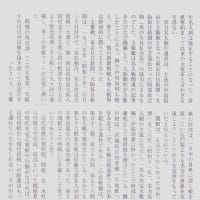















これに対してお答えいたします。
この駒は、大橋家に伝わっていたものです。
大橋家では、そのほかに水無瀬駒として伝えられている駒もありますが、この駒は「後水尾天皇筆」として伝えられてきました。
その理由はよくわかりませんが、小生の解釈では、「天皇が書いた駒」だとすることにより、同家の格を、より高めようとする意図が働いたものと考えます。
木村義徳さんも、同様のことを疑っておられたようで、将棋博物館に寄託するにあたって、大橋家の伝承が正しいのかどうか、ハッキリさておきたい気持ちで、鑑定を小生に要請されたのだと思います。
結果、小生は見た途端、これは水無瀬兼成さんの筆跡に間違いないと直感した次第です。
ですが、そのことを直ぐには言い出しにくい気持ちがよぎりましたが、事前に後水尾天皇の筆跡や訓戒書などを調べており、それらとは合致しないわけで、そのことを名人に申し上げた次第です。
大変貴重なお写真とお話をありがとうございまする。
「将棋駒ものがたり」によりますと、水無瀬兼成卿は
1590年から1602年の13年間に735組の駒を
制作なされたとのことです。駒の制作記録は、
水無瀬神宮に『将棊馬日記』として伝えられているそうです。
錦旗駒のルーツから発展していく駒の歴史は、江戸時代
から明治、大正、昭和から今日まで、続いている
素晴らしい日本の文化ですね。
ご指摘ありがとうございました。おっしゃる通り、大山名人家は誤記でした。大変な間違いで、確認をさぼっていました。
福井さんへ。
イヤハヤ。大きく持ち上げてくださって、恐縮至極です。どうしても、水無瀬兼成さんの筆跡には勝てません。
そのことは、40年ほど前に水無瀬神宮において、熊澤さんが「将棋駒日記」などの資料を再発見し、専門詳細を発表して我々に教えていただいたのです。
「将棋駒ものがたり」は、それを孫引きしているのですよ。