
笛吹川の土手の上から見た八ヶ岳です。
今朝は本当に寒かった。
気温データの上ではもっと寒い朝もあったのでしょうが、あたたかくなり始めた時分のこの気温はこたえます。
周りを見回すと西山と呼ぶ南アルプスの各山々も白さを増しており、さもありなんという気がしました。
朝、回覧板を配って歩いた帰りに八ヶ岳を見るとその雪をかぶった美しさに思わず見とれてしまいました。
さっそく家に戻りカメラを持って土手に向ったのですが、一歩遅く誰かが燃やした煙に美しさが損なわれてしまいました。
風の無い朝だったので気持ちはわからないでもないですが。
川向こうのことなので文句も言えず...。
思えば八ヶ岳は、小さなときからいやでも目に映る大きな山でした(って過去形で言う話ではありませんが)。
甲府盆地の南の端に位置する我が家からは前衛の山にさえぎられて富士山が見えません。
ですから山といえば八ヶ岳、だったわけです。
裾野の大きさは富士山にひけをとりません。
噴火により先端部が崩壊しなければ富士山より大きかったかもしれません。
まあ崩れたおかげで八ヶ岳と呼ばれる名前になったのでしょうが。
山梨には昔から八ヶ岳と富士山が背比べをしたという話が残っています。
両方の山の間に樋を渡して水を注いでみた(誰が?と突っ込みたくなりますが)。
富士山の方が高かったので「どうだ」とばかりに富士山に叩き潰された、という説と、
八ヶ岳の方が高いことをくやしがった富士山が、やはりたたいてつぶした、という説があるようです。
いずれにしても現在の富士山と八ヶ岳との間には900メートル近い差がありますが、地質的には今から25万年前の古い八ヶ岳は3,400メートルあったとされています。
一方その当時の富士山(小御岳山)は2,400メートル。八ヶ岳の方がずっと高かったようです。
興味のある方は こちら を。
上記文献「伝説r富士山と八ヶ岳の背くらべ」の地質学的考察」によれば、八ヶ岳の崩壊は噴火口が移動したことにより崩れてしまったもののようです。
事実としてはそうなのでしょうが、私としてはやはり「富士山犯人説」を取りたいな。
今朝は本当に寒かった。
気温データの上ではもっと寒い朝もあったのでしょうが、あたたかくなり始めた時分のこの気温はこたえます。
周りを見回すと西山と呼ぶ南アルプスの各山々も白さを増しており、さもありなんという気がしました。
朝、回覧板を配って歩いた帰りに八ヶ岳を見るとその雪をかぶった美しさに思わず見とれてしまいました。
さっそく家に戻りカメラを持って土手に向ったのですが、一歩遅く誰かが燃やした煙に美しさが損なわれてしまいました。
風の無い朝だったので気持ちはわからないでもないですが。
川向こうのことなので文句も言えず...。
思えば八ヶ岳は、小さなときからいやでも目に映る大きな山でした(って過去形で言う話ではありませんが)。
甲府盆地の南の端に位置する我が家からは前衛の山にさえぎられて富士山が見えません。
ですから山といえば八ヶ岳、だったわけです。
裾野の大きさは富士山にひけをとりません。
噴火により先端部が崩壊しなければ富士山より大きかったかもしれません。
まあ崩れたおかげで八ヶ岳と呼ばれる名前になったのでしょうが。
山梨には昔から八ヶ岳と富士山が背比べをしたという話が残っています。
両方の山の間に樋を渡して水を注いでみた(誰が?と突っ込みたくなりますが)。
富士山の方が高かったので「どうだ」とばかりに富士山に叩き潰された、という説と、
八ヶ岳の方が高いことをくやしがった富士山が、やはりたたいてつぶした、という説があるようです。
いずれにしても現在の富士山と八ヶ岳との間には900メートル近い差がありますが、地質的には今から25万年前の古い八ヶ岳は3,400メートルあったとされています。
一方その当時の富士山(小御岳山)は2,400メートル。八ヶ岳の方がずっと高かったようです。
興味のある方は こちら を。
上記文献「伝説r富士山と八ヶ岳の背くらべ」の地質学的考察」によれば、八ヶ岳の崩壊は噴火口が移動したことにより崩れてしまったもののようです。
事実としてはそうなのでしょうが、私としてはやはり「富士山犯人説」を取りたいな。










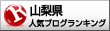
















八ヶ岳は毎日見ている山ですので、すごく身近に感じます。
世界遺産への登録を目指している富士山ですが、確かにこの美しい姿が未来永劫続くわけではないのでしょうね。今の私たちはラッキーなのかもしれないです。