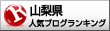恒例の味噌造りを行いました。
庭に大きな釜を据え付けて、大豆を煮ます。
燃料は柿、梅、はちすなどの庭木の枝。
始めは強い火力で、しかし吹きこぼさないように焚いていきます。
ときどき大きなしゃもじで豆をかき混ぜて焦げないように注意しなければなりません。
このあたりが一番難しい所でしょうか。
中のお湯が沸騰するようになったら火力を弱め、豆が指で簡単につぶれるくらいまで煮ます。
およそ三時間くらい、火を絶やさないように気を付けます。

豆が煮えたところで火を止め、用意したざるに均等に分けていきます。
写真では、元の豆で1キログラムずつに分けたところ。
この状態で、豆の粗熱を取り除いていきます。
熱が大分さめたところで、ミキサーにかけて豆をすりつぶします。

電動なので、8キログラムの煮た豆はあっという間にすりつぶされていきます。
このあたりはとにかく手早く手早く。
すりつぶした豆に糀(米麹と麦糀を調合したもの、比率はそれぞれの家庭で異なります)と塩を混ぜ合わせて適当な量にしたものを容器に入れます。

こうしてできた味噌は、台所の床下収納に入れて約半年貯蔵すると、美味しい味噌の出来上がり。
子供が「味噌が変わった?」というほど、独特の味の味噌になるのです。
文字通りの「手前味噌」ですね。
庭に大きな釜を据え付けて、大豆を煮ます。
燃料は柿、梅、はちすなどの庭木の枝。
始めは強い火力で、しかし吹きこぼさないように焚いていきます。
ときどき大きなしゃもじで豆をかき混ぜて焦げないように注意しなければなりません。
このあたりが一番難しい所でしょうか。
中のお湯が沸騰するようになったら火力を弱め、豆が指で簡単につぶれるくらいまで煮ます。
およそ三時間くらい、火を絶やさないように気を付けます。

豆が煮えたところで火を止め、用意したざるに均等に分けていきます。
写真では、元の豆で1キログラムずつに分けたところ。
この状態で、豆の粗熱を取り除いていきます。
熱が大分さめたところで、ミキサーにかけて豆をすりつぶします。

電動なので、8キログラムの煮た豆はあっという間にすりつぶされていきます。
このあたりはとにかく手早く手早く。
すりつぶした豆に糀(米麹と麦糀を調合したもの、比率はそれぞれの家庭で異なります)と塩を混ぜ合わせて適当な量にしたものを容器に入れます。

こうしてできた味噌は、台所の床下収納に入れて約半年貯蔵すると、美味しい味噌の出来上がり。
子供が「味噌が変わった?」というほど、独特の味の味噌になるのです。
文字通りの「手前味噌」ですね。