













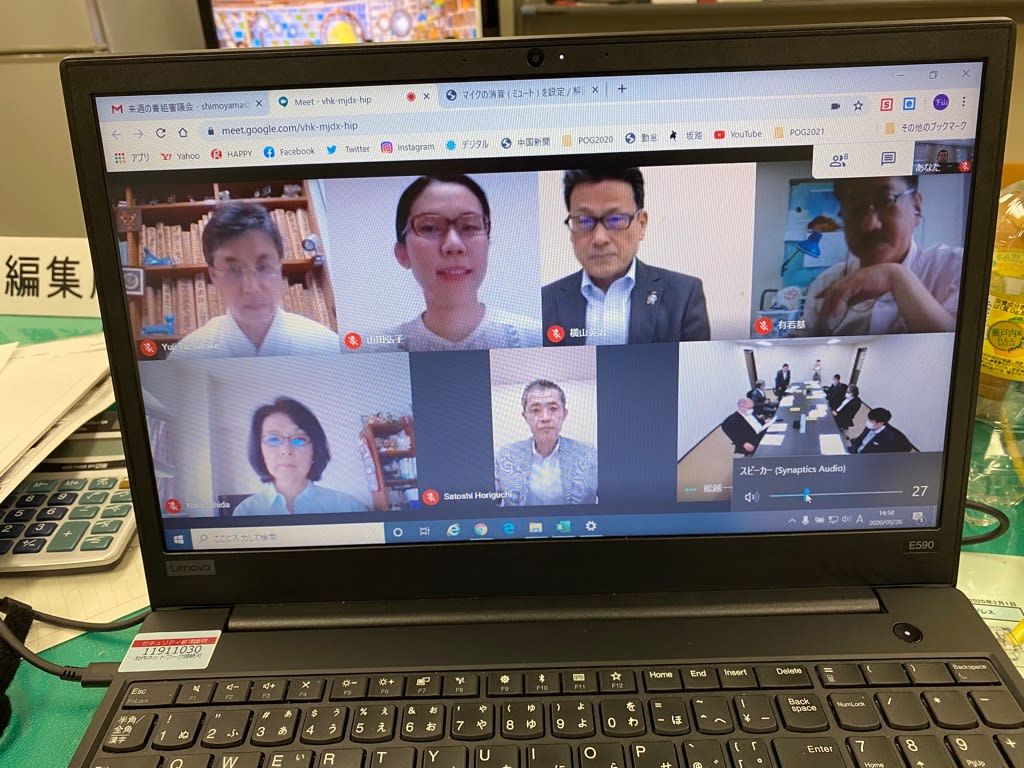























読書文化の普及に貢献するためのチャレンジで、好きな本を1日1冊選び、本についての説明はナシで表紙画像をFacebookへ7日間アップを続ける。その際毎日1人のFB友達を招待し、このチャレンジへの参加をお願いする。というもの。
だそうな。割と流行ってるみたい。
しかし、誰にバトンを渡すかにも迷うし、俺で打ち止めにしちゃいました。
その代わり、数冊ほど一気にご紹介。
それぞれの年代で、俺の胸を撃ち抜いた作品だ。
その時の境遇や心模様が投影されているし、逆に作品が僕という人間を形作ったともいえる。
まずはこれ。
小学一年生の時だと思う・
とにかく心を奪われたなあ。
俺が今でもみんなで仕事をするのが好きなのは、こうした作品に触れたからかもしれないな。
そして中学生に。
繁華街の本屋さんをはしご。とにかくうろうろ。
書棚の本の位置が変わるとすぐに気づくほどに、本屋に通ったなあ。
そこで出会ったのがこれだ。
吉行淳之介。
「性」を窓口に人間を描くってことなんだけど、とにかく文章がキラキラしてた。
こんな文章を書きたいと、心から思ったな。
大学では妄信的に国文学科に進み、近代文学を学んだ。
卒論はもちろん吉行。
上野毛の自宅を訪ねたけど、呼び鈴が押せなかった。
あそこで押してたら、俺は大学院に行ってたんだろうなあ。
まあ、人の進路なんてのは、偶然と必然が絡み合ってるわけだけどね。
そして高校時に心を撃ち抜かれたのがこれだ。
中島敦については、こんなことを書いたことがある。
芥川賞と「虎」 冬の曇天に春の風が吹き抜けたようだった。広島市佐伯区の小山田浩子さん(30)が、「穴」で第150回芥川賞を受賞した。その一報に接した際は身震いを覚えた。 というのも、芥川賞は直木賞とともに、文壇の最大行事として存在感が突出しているからだ。社会現象的なとらえ方に批判もあるが、この国の純文学の歴史であることも確かである。 その分、落選作家の悲憤慷慨(こうがい)には事欠かない。第1回からしてそうだ。薬代に賞金500円を熱望した太宰治は落選。選考委員の川端康成の選評に憤り、「刺す、さう思った。大悪党だと思った」となじった。 もっとも、この時に受賞していたら太宰はどうなっていたか。無頼と苦悩に彩られた彼だっただろうか。初のノミネートだった小山田さんの受賞を喜びながら、ふと思った。
思いを巡らせた作家がもうひとりいる。太宰と同じ1909年に生まれ、太宰の落胆から十数年後、川端の選考のもと、同様に落選した中島敦である。30代の早世も似通っている。 臆病な自尊心と尊大な羞恥心―。思春期に胸を射貫かれた人は多い、中島の「山月記」のフレーズだ。才能がないと認めるのは恐れているものの、しゃにむに努力することもまた厭(いと)う。そんな心中の「虎」はいつしか主人公を本当の虎に変えてしまう。
だれもが心中に「虎」を飼う。小山田さんもまた、この道で夢を諦めかけた。三島由紀夫の才能に圧倒され、同世代の綿矢りささんらの登場に夢が遠のいたと感じた。挑戦せず沈んだそんな時期を、夫の励ましもあって乗り越えてきた。 虎」をならし、夢をどこまで追いかけられるか。自分をどこまで信じられるか。諦めの悪さの向こうに何かが待っていると信じたい。それは文学に限った話ではないのだろう。
ここに書いてあるのは、私自身の話でもある。
思春期の懊悩にここまでフィットする作品はないと思える。
そんな少年も青年となり、やがて組織の垢にまみれるオッサンになる。
であれば、さまざまに迷う。
仕事自体も少し特殊だ。
人々を励ますこともあれば、棒っ切れでぶん殴るようなこともある。
もちろん殴るこちらも痛みを伴うわけで、覚悟とささやかな誇りがなければやってられないわけだ。
一方で、キャリアを重ねると、理想論では通らないことにも出会う。
ただそれでも、自分を貫くこと、誇りを捨てないことが大切なんだろうと思う。
他人を棒っ切れでぶん殴った以上、組織のために自分を曲げては申し開きができないからだ。
それでいくつもの失敗をしてきたが、それはそれでまったく後悔はない。
そしてもう一つ、大事なことがある。
一緒に火の海を渡ってくれる、一緒に損を被ってくれる、そんなダチが見つかるかどうか、見つけられるかどうか。
これは実に大きいわけだ。
てなことを考えさせられたのがIWGPシリーズだ。
そう、これ。
若造のマコトにいろんなことを教えてもらったよ。
初心やら矜持やら、いろんなことを思い起こさせるブックカバーチャレンジでした。
花田さん、ありがとう。