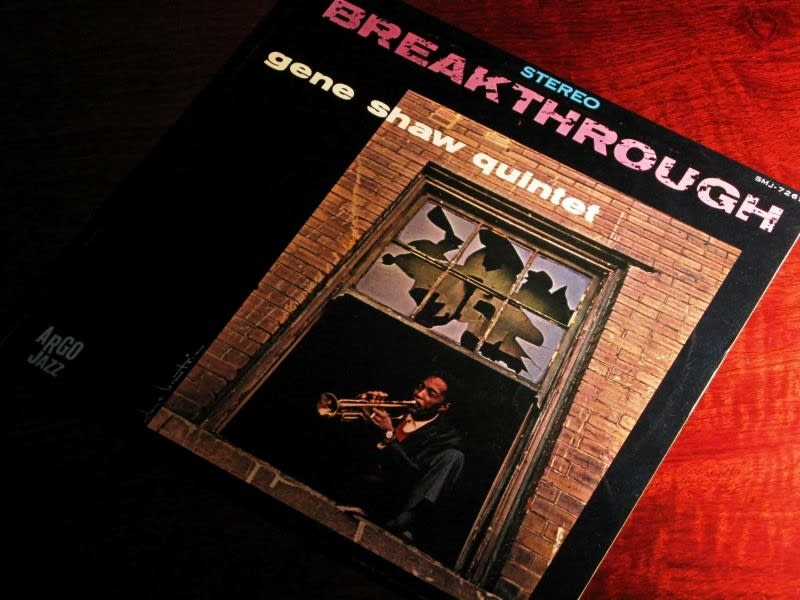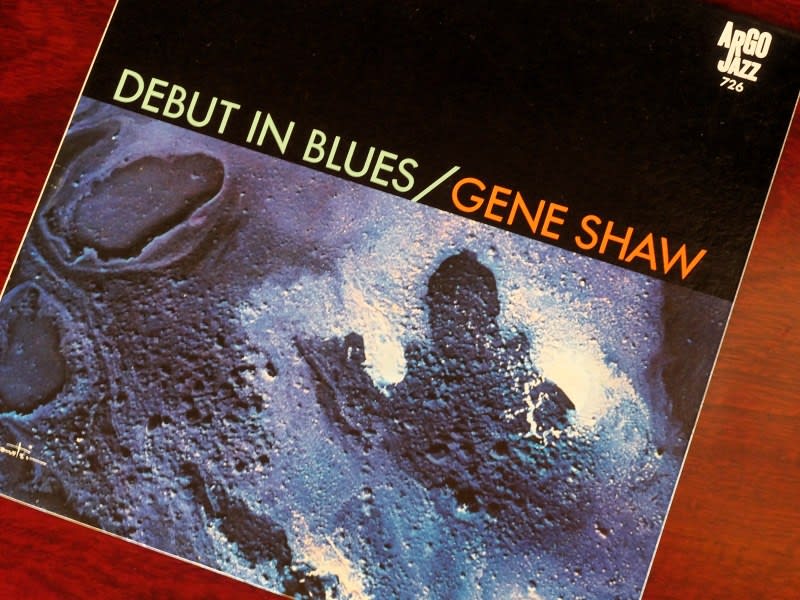右が初リーダー作”QUINTET/SAYING SOMETHING”(SAVOY 1961年録音)、左が1981年に録音された”POLITELY”(MUSE)。両作の間に20年の差があるが、リズム感に多少の違いは有れど一般的な聴き方では時代の差を感じない。フォー・ビートの流れが絶え間なく続いている訳だが、60年代後半から70年代にかけて多くのハード・バッパー達が生き場所を失ったのも事実。ただ、70年代後半から、ハード・バップ再興の機運が高まり、B・ハードマンも爛熟期にリーダー作がSAVOY1枚だったのに対し、80年前後にはMUSEに3枚も録音している。
ハードマンは50年代に、ブレイキーのJ・Mの一員になっているが、一時的、代打要員的な使われ方をされたのか、実力の割に評価、人気は上がらなかった。また、初リーダー作に聴く気も失せる阿保らしいカヴァが使われる不運に泣いた。けれど、TOPの”Capers”(tb奏者、T・マッキントッシュ作)は一度聴いたら、忘れられほどノスタルジックなメロディを歌心たっぷりにtpを鳴らすハードマン一世一代の名演です。他の曲も彼の実力を十二分に表している。
左の”POLITELY”のカヴァはSAVOY盤と対照的ですね。同世代のハード・バッパー達の多くが失墜していった中、キリッとした顔付きと身なりから推察すると、それなりに恵まれた環境下にいるのだろう。つまり、それだけ実力があった裏返しと言える。ただ、本アルバムも不幸の目に遭った。犯人は録音の名手、V・ゲルダー。ハードマンのtp、クックのtsが薄く、紙ぽく耳障りな音になっている。これでは本作の出来映えを云々する以前の問題です。録音とマスタリング(刻印有)を担当したゲルダーの「弘法にも筆の誤り」です。


なお、必殺の名曲、”Capers”はこの”THE CUP BEARERS / BLUE MITCHELL”(RIVERSIDE)にも収録されている。

この作品にはもう一曲、C・ウォルトン作の哀愁に満ちた名曲、”Turquoise”も収録されている。