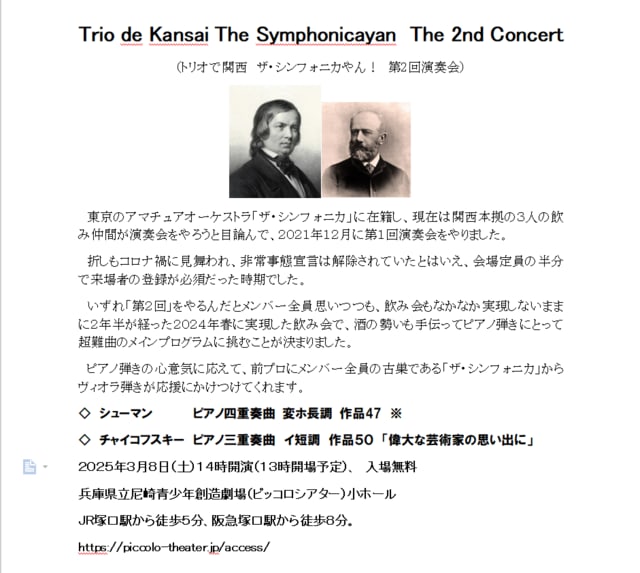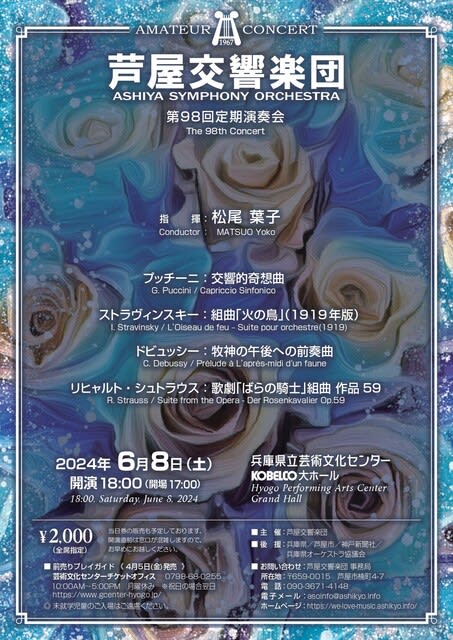オヤジの所属オケの次回の定期演奏会の練習が始まっています。
次の演奏会のメインはショスタコーヴィチの交響曲第10番です。
オヤジは小学生の時代にタコに出会って以来タコキチを自認していますが、所属するアマオケでタコを演奏する機会になかなか巡り合えませんでした。
初めて演奏したのが2003年に今の所属オケの2度目の在団時、第7番「レニングラード」でした。
その翌々年の2005年には第15番を弾きました。
2005年の秋から10数年単身赴任生活で、赴任先のオケに入れていただきました。
最初の赴任地札幌で2006年に「祝典序曲」と第5番を弾くことができました。
このように限られた期間で立て続けにタコを弾く機会に恵まれましたが、結局はそれきり。
今回は19年ぶりにようやくまたタコを弾くことが出来ます。
何時?が定かな記憶はありませんが、多分中学時代に初演者ムラヴィンスキー指揮のレニングラードフィルのモノラルLPを買って、その時に全音のスコアも買ってスコアを見ながら聴いていました。
LPもまだ実家にあるはずです。
スコアの裏表紙には700円と書いてあり、大分茶褐色に褪せて年季が入ってます。
今日の練習ではその年季に見合う遺産を微塵も感じませんでしたけど。。。
要するに聴くと弾くとは大違いですわ。(笑)



次の演奏会のメインはショスタコーヴィチの交響曲第10番です。
オヤジは小学生の時代にタコに出会って以来タコキチを自認していますが、所属するアマオケでタコを演奏する機会になかなか巡り合えませんでした。
初めて演奏したのが2003年に今の所属オケの2度目の在団時、第7番「レニングラード」でした。
その翌々年の2005年には第15番を弾きました。
2005年の秋から10数年単身赴任生活で、赴任先のオケに入れていただきました。
最初の赴任地札幌で2006年に「祝典序曲」と第5番を弾くことができました。
このように限られた期間で立て続けにタコを弾く機会に恵まれましたが、結局はそれきり。
今回は19年ぶりにようやくまたタコを弾くことが出来ます。
何時?が定かな記憶はありませんが、多分中学時代に初演者ムラヴィンスキー指揮のレニングラードフィルのモノラルLPを買って、その時に全音のスコアも買ってスコアを見ながら聴いていました。
LPもまだ実家にあるはずです。
スコアの裏表紙には700円と書いてあり、大分茶褐色に褪せて年季が入ってます。
今日の練習ではその年季に見合う遺産を微塵も感じませんでしたけど。。。
要するに聴くと弾くとは大違いですわ。(笑)