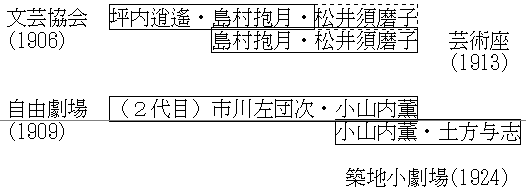1912(大正元)年12月 2個師団増設案否決により上原勇作陸相辞任。第2次西園寺内閣退陣し、第3次桂内閣成立。第1次護憲運動始まる。
退く日に際し 上奏し。
1912年 2個師団増設案 第2次西園寺内閣 上原勇作陸相 上奏
そのような最中の大正元年(1912年)12月、第2次西園寺公望内閣の陸軍大臣・上原勇作が陸軍の二個師団増設を提言する。
Amid this, in December 1912, Yusaku UEHARA, Minister of Army in the
second cabinet of Kinmochi SAIONJI proposed to increase two divisions of army.
第二次西園寺公望内閣のとき、緊縮財政による国家財政再建や行政整理を理由に、西園寺公望首相が、陸軍による「二個師団増設」の要求を拒否した(二個師団増設問題)。
During the second Kinmochi SAIONJI Cabinet, because of the national
financial reconstruction and the administration by reduced budget, Prime Minister Kinomochi SAIONJI refused the Army's 'two division
expansion' demand (two divisions' expansion issue).
しかし、上原勇作陸軍大臣が辞表を提出、陸軍は軍部大臣現役武官制を盾に後任陸相の推薦を拒否したため内閣は総辞職に追い込まれた(二個師団増設問題)。
However, the Cabinet was forced to resign en masse because Yusaku UEHARA, the Minister of Army, submitted his resignation and the
military refused to nominate an incoming Minister of Army by hiding
behind a rule that only an active military officer could serve as Army or
Navy Minister (the issue of building additional two divisions).
[point]
1.陸軍は「二個師団増設問題」(1912年)で、上原勇作陸相を辞任させ、第2次西園寺内閣を総辞職に追い込んだ。
[解説]
1.1911年10月に辛亥革命がおこり、朝鮮、満州への革命の波及をおそれた陸軍は、第2次西園寺公望内閣(同年8月成立)に対し、朝鮮常駐の2個師団増設を強く要求するにいたった。師団とは、他からの援軍がなしで、単独で戦争作戦が行える軍隊の単位。歩兵、砲兵、工兵等の戦闘兵員の他、武器弾薬食料を運ぶ兵員、戦車部隊や、若干の航空部隊も含む。平時は1万人前後、戦時は最大2万人規模にふくらむ。
2.しかし行財政整理を政策の中心にすえる西園寺内閣は、世論を後ろ盾に、要求を拒否した。このため陸軍は、上原勇作陸相を辞職(1912(大正元)年12月)させ、後任陸相を出さなかった。このため軍部大臣現役武官制に縛られた、西園寺内閣は総辞職に追い込まれた。
3.かわって長州閥と陸軍の長老である桂太郎が、就任したばかりの内大臣と侍従長を辞して第3次桂内閣を組織した。すると、藩閥勢力が新天皇を擁して政権独占をくわだてているという世論が高まり、大正政変・第1次護憲運動へと発展していった。
4.その後二個師団増設問題はくすぶり続けたが、第1次世界大戦勃発を背景に、第2次大隈重信内閣(1914年4月成立)が、1915年12月、ようやく2個増師を実現させた。
〈2017早大・法
① 4月11日
d元老会議大隈伯を首相に推薦すべしとのこと新聞に顕はる。大正の御代に伯一度政権を掌るべしとの余の想像は正に事実とならんか。
問8 下線dによって成立した内閣に関連する記述として誤っているものはどれか。1つ選べ。
あ ドイツに宣戦布告して第一次世界大戦に参戦した。
い 中国に対して21ヵ条要求の承認を求めた。
う 総選挙で立憲政友会に大勝した。
え 朝鮮への二個師団増設を実現した。
お 中国の政権に巨額の借款を与えた。」
(答:お× ※これは西原借款で寺内正毅内閣の失政)〉
〈2016立命館大・全学部
日露戦争の勝利によって、大陸進出を本格化した日本は、その終結後も軍事力の増強に力を注いでいった。1907年に[ A ]を制定し、平時の陸軍を25個師団へと増強する方針などを定めたのはその現れである。その後、陸軍は不況の到来のなかで緊縮財政を唱える第2次[ B ]内閣に対して2個師団増設を要求し、内閣を瓦解に追い込んだが、その強引なやり方は1世論の批判を引き起こすこととなった。
問a 空欄[ A ]にあてはまる、もっとも適当な語句を漢字6文字で答えよ。
問b 空欄[ A ]では、日露戦争後の日本の仮想敵国が定められている。このとき、仮想敵国の順序として、ロシアの次におかれた国はどこか。国名を答えよ。
問c 空欄[ B ]にあてはまる、もっとも適当な人名を答えよ。
問d 下線部1に関連して、世論の不満は第2次[ B ]内閣瓦解のあとに続いた内閣に対する批判運動として盛り上がりをみせた。その批判運動を何というか。もっとも適当なものを下から一つ選び、記号で答えよ。
あ 大同団結運動 い 第一次護憲運動
う 第二次護憲運動 え 国体明徴運動」
(答:a帝国国防方針、bアメリカ、c西園寺公望、dい)
1907年「帝国国防方針」なる。
行く罠帝国 星双子。
1907年 帝国国防方針 25個師団
1907年には山縣の主導によって平時25師団体制を確保するとした「帝国国防方針」案が纏められる。
In 1907, under the leadership of Yamagata, the "Imperial Defense Policy" proposal was prepared to
secure a 25 division formation during times of peace.
〈2016早大・文
「大正デモクラシー」の時代をみる上で、ひとつの大きな画期となったのが、第一次護憲運動である。1912年、要求していた2個師団増設が第二次西園寺内閣によって財政上の問題から拒絶されると、陸軍大臣の[ A ]が辞表を提出し、内閣は総辞職した。後継として組閣したのは内大臣兼侍従長だった桂太郎であるが、このことが宮中と政府との領分を乱すとの批判が起こり、立憲政友会の[ B ]、立憲国民党のa犬養毅をはじめとする野党、ジャーナリスト、商工業者や都市民衆を中心とする大規模な運動が、「憲政擁護・[ C ]をスローガンとして全国的に広がった。
問1 空欄Aにあてはまる人名を漢字で記述しなさい。
問2 空欄Bにあてはまる政治家で、「憲政の神様」と称された人物は誰か。1つ選べ。
ア 大隈重信 イ 原敬
ウ 尾崎行雄 エ 加藤友三郎
オ 斎藤隆夫
問3 下線aの人物(犬養毅)について、誤っている記述はどれか。1つ選べ。
ア 大隈重信らによって結成された立憲改進党に入党した。
イ 第一次大隈内閣の文部大臣在任中、共和演説事件によって辞職した。
ウ 田中義一の後継として、立憲政友会の総裁に就任した。
エ 組閣の際、大蔵大臣に高橋是清を起用して金輸出再禁止の実施に踏み切った。
オ 首相在任中に「五・一五事件」によって暗殺され、これによって戦前における政党内閣の時代は終焉をむかえた。」
(答:問1上原勇作、問2ウ、問3イ×※犬養毅ではなく尾崎行雄)〉
〈2016法大・文(哲史)営(営)人間
D e.桂首相は、優詔を拝して、辞する能(あた)はす、遂に内閣を組織せりと公言せり。然るに桂首相は当時内大臣兼侍従長の職に在り。右優詔は何人の奏請せしものなるや。
又桂首相内閣組織の大命を拝し、其の閣員を奏上するに際し、海軍大臣留任の優詔あり。是れ何人の奏請に係るものなりや。
桂首相内閣組織の大命を拝し、未(いま)た其の閣員を奏上せさるに先(さきだ)ち、其の氏名を公にし、甚しきは其の抱負を公言して憚(はばか)らさるものすら之(こ)れありしか如し。是れ果して妥当の行動と為(な)すものなりや。
問7 史料Dの下線部eにもっとも関係のうすいものを、以下のア~エのなかから一つ選べ。
ア 立憲同志会 イ 薩摩藩
ウ 大逆事件
エ 二個師団増設問題」
(答:イ× ※桂は長州軍閥)〉