次の文中の(a)~(e)については、【 】のなかに入る最も適当な語句を①~⑤より選び、その番号をマークしなさい。また、(1)~(5)の[ ]には、最も適当な語句を記入しなさい。
1700 年代に入り、幕藩体制の動揺が目立ちはじめたころ、諸藩でも農村の荒廃や財政窮乏に悩まされていた。
そこで諸藩は、倹約や統制を強め、財政難を克服して藩権力の強化を目指す藩政改革が広く行なわれた。
これらの藩では、農村の復興がはかられ、特産物(国産品)生産を奨励するとともに、専売制(専売仕法)が強化され、またそれぞれに藩校(藩学)を設立・再興し、藩士の子弟や、領民の教育に力を入れるようになった。
宝暦年間に、熊本藩主(a)【①細川政元 ②細川頼之 ③細川忠興 ④細川重賢 ⑤細川晴元】は、堀勝名(堀平太左衛門)ら有能の士を抜擢して要職に据え、職制整備、財政緊縮、農地の整備、治水など広汎な改革を断行した。
また、藩校(b)【①造士館 ②致道館 ③学習館 ④養賢堂 ⑤時習館】を設立し、藩士の子弟のみならず、庶民でも好学の者には門戸を開き、文武の奨励につとめ、他藩の模範となった。
ついで、1700 年代後半には、とくに東北諸藩に名君があらわれ、国産品を創出し、専売制を強化して財政難をきりぬけようとした。
なかでも、米沢藩主[ (1) ]は、明和年間からの改革で、農業および国産品の奨励、門閥勢力の排斥などに治績をあげ名君とうたわれた。
とくに養蚕・織物業を盛んにして家中工業としたが、その産物である米沢織は、同地の特産品となった。
さらに、衰退していた藩校に儒者細井平洲を招いて復興し、興譲館と名づけ、藩士や領民の文教政策にも力を注いだ。
また、寛政のころ、秋田藩主[ (2) ]も、疋田定常・大越範国らの補佐を得て天明の飢饅後の藩政改革につとめ、農・林・鉱業の奨励織物・製糸・醸造などを保護育成した。
また、1789(寛政元)年に藩校を創設し、江戸の儒者山本北山らを招いて文教政策の刷新をはかった。
この藩校は、1811(文化 8)年に、(c)【①明徳館 ②教授館 ③明倫館 ④弘道館 ⑤明倫堂】と改称され、その後も同藩の文教の中心となり、興隆していった。
また、松平定信も、白河藩主時代に農村復興や殖産興業、文武奨励などの藩政改革を行い、とくに天明年間の飢謹において、その迅速な対応により、領内から一人の餓死者も出さなかったといわれ、これらのことが、後に幕府の寛政の改革を遂行する下地ともなった。
1800 年代に入ると、後年明治維新の中心となった西南雄藩において、さまざまな改革が行われるようになった。
薩摩藩(鹿児島藩)では、家老調所広郷が、藩債 500 万両を 250 年という長期年賦返済で実質的に棚上げし、また、多くの国産品の開発・改良および合理化に努力して、藩財政を再建した。
とりわけ、奄美三島の[ (3) ]の専売制強化(惣買入制度)や、琉球との密貿易が、同藩に多大な利益をもたらした。
これらを財政的基盤として藩主(d)【①島津重豪 ②島津義久 ③島津家久 ④島津斉彬 ⑤島津久光】の代になると、反射炉や造船所、ガラス製造工場などの洋式工場群(集成館)がつくられ、洋式兵制(洋式軍備)の採用とあわせて、のちに明治維新を推進する力を貯えていった。
長州藩(萩藩)でも、天保年間に、藩主毛利敬親の信任を得た村田清風が、銀 8 万貫を超える藩借財の整理、紙・蠣などの専売制の促進、下関に設けた越荷方(他国からの積荷を抵当にした貸付業や、倉庫業)からの収益などによって財政再建をはたし、洋式兵制の採用とあいまって雄藩のひとつとなった。
しかし、1843(天保 14)年に藩士の借財整理をねらって発令した(e)【①27 ②37 ③47 ④57 ⑤67】か年賦皆済仕法は、事実上の負債棚上げであり、債主に不利なため、金融を停滞させたとして一方では反発された。
幕末期になると、福井藩(越前藩)では藩主松平慶永(松平春嶽)が、橋本左内や由利公正らの賢臣と、熊本藩の儒者であり政治思想家の[ (4) ]を登用し、重商主義的な富国強兵策による藩政改革を実施した。
また、宇和島藩でも藩主[ (5) ]が、長州藩より村田蔵六(大村益次郎)を招き、蒸気軍艦の建造をはじめとして洋式兵制を導入し、殖産興業、文武教育の振興などの藩政改革を行った。
この他に、水戸藩・肥前藩(佐賀藩)・土佐藩(高知藩)などでも藩政改革が行われ、それぞれに成功・不成功があったが、これらの諸藩における改革、とくに財政的基盤の強化と洋式兵制の充実などは、のちに明治維新を成就させる原動力ともなった。
[解答] a ④ b ⑤ c ① d ④ e ②
(1) 上杉治憲(鷹山) (2) 佐竹義和 (3) 黒砂糖 (4) 横井小楠 (5) 伊達宗城
[解説](1)鷹山(ようざん)は米沢藩(よねざわはん)。
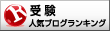
受験 ブログランキングへ
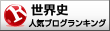
世界史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ






















 『後漢書』東夷伝には、107年にも倭国の帥升らが生口(奴隷)160人を後漢の安帝に献上したと記されている。
『後漢書』東夷伝には、107年にも倭国の帥升らが生口(奴隷)160人を後漢の安帝に献上したと記されている。









