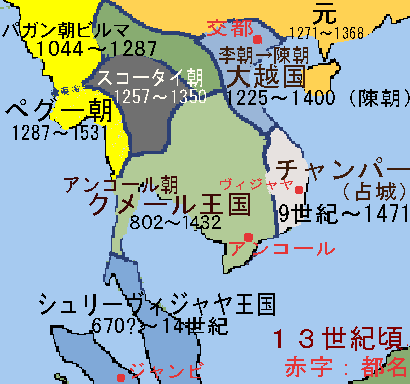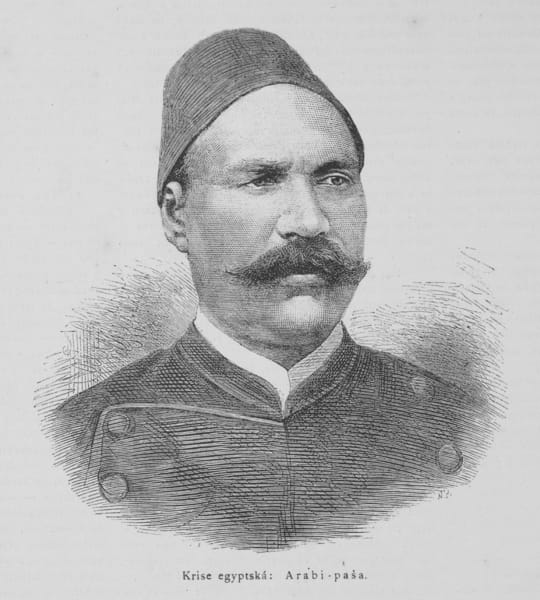次の文を読んで、下の問に答えなさい。
17 世紀末にカムチャッカ半島を征服したロシア人たちは、以後、狩猟、毛皮貢税(ヤサーク)の徴収や交易を目的に千島列島を南下し、しだいに蝦夷島本島に近づき、1779 年には、シベリアの企業家が派遣したシャバリン一行がアッケシ(厚岸)に来航して松前藩に通商を求めるにいたった。
松前藩がこうしたロシア人の動きを最初に知ったのは 1759 年のことであったが、同藩はこうしたロシア人の動向はもとより、ロシア人との交渉の事実も幕府に報告しなかった。
しかしその後、このことが外に漏れた。
このことにいち早く関心を傾け、その真相を究めようとしたのが仙台藩の藩医( 1 )であった。彼は長崎のオランダ語通詞や門人の松前藩医などから情報を入手し、1783 年( 2 )を著して蝦夷地の開発とロシアとの通商の必要を説き、同書を幕府に献じた。
当時幕府は財政難に苦しんでいただけに、時の老中( 3 )はこの意見に注目していち早く採用し、1785 年から翌年にかけて蝦夷地調査を実施したが、途中、失脚したため、蝦夷地開発計画は中止された。
しかしその後、ロシア船をはじめ、イギリス船やアメリカ船が日本近海に来航して、鎖国体制をおびやかしはじめた。1792 年ロシアの使節( 4 )が根室に来航し、幕府に大きな衝撃を与えた。
彼はロシアの女帝( 5 )二世が派遣した正式な使節であっただけでなく、伊勢国漂流民の神昌丸船頭( 6 )などの送還を名目に日本との通商を求める書簡を持参していたからである。
( 7 )を著してロシアの南下を強く警告した林子平が、処罰された直後のことであった。
1804 年には( 8 )が長崎に来て再び通商を求めたが、幕府はこれを拒否した。
その後ロシアの艦船が蝦夷地の近海に出没してしばしば紛争をおこした。ロシアの進出に関心を強めた幕府は、(a)1798 年幕吏を松前や蝦夷地(南千島と樺太を含む)に派遣して調査を行い、1799 年箱館周辺の和人地と東蝦夷地を幕領とし、次いで 1807 年松前氏を移封して、松前・蝦夷地全域を幕領とし、奥羽諸藩にその警備を命じた。
その後ナポレオン戦争の影響でロシアの極東への関心は弱まり、一時ロシア船の出没はみられなくなったが、それにかわってイギリス船が日本近海に出没するようになった。(b)1808 年イギリス軍艦が、当時交戦国であったオランダ商船を追って長崎に入港するという事件がおき、つづいて
イギリス船やアメリカ船がしばしば近海に姿をあらわすと、幕府は 1825 年に( 9 )令を出して鎖国
体制の維持に努めた。そのため 1837 年に、日本人漂流民を護送するとともに通商を求めて浦賀
に来航したアメリカの商船( 10 )号が撃退された。こののち(c)( 11 )が「慎機論」を、( 12 )が
「戊戌夢物語」を著して上記の法令の不当を論じたが、かえって処罰された。
問 1.上の文の(1)~(12)に適当な語句を( )の番号とむすんで書き出しなさい。
〔解答例:(③一カムチャッカ半島〕
問 2.下線部分(a)について、この調査の際、エトロフ島に渡り「大日本恵登呂府」の標柱をたてた人物は誰か。
問 3.下線部分(b)について、この事件を一般に何とよぶか。
問 4.下線部分(c)について、この一連の事件を一般に何とよぶか。
解答
問1
(1)一工藤平助 (2)一赤蝦夷風説考 (3)一田沼意次 (4)一ラックスマン (5)一エカチェリーナ (6)一大黒屋光太夫 (7)一海国兵談 (8)一レザノフ(9)一異国船打払〔無二念打払〕 (10)一モリソン (11)-渡辺崋山 (12)-高野長英
問2 近藤重蔵 問3 フェ-トン号事件 問4 蛮社の獄