漁師になるための学校、漁業学園。
こんにちは、園長の青木です。
ホームページはこちらです。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-940/
11月の見学会は漁師.jpでもお知らせしています。
www.ryoushi.jp
カツオの釣り込み練習と平行して、クロスロープの刺しつぎをやっています。
エイトロープ、クロスエイトとも呼ばれる8本のヒモを編み込んで作ったロープです。


例によって、ホワイトボードに生徒の名前と、覚える内容が書かれました。
できた日付を先生が記入していきます。
遅れている人が、一目で分かってしまうシステムです。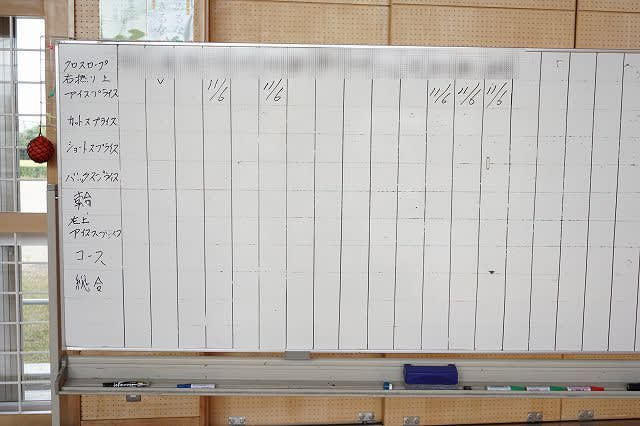
このロープの端末処理、あるいは連結する作業をやっていきます。
実習が2時限あると、1時限は釣り込み、1時限は刺し継ぎってところです。



毎年、生徒が苦労する実習です。
漁師でも、マスターしている人は少ないようです。
YouTubeにショートスプライス(つなぎ合わせ)の動画がありました。
難しさがわかると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=Kde9z-1A3nU&t=23s
みんながんばれ!
学園見学のお申し込み、入学のお問い合わせは電話、Eメールで。
電話 054-626-0219
Eメール gyogaku@pref.shizuoka.lg.jp
【ロープの種類】
多く見かけるのが3つのヒモをねじって作った「三つ打ちロープ」です。
そして最近多くなったのが「八打ち」のクロスロープ。単にエイトとも呼びます。
さらに「12打ち」や、タフレ、エースラインなど、もっと細いヒモを編み込んで作るロープもあります。
三つ打ちロープと、他のロープの違いはキンクという撚(よ)れ、捻(ねじ)れができないことです。
長所と引き替えに、加工するのは大変になります。
園長のつぶやき
学園の実習を見ると、漁師の仕事は魚を捕るだけではないことが良く分かります。
特にクロスロープの加工は難しい作業です。
あきらめるな、あきるな!
で覚えなくてはなりません。
ですけど、苦労はムダになりません。
学園の卒業生は、学園で学んだ中で、実習のことを高く評価しています。
もちろん、漁師で一番大事なのは魚をとることです。
ただし、それは簡単に身につく技術ではありません。
新人の漁師にとって、ロープワークのような作業を素早く、きれいにできるが大変重要です。
この技術で他の仕事をする上でも気持ちの余裕が生まれるし、
先輩の漁師からも評価され、漁師の仲間として認められていきます。















































