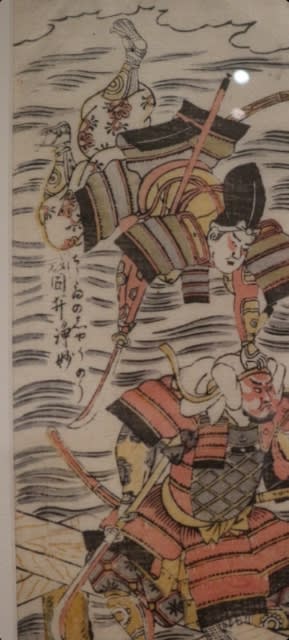●ゴンタ太鼓
どこの神社にもゴンタダイコやゴンタヤッサともいうべき、気象の荒い人が集まる屋台というのがあります。きっと読者の皆様のなかでも、あの神社やったらあっこ、この神社やったらここ、というのを思い浮かべている方もいらっしゃるでしょう。
三木市大宮八幡宮では、ゴンタといえば語弊がありますが、迫力のある屋台といえば、播州最大級の下町屋台を思い浮かべる方が多いでしょう。あの大きな屋台をかつぐのは、よっぽどの気概がないとつとまらないようにおもいます。

しかし、この記事では、昔のゴンタ太鼓は新町だったことが書かれていることに触れました。これは、明治四年(1871)のことです。しかし、喧嘩がもっとも強い屋台はべつにあったとのことです。
●昭和二十五年(1950)座談会「明治初年の三木町」*より
上記座談会の記録によると、明治四年(1971)ごろに生まれたとおもわれるM氏が、興味深い発言をしています。
「喧嘩をよくした。屋根の瓦をめくって放つたりした。」
めちゃくちゃですね😅
まあ、今でも毎年のように喧嘩はありますが、瓦を放るなんてことは、なかなかありません。M氏がものごころついたころと考えると、明治十四年ごろの話でしょうか。そして、M氏は続けます。
●喧嘩最強は、、、

「一番強かったのは上町でした。」
まさかの上町でした。
今となっては、家の件数がおそらくもっとも少なく屋台の保持を断念した上町です。その状況は明治時代でも同様とおもわれます。人数が少ないはずの上町が強かったのは一人一人がスーパーサイヤ人のようにが喧嘩がつよかったということでしょうか。さらにM氏は続けます。
「上町は旦那衆で太鼓かきの人を雇つたから、そいつが強かつた」
江戸時代の檀鶴が出ていた文政時代ころまでは、上町の庄屋さんのご子息は、当番の年は檀鶴で能を奉納していたようです。その他のもろもろの「担い物」をするのは雇われ人とのことで、主役が屋台になってからも、人を雇う祭はしばらく続いていたようです。
*編輯・青甲社編集同人『青甲 八、九、十月号』(青甲社、1950)所収
*編輯・青甲社編集同人『青甲 八、九、十月号』(青甲社、1950)所収