この旅の一番の目的は、応挙の「大乗寺障壁画」に再会すること。
実は13年前、2003年夏に天王寺公園内にある大阪市立美術館で
開催された特別展『円山応挙、写生画 創造への挑戦』で、
実寸大の間取りで障壁画が飾られ、その素晴らしさに感動し、
大乗寺にて拝見できたらと思いながら、日が過ぎました。
数年後には全て収蔵庫に納められてしまい、金箔の上に
デジタル化された再現障壁画と聞き、忘れておりました。
大乗寺へは山陰線香住駅から山側へ車で5分
30段程度の急な石段の上に山門が
細かな細工が施され、左右には象でしょうか?



裏側の山門で、右手に創建同時期の樹齢1200年の楠と
旧の鐘があり、戦中鉄砲の弾の材料として供出され戻ったが、
材質検査で一部欠け、音が良くないため置かれています。
客殿の前には、丸山応挙さんの木造が置かれており
客殿にも素晴らしい細工が見られます。


拝観する入り口は土間になっており、大きなへっついさんが

13部屋ある客殿の配置図で、全て国の重要文化財に指定された
応挙とその門弟12人による165面の障壁画があります。
HP(詳細はデジタルミュージアム参照)によりますと、
”障壁画で囲まれる各部屋の空間が立体曼荼羅を構成しており、
宗教的空間の具現化を意図したものではないかといわれ、
応挙は絵画の美術的評価に加えて空間プロデューサーとして
の側面が再評価されています。”とのこと

内拝料800円を支払うと、20分程度かかる説明付きの案内を
していただけ、最初に『農耕の間』(呉春)を鑑賞しながら
 四季耕作図
四季耕作図
注意事項そして、応挙の意図した立体曼荼羅の説明へと続き
仏間におられる御本尊十一面観世音菩薩様の慈悲が水の流れと

して描かれており、最終的には
二階の芦雪の『猿の間』の海と同じ位置に
 猿の間
猿の間
農耕の間の欄間の波が彫られており、
仏間へと戻る意図の基づく立体曼荼羅の構成だそうです。
欄間に下には本寺の亀居山の亀さんが泳いでおり、フフフ
客殿を右周りに巡ります。
『孔雀の間』は応挙の『松に孔雀図』が三面(北‣東‣南)に、
金箔の上に墨だけで濃淡がでており、
西側の障子を開けると光線の具合で緑色にも見えます。
複製画で金箔が新しいので、やや煌びやかでした。
 北面
北面

 東面
東面
東面の拡大

奥に御本尊の仏間があり襖を開けられ、ご挨拶を、
ふと襖の松を見ると、連続性が保たれており声が出ません。
応挙の『郭子儀の間』いわゆる「芭蕉の間」には
彩り豊かで、のびやかな筆遣いが印象的で、
安禄山の乱を鎮めたことで名を上げた郭子儀を描き、
本尊の南を守る増長天(政治を司る)とされています。
西面は複製図

東面は文化庁の指導で、現物の四枚の障壁画が展示され、
やはり、落ち着いた色になり、見られて嬉しいです。
郭子儀の眼と、幼児のお尻を見なが移動すると、
いつも見られる印象や、お尻の方向が変わる
『八方にらみ」にも挑戦しました。

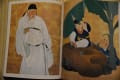

応挙の『山水の間』や『鯉の間』も


まだまだ紹介したいのですが・・・・
城崎温泉や湯村温泉のお寄りの際、時間をお取りください。
尚一部写真は、図録『円山応挙、写生画 創造への挑戦』から。
 表裏
表裏  表のみ
表のみ
実は13年前、2003年夏に天王寺公園内にある大阪市立美術館で
開催された特別展『円山応挙、写生画 創造への挑戦』で、
実寸大の間取りで障壁画が飾られ、その素晴らしさに感動し、
大乗寺にて拝見できたらと思いながら、日が過ぎました。
数年後には全て収蔵庫に納められてしまい、金箔の上に
デジタル化された再現障壁画と聞き、忘れておりました。
大乗寺へは山陰線香住駅から山側へ車で5分
30段程度の急な石段の上に山門が
細かな細工が施され、左右には象でしょうか?



裏側の山門で、右手に創建同時期の樹齢1200年の楠と
旧の鐘があり、戦中鉄砲の弾の材料として供出され戻ったが、
材質検査で一部欠け、音が良くないため置かれています。
客殿の前には、丸山応挙さんの木造が置かれており
客殿にも素晴らしい細工が見られます。


拝観する入り口は土間になっており、大きなへっついさんが

13部屋ある客殿の配置図で、全て国の重要文化財に指定された
応挙とその門弟12人による165面の障壁画があります。
HP(詳細はデジタルミュージアム参照)によりますと、
”障壁画で囲まれる各部屋の空間が立体曼荼羅を構成しており、
宗教的空間の具現化を意図したものではないかといわれ、
応挙は絵画の美術的評価に加えて空間プロデューサーとして
の側面が再評価されています。”とのこと

内拝料800円を支払うと、20分程度かかる説明付きの案内を
していただけ、最初に『農耕の間』(呉春)を鑑賞しながら
 四季耕作図
四季耕作図注意事項そして、応挙の意図した立体曼荼羅の説明へと続き
仏間におられる御本尊十一面観世音菩薩様の慈悲が水の流れと

して描かれており、最終的には
二階の芦雪の『猿の間』の海と同じ位置に
 猿の間
猿の間農耕の間の欄間の波が彫られており、
仏間へと戻る意図の基づく立体曼荼羅の構成だそうです。
欄間に下には本寺の亀居山の亀さんが泳いでおり、フフフ
客殿を右周りに巡ります。
『孔雀の間』は応挙の『松に孔雀図』が三面(北‣東‣南)に、
金箔の上に墨だけで濃淡がでており、
西側の障子を開けると光線の具合で緑色にも見えます。
複製画で金箔が新しいので、やや煌びやかでした。
 北面
北面
 東面
東面東面の拡大

奥に御本尊の仏間があり襖を開けられ、ご挨拶を、
ふと襖の松を見ると、連続性が保たれており声が出ません。
応挙の『郭子儀の間』いわゆる「芭蕉の間」には
彩り豊かで、のびやかな筆遣いが印象的で、
安禄山の乱を鎮めたことで名を上げた郭子儀を描き、
本尊の南を守る増長天(政治を司る)とされています。
西面は複製図

東面は文化庁の指導で、現物の四枚の障壁画が展示され、
やはり、落ち着いた色になり、見られて嬉しいです。
郭子儀の眼と、幼児のお尻を見なが移動すると、
いつも見られる印象や、お尻の方向が変わる
『八方にらみ」にも挑戦しました。

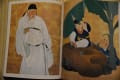

応挙の『山水の間』や『鯉の間』も


まだまだ紹介したいのですが・・・・
城崎温泉や湯村温泉のお寄りの際、時間をお取りください。
尚一部写真は、図録『円山応挙、写生画 創造への挑戦』から。
 表裏
表裏  表のみ
表のみ











