
今日は京都河原町六条下ルにある「ひと・まち交流センター」
で桂川流域ネットワークの会議に参加してきました。
8月に開催される「日吉ダム・天若湖アートプロジェクト」
の実施計画についてミーティングです。
私達が担当する「桂川水運・筏の記憶をたどる」計画も
いよいよ、具体的に動き出しそうです。
桂川の筏は奈良時代より流され、保津川の水運事業の原点に
この筏流しがあります。
その昔、桓武天皇の命により、長岡京遷都(787)と
その6年後の794年の平安京遷都が行なわれ、その都
造営という大事業の為、保津川の上流・日吉や京北から
筏を流したことに始まります。
その後、室町文化華やかなる都を造営し、戦国時代になると
伏見城や大坂城の建築用材として筏が組まれ、保津川を
流れていったのです。
日吉町はこの筏水運が盛んな地域で、同町の歴史を語る上で
筏は外す事のできない存在なのです。
その筏を当時の組み立て手順で、より正確に当時の姿を再現し
遠い昔の筏流しの記憶をたどろう!いう試みがが今回の企画です。

桂川ネットの先生方や京都造形大学や摂南大学の学生さんと
力を合わせ、歴史的にも価値の高い企画にしたと思っています。
で桂川流域ネットワークの会議に参加してきました。
8月に開催される「日吉ダム・天若湖アートプロジェクト」
の実施計画についてミーティングです。
私達が担当する「桂川水運・筏の記憶をたどる」計画も
いよいよ、具体的に動き出しそうです。
桂川の筏は奈良時代より流され、保津川の水運事業の原点に
この筏流しがあります。
その昔、桓武天皇の命により、長岡京遷都(787)と
その6年後の794年の平安京遷都が行なわれ、その都
造営という大事業の為、保津川の上流・日吉や京北から
筏を流したことに始まります。
その後、室町文化華やかなる都を造営し、戦国時代になると
伏見城や大坂城の建築用材として筏が組まれ、保津川を
流れていったのです。
日吉町はこの筏水運が盛んな地域で、同町の歴史を語る上で
筏は外す事のできない存在なのです。
その筏を当時の組み立て手順で、より正確に当時の姿を再現し
遠い昔の筏流しの記憶をたどろう!いう試みがが今回の企画です。

桂川ネットの先生方や京都造形大学や摂南大学の学生さんと
力を合わせ、歴史的にも価値の高い企画にしたと思っています。















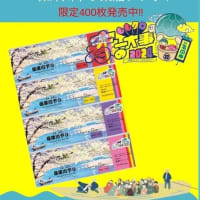

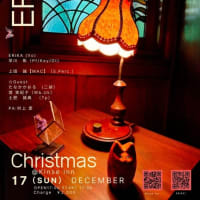



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます