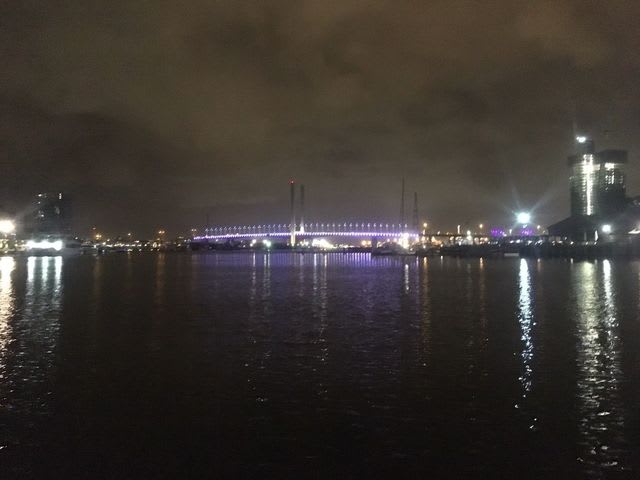2017年2月7日(火)
今日は「北方領土の日」なんだそうだ。日露和親条約、手許の年表には「安政元年12月21日」とあるのが、西暦では「1854年2月7日」というわけである。この時、下田・函館・長崎の開港とあわせて、択捉・得撫両島間を(千島列島方面での)国境とし、樺太は両国雑居地とすることを取り決めた。これが「択捉までは日本固有の領土」という当方の主張の根拠になっている。
僕は領土拡張主義者ではないし、国境を固定・強化して壁を作るよりも、国境越しの人や物の交流を平和裏に促進することによって国境を相対化することのほうが、理念的にも現実的にもはるかに上等だと信じている。ただ、国境について論じようというなら、日本政府もウヨクの面々もずいぶん遠慮するものだといつも不思議に思う。
というのは、日露和親条約の続編ともいうべき千島・樺太交換条約(樺太・千島交換条約、サンクトペテルブルク条約)というものが存在するからで。これは明治8(1975)年5月7日に締結され、日本は樺太での権益を放棄する代わりに、得撫以北の千島18島を領土とすることを取り決めた。この時期、日本はまだ不平等条約下の半植民地状態にあったこと言うまでもない。政治的にも軍事的にも圧倒的な優位に立っていたのがロシアで、それを背景として政治的にも経済的にもはるかに価値の高い(とロシアが判断した)樺太を取ったことがはっきりしている。せめてもの引き替えに日本は千島列島を得た。1945年の敗戦の結果として日本に求められたケジメが「明治以降の軍事活動によって他国から切り取った領土の返還」ということであったのなら、千島全域はそれに該当しないこと明白である・・・と主張しないのかしら。
ことのついでにおさらいするのだが、ポツダム宣言(1945年7月26日)の発信者は「合衆国大統領、中華民国政府主席、英国総理大臣」つまり米・中・英であってソ連は入っていない。同宣言は「日本国の主権は本州、北海道、九州および四国ならびに我々の決定する諸小島に限られねばならない」としているから、千島の帰属はこれら三国の「決定」に委ねられる理屈だろうが、ソ連はいわばポツダム宣言に便乗しながら、それに拘束されないものとして独自に行動した。スターリン自身は北海道侵攻にかなり乗り気だったのを、モロトフやジューコフに止められた経緯を以前どこかに書きとめた記憶がある。
ヤルタ会談は1945年2月4~11日である。既に消耗しきっていたF.ルーズペルトがスターリンの意のままに譲歩を重ねるのを、チャーチルがブルドッグのように切歯扼腕しつつ傍観した経緯が、今日ではよく知られている。ルーズベルトはスターリンにたいそうな置き土産を遺して4月12日に他界した(1882-1945)。後はスターリンのやりたい放題で、こう見ると1944年あたりからのFDRはおよそろくなことをしていない。仮に僕がアメリカ人だとして、アメリカの国益という観点から見て「ろくなことをしていない」という意味である。ついでながら第31代大統領だったフーヴァーは、「そもそも日本との戦争の全てが、何が何でも戦争に突入したいという狂人(ママ、もちろんFDRのこと)の欲望だった」と書いているらしい。古き良き共和党精神にとっては、まことに狂気と映ったことだろう。
何しろソ連はヤルタ・ポツダム体制で大いに利得を占めながら、微妙にその主流から外れた位置をとり続けた。実にしたたかなもので、この結果日ソ平和条約は戦後70年以上を経て依然未締結、ポツダム宣言の趣旨に沿って領土問題で抗弁しようにも「あれにはウチは加わっていない」ということになりかねない。交渉の制度的な土台がないところで実力を背景にした強談判に終始すること、日露和親条約の時代と大差ないということになるのかな。誰が担当しても難題に違いない。
朝のお勉強でした。

ヤルタ会談の有名な写真、Wikiよりコピペ。FDRの憔悴ぶりとスターリンの満足げな無表情に注目。
Ω