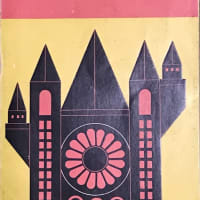2024年6月16日(日)
> 1962年6月16日、アメリカの海洋生物学者レイチェル・カーソンは『沈黙の春』という題名で「ニューヨーカー」紙上に連載を始めた。『沈黙の春』は、「湖水のスゲは枯れはて、鳥は歌わぬ」と言うキーツの詩の引用から始まる。当時アメリカで日常的に行われていた農薬の大量散布が環境に及ぼす影響を論じた警告の書であった。連載終了後、9月27日に単行本として出版されたが、刊行当日に四万部が売れたという。
連載が始まると賛否両論が巻き起こった。中でも農薬を製造する薬品会社からは強い反発があり、出版妨害もあった。しかし、この問題について初めて知る機会を得た大衆は、彼女を支持した。マスコミもこぞってこの問題を取り上げ、ついには当時の大統領ケネディが直属の科学諮問委員会を設けて調査し、『沈黙の春』の内容がデータとして誤りのない事実であることを確認したのである。
この本の刊行の二年後、カーソンは癌によって56歳で死去した。今日地球規模で環境汚染は問題となり、さまざまな運動が行われている。われわれの地球を守るという行動の、その最初の扉を大きく動かしたのは、『沈黙の春』という一冊の本であった。
晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店)P.173
1972年の春、高校に入って最初の生物の授業の際に教科担任の岡村先生が一冊の本を推薦してくださった。『生と死の妙薬』という邦題で、これが『沈黙の春』の訳本だった。


50名弱の同級生の中で、すぐに読んだのはたぶん一人だけ。ときどき話に出てくるRという友人で、生態学や人類学など地球規模でものを言いたがり、一方では無類の昆虫好きという彼の性癖にぴったり合致したのだろう。僕は購入したものの長らく読まずに放ってあった。『沈黙の春』がどうして『生と死の妙薬』に化けるか、そのことの方が気になっていたかもしれない。僕らが高校を出る頃には改題されて文庫入りし、以来『沈黙の春』で通っている。
レイチェル・カーソン(Rachel Louise Carson、1907年5月27日 - 1964年4月14日)には信奉者が多いが、尤もなことである。レイチェル・カーソン日本協会というものがあり、『沈黙の春』とあわせて『センス・オブ・ワンダー』を高く評価していることが窺われる。茅ヶ崎教会の田村博先生も同協会の会員で、カーソンにたびたび言及なさっている。
レイチェル・カーソンは生涯を独身で過ごし、1953年以降は作家のドロシー・フリーマンと深い友情を結んだ。『沈黙の春』執筆中から乳癌を患い、同書刊行の二年後に他界したのは上掲書の通り。遺言によって火葬に付されたのもアメリカでは珍しい。
今年は没後60年にあたり、古書のサイトでも彼女にちなんで環境問題の特集が組まれたりしている。
そういえば今朝の朝刊一面見出しは、原発の「増設」を認めるという経産省の方針を報じていた。列島全体が常に地震の危険に曝されているという国土の基本条件があり、実際に2011年のあのことがありながら、なお原発に執着できる精神構造は不思議という他ない。カーソンの警告とはやや別の方向から、沈黙の春の危険がわれわれを脅かしている。すぐそこに存在するさし迫った危険である。
写真:https://ja.wikipedia.org/wiki/レイチェル・カーソン
Ω