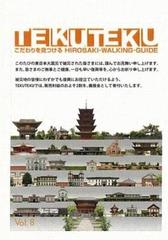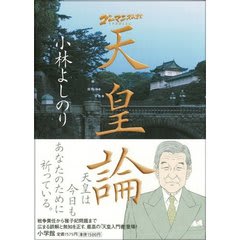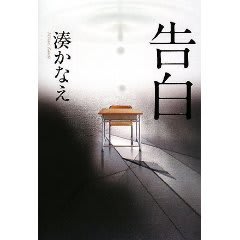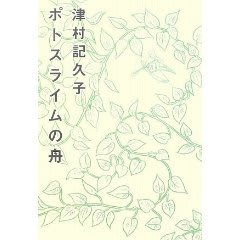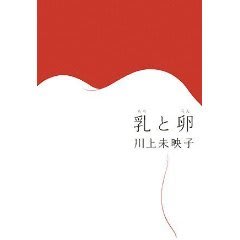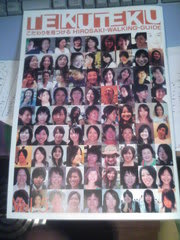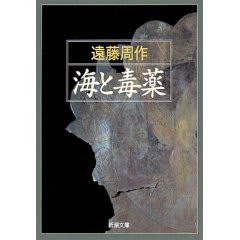小林よしのり編集長の「わしズム」が復活しました。
前号の「前夜」がコンセプト不足で失敗したのか、わしズムとして復刊。
女優が表紙だと何の雑誌かよくわかんらんから売れなかったようですね・・・。
内容はわしズム踏襲で、でも前夜の女性作家ものがやや多め。
特集「女性宮家創設の真相はこれだ!」
まずゴー宣二本立て。
そして小林よしのりと久能靖と友納尚子の対談。
田中卓、高森明勅の評論。
以上これだけ読めば、女性宮家の必要性、皇室典範の改正、男系固持の不可能さがわかる。
続いての特集「AKB48で日本が変わっていく!」
まさかのAKB特集で、よしりんと秋元康の貴重な対談あり。
ゴー宣もAKBについて。
その他AKB評論が7本くらいとアイドル誌並だ。
ま~、普通の言論誌でないところがわしズムのいいところである。
自分はAKBはさほど興味ないが、推しメンは柏木由紀!
あの清楚さと長身と丸い鼻と巨乳が魅力的。
さらにはゴー宣外伝「女について」の第二弾も、よしりんの女遊びについて赤裸々に描いてる。
あそこまで行くと笑える。よしりんはかなり器小さいしね~。
「10万年の神様」は面白くないです。
多分人気無くなったらやめるだろうが。
その他、今回も照沼ファリーザ(晶エリー)のヌードもある!
辛酸なめ子の漫画も好きだな。
そんなわけで、復活したわしズムは前号よりは面白くなりました。
次号も乞うご期待!
前号の「前夜」がコンセプト不足で失敗したのか、わしズムとして復刊。
女優が表紙だと何の雑誌かよくわかんらんから売れなかったようですね・・・。
内容はわしズム踏襲で、でも前夜の女性作家ものがやや多め。
特集「女性宮家創設の真相はこれだ!」
まずゴー宣二本立て。
そして小林よしのりと久能靖と友納尚子の対談。
田中卓、高森明勅の評論。
以上これだけ読めば、女性宮家の必要性、皇室典範の改正、男系固持の不可能さがわかる。
続いての特集「AKB48で日本が変わっていく!」
まさかのAKB特集で、よしりんと秋元康の貴重な対談あり。
ゴー宣もAKBについて。
その他AKB評論が7本くらいとアイドル誌並だ。
ま~、普通の言論誌でないところがわしズムのいいところである。
自分はAKBはさほど興味ないが、推しメンは柏木由紀!
あの清楚さと長身と丸い鼻と巨乳が魅力的。
さらにはゴー宣外伝「女について」の第二弾も、よしりんの女遊びについて赤裸々に描いてる。
あそこまで行くと笑える。よしりんはかなり器小さいしね~。
「10万年の神様」は面白くないです。
多分人気無くなったらやめるだろうが。
その他、今回も照沼ファリーザ(晶エリー)のヌードもある!
辛酸なめ子の漫画も好きだな。
そんなわけで、復活したわしズムは前号よりは面白くなりました。
次号も乞うご期待!