『流燈記』を読んで三浦哲郎が私の兄と同年齢だと知りました。6歳上の兄の少年期のことはまったく知りませんでした。
司さんの扉絵から各章のはじめを綴ってみます。
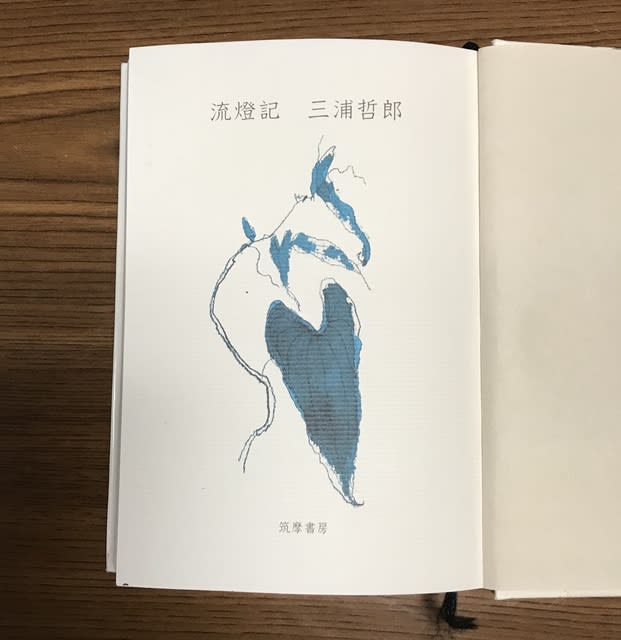
p005 序章/泉の水を飲もうとして、由良耕三は、ふと躊躇った。まさか、この水、軀に毒ではあるまいな。
山の窪地の、低い崖下で見付けた円い鏡のような泉である。それがただの水溜まりでないことは、水面に落ちた病葉が残らず岸の一角に吸い寄せられているのを見ればわかる。湧き出た水が、そこからすこしずつ溢れているのだ。溢れた水は、青草を濡らしながら崖裾をめぐって、窪地の外へ流れ出ている。
【この章の終わり近くには、戦争が終わって40年くらい経った時点の東北の山の中でトーチカ跡を見る主人公の思いが書かれています。(まさか今時、こんなものにお目にかかることになるとは思わなかったな)】
p024 一章/満里亜という女の目は、どうして暗いところでもあんなに明るんで見えるのだろう。
生まれ育った村を出て、矢ノ浦で暮らすようになった耕三が初めて他人に抱いた疑問というそれであった。
たとえば防空壕のなかにいても、耕三には満里亜の目だけがうっすらと明るんで見える。町内の人たちが古材を持ち寄って米問屋の裏庭に作った防空壕だから、もともと照明の設備などなくて、入口の扉を閉めてしまうと真っ暗になるが、その闇に目が馴れてくると、満里亜がどこにいるかが耕三にはわかる。離れていても、両目がすこし黄色っぽく明るんで見えるから、ああ、満里亜はあそこにいるのだとわかる。
p037 二章/満里亜という名の奇矯な女学生の正体は、それから半時間もしないうちに、あの猫のように黄金色のほのかな光を宿している目の謎を除いて、 大体わかった。
母親より先に学校から帰ってきた安吉によると、満里亜は、おなじ町内にある桔梗屋という下駄屋の孫娘で、毎年、夏と冬には独りで桔梗屋にきて休暇を過ごすのがならわしだから、ずっと以前から顔馴染みなのだということであった。
p54 三章/実際、夏の休暇に入ると、その第一日目の昼前に、表二階の住人たちは未練げもなく纏めた荷物を手に提げてさっさと帰省していった。
下宿を出るとき、普段は無口で無愛想な桑田が、上り框に腰を下ろして編上靴の紐を結びながら、送って一緒に階下へ降りた耕三に珍しく声をかけた。
「なあ、由良よ。貴様、休み中にいちど浜へ遊びにこいや。」
予科練志望の桑田は、誰に教わったのか、もうすっかり海軍軍人の言葉遣いになっていた。「俺たちの村は隣同士だからな、俺んとこでもいいし、北上んとこでもいいから、いちど遊びにこいや。魚も貝も腹一杯食わしてやる。貴様は泳げるか?」
p77 四章/新学期がはじまって間もなく、ちょっとしたことがきっかけになって耕三にひとり親しい友達ができた。港のむこうの漁師町から汽車通学をしている、真柄千松という名の級友である。
ある日、国語の時間に、教師が夏休みの宿題の作文について講評し、提出された五十篇ばかりのうちから特に優れたものとして二篇を選んで、みんなに朗読して聴かせたが、その二篇というのが、真柄千松と耕三の書いたものであった。耕三は、そんなことになるとは予想もしていなかったので、びっくりした。
p087 五章/その次の週の日曜日の午前、耕三は、漁師町にある真柄の家を訪ねるために、市の駅から海岸行きの気動車に乗った。真柄に、浜へ遊びにこないかと誘われたとき、すぐその気になったのは、正直いえば前々から満里亜が住んでいる港町をいちど歩いてみたいと思っていたから彼は、帰りに独りで港町に途中下車するのを楽しみにして出かけていった。
河口港の鉄橋を渡るとき、両岸にひしめいている家並のなかから酒場<いさり火>の看板を探し出そうとしたが、見つからなかった。こんなに容易に港町を訪ねる機会に恵まれるのだったら、それとなく満里亜に所番地を聞いておくのだったと耕三は後悔した。
満里亜が毎日乗り降りしている港の駅に停車すると、憲兵の腕章をつけた兵隊が一人、改札口に立ってそこを通る人々を見守っているのが、窓から見えた。それが、いつかの梶田とかいう憲兵かどうかはわからなかったが、満里亜の憂鬱が察せられ、こんなところにいないで桔梗屋にきて暮らせばいいのにと彼は思った。
p108 六章/秋も深まったある日、耕三が学校から帰ってみると、郷里の母からなにやら嵩張った小包が届いていた。嵩張っているわりには軽いので、彼はなんとなくがっかりしたが。部屋へ持って開けてみると、綿入れの半纏と干餅が出てきた。干餅は歌留多子はどの大ささのが七枚、新聞紙にくるんで、砕けないように半纏のなかに包み込んであった。それと一緒に、鉛筆書きの母の手紙も入っていた。
p150 七章/十日間の春休みを終えて、村の家から戻ってきた晩、耕三は、翁屋のおばさんから留守中に起こった意外な出来事を知らされた。
満里亜が家出をしたというのである。
「大きな声じゃいえないんだけどね」と、裏二階の部屋へきておばさんはいった。「おとといの朝、友達の家にいくといって出かけたきり、帰ってこないんだって。桔梗屋の伯母さん、夜遅くこっそり訪ねてきたわ、心当りがないかって、どう? あなたを当てにしてたようだけど。」
耕三は二重に驚かされた。
「どうして僕を?」
「男の友達はあなた一人だからって。」
さいわい、耕三の視野には人影が見当らなかった。宿の客も満里亜ひとりだったと見えて、どの窓にも人の顔らしいものはない。さっき宿の女の人が、土間でズック靴を履いている満里亜に、これで今夜からまた淋しくなるという意味のことをいっていたのを、彼は確かめるようおもいだした。
「ひとりで泊り込んでても、宿の人に怪しまれなかったみたいだね。」
p200 九章/その日、満里亜が港の母の家ではなく、町の桔梗屋へ帰ったのは確かだが、その帰宅の模様ーー満里亜がどんな顔をして家の敷居を跨ぎ、それを桔梗屋の家族がどんなふうに迎えたかは、耕三は知らない。
二人は、谷間を出たところで、あとで駅で落ち合うことにして別れた。満里亜はそのまま村を通り抜けて駅へ向い、耕三は一旦生家に戻って、残飯で握り飯を拵えて貰った。一応食堂と呼ばれる家に下宿しているからといって、いつも充分に食べさせて貰っているわけではない。育ちざかりには三度の食事も不足がちで、おやつにありつくことなどほとんどないから、下宿生は常に空腹を抱えているといっていい。だから、耕三は、生家から町へ戻るときは忘れずに握り飯を余分に持ち帰るのである。
「今日は四つでいいよ。なるべく大きく握ってよ。」
p222 十章/夏休みの前日、北上たち四年生の一隊は夜行列車で川崎の軍需工場へ旅立っていった。耕三は翁屋のおばさんと一緒に駅まで見送りにいったが、壮行会は昼のうちに学校で済ませていたので、見送りは生徒よりも家族の人たちの方が多かった。四年生たちは戦闘帽の上から日の丸の鉢巻を締めて車窓にひしめき合い、それをホームから見上げる人々は目をうるませて、なかには打ち振るつもりのハンカチで顔を覆う婦人たちもいた。その光景は出征兵士の見送りとなんら変るところがなかった。
北上が窓から片手を差し伸べるので、耕三とおばさんとはかわるがわるそれを握った、こうして車窓から男同士で手を握り合うのは初めてで、耕三は、これでもう北上とは会えないのだという気がした。胸に熱いものが込み上げてきた。
「あとはしっかり頼んだぞ。」
と北上がいった。耕三は、
「先輩も軀に気をつけて……。」
としかいえなかった。北上は顔を力ませて笑った。
「軀なんかどうなったっていいんだ。それより貴様、海兵へいくつもりなら一日も勉強を怠るな。」
「はい……でも、間に合うでしょうか。」
「……どういう意味だ。」
満里亜は、無言で右手を胸の前に持っていった。首の白さが、すこしずつ胸の方へひろがるので、ゆっくりシャツのボタンを外しているのだとわかった。
「あんたとはもう会えないかもしれないから……。」と、満里亜はなおも素肌の白さを押しひろげながら、すこし嗄れた声でいった。「あたしを好きなようにして。あんたにしてあげられるのは、それしかないから。」
耕三は、息を詰めて満里亜の仄白い胸と向い合っていた。胸の鼓動の高まりで、軀が風に吹かれる若木のように揺れそうだった。「遠慮しないで。」と囁くように満里亜はいった。「でないと、空の上で後悔するわ。」
耕三は、やっとの思いで両手をズボンのポケットにねじ込んだ。それから膝に力を入れて、鉄のように重たくなった下駄を地面から持ち上げた。「さあ、いこう。遅くなるよ。」
歩き出すと、なんともいえない淋しさが胸を満たしてきた。なにが淋しいのか、わからなかった。わからぬままに、耕三は、助けてくれぇ、と叫びたい衝動に駆られた。
どんどん歩いて、林を抜けると、無数の星が音を立てて降ってきた。















