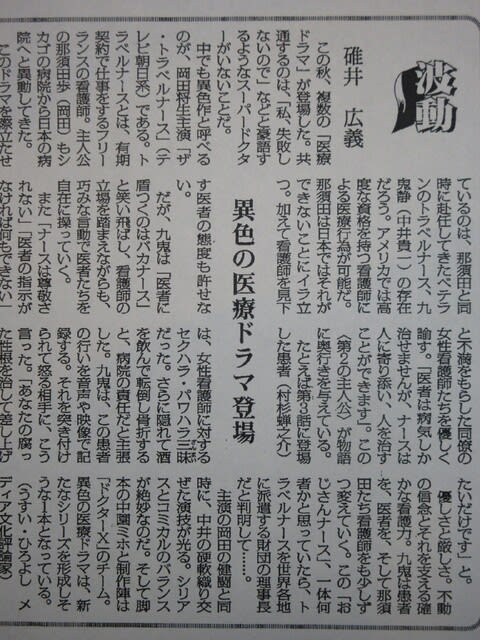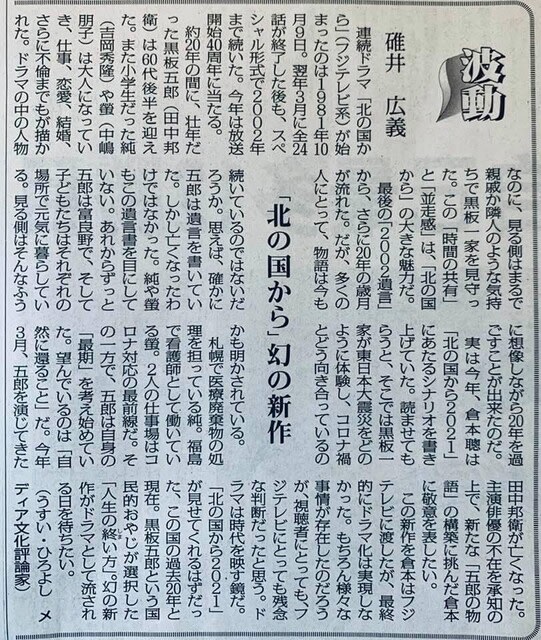ギャラクシー賞の今後
5月31日、第60回ギャラクシー賞(放送批評懇談会主催)の贈賞式が行われた。メインイベントは、すでに公表されていた「入賞作」から選ばれる「大賞」の発表だ。
今回、「テレビ部門」では大賞候補といえる入賞作が14作品あった。ラインナップを見ると、2022年におけるテレビの“成果”が概観できる。
14本のうち、ドラマは連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」(NHK)、「エルピス-希望、あるいは災い-」(関西テレビ放送)、そして「ブラッシュアップライフ」(日本テレビ放送網)など5本だ。いずれも高く評価された作品であり、ドラマの豊作年だったことがよくわかる。
残りの9本はドキュメンタリーなどのノンフィクション系だ。決定的な物証も自白もないまま有罪となった事件を、死刑執行から20年以上を経て問い直し、文化庁芸術祭賞の大賞を受賞したBS1スペシャル「正義の行方~飯塚事件 30年後の迷宮~」(NHK)。
安倍晋三元首相銃撃事件で明らかになった、日本の政治と旧統一教会との深い関係を掘り下げ、いち早く報じた報道1930「激震・旧統一教会と日本政治~問われる政治との距離感は」(BS―TBS)など、こちらも秀作が並んでいた。
最終的に、テレビ部門の大賞に選ばれたのは「エルピス」である。冤罪事件をテーマに、権力や忖度や同調圧力などに挑む者たちを描いただけでなく、メディアのあり方にも一石を投じる優れたドラマだった。
ただ、この結果を知った時、強く感じたことがある。長い歴史を持つギャラクシー賞だが、そろそろドラマとドキュメンタリーを同じ「テレビ部門」で審査する形を変えてもいいのではないか。
賞の審査は最終的に優劣を決めることになる。ドラマの「エルピス」が大賞で、「激震・旧統一教会と日本政治」が優秀賞、「正義の行方」は選奨という序列だが、ジャンルという足場が異なる作品を同じ土俵に上げて審査することに、どこか無理はないだろうか。
放送に関する他の賞はドラマ部門とドキュメンタリー部門が分かれているものがほとんどだ。「エルピス」の大賞に拍手を送りつつ、ギャラクシー賞の今後を思った。
(しんぶん赤旗「波動」2023.06.29)