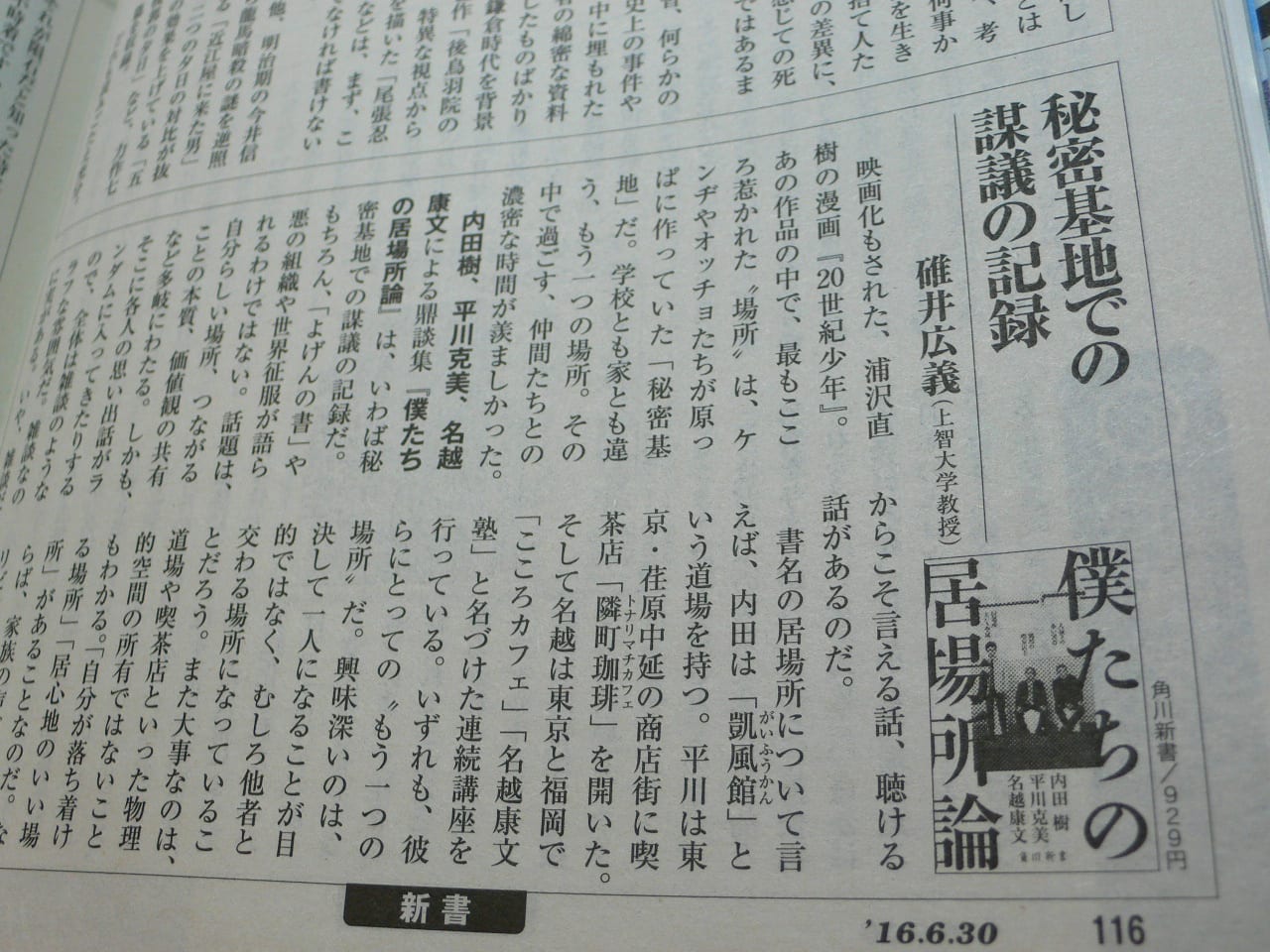
「週刊新潮」の書評欄に書いたのは、以下の本です。
内田樹、平川克美、名越康文
『僕たちの居場所論』
角川新書 929円
映画化もされた、浦沢直樹の漫画『20世紀少年』。あの作品の中で、最もこころ惹かれた“場所”は、ケンヂやオッチョたちが原っぱに作っていた「秘密基地」だ。学校とも家とも違う、もう一つの場所。その中で過ごす、仲間たちとの濃密な時間が羨ましかった。
内田樹、平川克美、名越康文による鼎談集『僕たちの居場所論』は、いわば秘密基地での謀議の記録だ。もちろん、「よげんの書」や悪の組織や世界征服が語られるわけではない。話題は、自分らしい場所、つながることの本質、価値観の共有など多岐にわたる。
しかも、そこに各人の思い出話がランダムに入ってきたりするので、全体は雑談のようなラフな雰囲気だ。雑談なのに実がある。いや、雑談だからこそ言える話、聴ける話があるのだ。
書名の居場所について言えば、内田は「凱風館(がいふうかん)」という道場を持つ。平川は東京・荏原中延の商店街に喫茶店「隣町珈琲(トナリマチカフェ)」を開いた。そして名越は東京と福岡で「こころカフェ」「名越康文塾」と名づけた連続講座を行っている。
いずれも、彼らにとっての“もう一つの場所”だ。興味深いのは、決して一人になることが目的ではなく、むしろ他者と交わる場所になっていることだろう。
また大事なのは、道場や喫茶店といった物理的空間の所有ではないこともわかる。「自分が落ち着ける場所」「居心地のいい場所」があることなのだ。ならば、家族の声が聞こえるリビングの片隅もまた、大人の男の居場所である。
佐藤隆介 『鬼平先生流〔粋な酒飯術〕』
小学館文庫 659円
著者は作家・池波正太郎の“押しかけ書生”だった。日常の中で師匠から勝手に学んだ、食と酒の極意を伝えている。豪華店や高級店より近所の洋食屋を愛し、「食べもの屋は家族だけの小さな店に限る」と言っていた池波。季節を感じつつ暮すことで味覚も深まる。
城山英巳
『中国 消し去られた記録
~北京特派員が見た大国の闇』
白水社 3888円
本書は言論の自由など庶民の権利を守るために活動する人びとの記録だ。人権派弁護士、調査報道記者、そして知識人たちが、抑圧・拘束・投獄される様子に怒りと恐怖を覚える。同時にこの本を上梓した著者の勇気に敬意を払いたい。まずは現実を知ることからだ。
若杉 実 『東京レコ屋ヒストリー』
シンコーミュージック 1944円
音楽もスマホでダウンロードして聴く時代。その一方でレコードも愛され続けている。本書はレコード屋の歴史を深堀りしたノンフィクション。西新宿や目白などのディープ過ぎる店と、マニアック過ぎる男たちが登場する。レコード屋は店そのものが文化なのだ。
小林信彦
『古い洋画と新しい邦画と~本音を申せば』
文藝春秋 1890円
週刊誌連載のクロニクル・エッセイ集だ。ディズニーとアメコミ・ヒーローが氾濫する最近のアメリカ映画を「つまらない」と言い切り、ルビッチやアルトマン、ギャグニーなどを語るのも著者ならでは。一方で綾瀬はるかから安藤さくらまでを的確に評して見事だ。
吉田篤弘 『台所のラジオ』
角川春樹事務所 1728円
クラフト・エヴィング商會の作家による短編集だ。大事件も大恋愛も描かれない。穏やかに暮す人たちの心を揺らす、さざ波のような出来事があるだけだ。それなのに、読後は不思議なあたたかさに包まれる。食べものとラジオが大切な脇役だが、表題作は存在しない。
(週刊新潮 2016.06.30号)









































