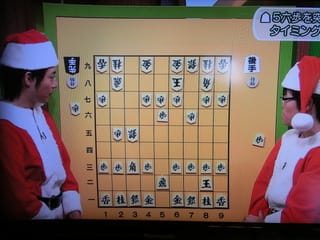(hawaiiフォト・シリーズ)
今年の「こんな本を読んできた」を整理しようと思って、ふと、昨年分のうち11月と12月をアップしないままだったことに気がついた。
遅ればせながらではありますが(笑)、2010年11月の「読んで書評を書いた本」を紹介しておきます。
(掲載は「週刊新潮」)
2010年 こんな本を読んできた(11月編)
佐々木譲『カウントダウン』
毎日新聞社 1680円
財政破綻寸前の町を再生するため立ち上がる男たちを描いた長編小説だ。著者の出身は北海道夕張であり、古里に対する義憤と応援の思いが凝縮されている。
舞台となるのは北海道幌岡市。ワンマン市長の長期政権で市議会は形骸化し、無益な投資が市の財政を危機的状況に追い込んでいた。ある日、司法書士で最年少市議会議員の森下直人の事務所を一人の男が訪れる。選挙コンサルティングの多津美裕だ。以前、大手広告代理店にいたという多津美は、いきなり直人に「市長選に出ろ」と迫る。
あらためて町の惨状に目を向けた直人は、故郷が夕張の二の舞になる前に、火中の栗を拾おうと決意する。極秘で結成される支援組織。専門家の力も借りての現状分析と政策の作成。効果を計算した上での出馬宣言。やがて、直人が予想しなかったほどに過酷で滑稽な選挙戦へと突入していく。
(10.09.25発行)
村松友視『ギターとたくあん~堀威夫流 不良の粋脈』
集英社 1500円
ホリプロの創始者である堀威夫の軌跡を追った人物評伝だ。同時に日本の芸能界の50年史でもある。
昭和23年、16歳の堀少年はラジオから流れる「湯の町エレジー」で音楽に目覚める。アルバイトをした金でギターを購入し、練習を開始。やがて少年は一人前の音楽家へと成長し、人気バンド「スイング・ウエスト」を率いるようになる。順調な流れの中で会社を設立。しかし盟友の叛逆に遭い、全てを失う。ところが、堀威夫はめげない。失敗をバネに新たな芸能プロを興す。それが後のホリプロだ。ここからは舟木一夫、和田アキ子、森昌子、石川さゆり、山口百恵、榊原郁恵といったスターたちの発掘と育成、そして成功の物語が展開されていく。
本書の魅力は堀威夫という男の魅力に尽きる。大胆にして細心。不良性と社会性。その振り幅を著者は「正負の戸板返し」と呼ぶ。
(10.10.20発行)
田村隆一『田村隆一全集 1』
河出書房新社 4725円
没後12年(13回忌)を迎えた現代詩の巨星。満を持して全集の刊行が開始された。この第1巻には最初の詩集『四千の日と夜』など瑞々しい初期詩篇が収められている。また、散文として自伝的要素の強い『若い荒地』も読める。多彩な才能を発揮した詩人の出発点だ。
(10.10.30発行)
ペン編集部:編『印象派。絵画を変えた革命家たち』
阪急コミュニケーションズ 1680円
ゴッホ、モネ、ルノアールなどの印象派と次世代の画家たちが一堂に会した美術ガイドだ。印象派の出現が与えたインパクトの大きさに驚かされる。中でも屹立しているのがゴッホだ。スケッチが挿入された自筆の手紙は、その人間像を知る手掛かりとして興味深い。
(10.10.16発行)
小島正美 『ニュースはこうして造られる~情報を読み解く力』
エネルギーフォーラム 1260円
「ニュースとは切り取られた事実のことだ」と著者はいう。本書は毎日新聞編集委員による情報解読法だ。リスク報道にかかるバイアスや、国民の間に不安が生じるメカニズムなどを分析している。巻末で著者が提案する「報道ガイドライン」の早期実現が望まれる。
(10.10.05発行)
桐野夏生 『優しいおとな』
中央公論新社 1575円
日本そのものが破綻してしまったかのような近未来の渋谷が舞台だ。主人公は1人で生きる15歳の少年イオン。保護施設を脱出して路上生活者となり、炊き出しの食事とささやかなアルバイトで命をつないでいる。
そんなイオンが危険な地下世界へと入っていく。かつて同じ施設で暮らし、自分を守ってくれた双子の兄弟を探すためだ。地下を根拠地とする疑似軍隊に紛れ込んだイオンだったが、双子はなかなか見つからない。やがて、地下世界の住人たち、そしてイオンにも大きな危機が訪れる。
描き出される荒廃した世界と、そこに生きる人間たちの姿は様々な寓意に満ちている。これは前作『東京島』をより進化させた物語なのだ。少年イオンの悲しいまでに愛を求める孤独な魂が胸を打つ。タイトルの「優しい」には、著者が現代社会に向けた痛烈な批判が込められている。
(10.09.25発行)
内田 樹『街場のマンガ論』
小学館 1470円
常日頃「マンガびいき」を標榜する著者のマンガ論。専門である哲学よりも小説よりも熱く語っている。ただし、いかに「日本が誇るソフト」と持ち上げられてもマンガはマンガだ。どこか「日陰者」的存在であることを踏まえた上での「身びいき」であり応援である。
最も頻繁に登場する作品は山本鈴美香『エースをねらえ!』だ。この作品から、日々の生活を「唯一無二のかけがえのない経験」として捉える生き方を学んだと著者はいう。いわば「死に臨んで悔いのない」状態である。また井上雅彦『バガボンド』を「短期間に成長する子どもの物語」と考え、その葛藤と成熟の関係に教育の原点を見出す。
さらに近頃巷の女子に人気の「ボーイズラブ(少年愛)マンガ」にも言及し、全共闘運動の反米ナショナリズム闘争の「松明」を継承したものと位置付ける。独断にして卓見なり。
(10.10.09発行)
辰濃哲郎&医薬経済編集部
『歪んだ権威~密着ルポ 日本医師会 積怨と権力闘争の舞台裏』
医薬経済社 1890円
元朝日新聞記者が日本医師会の内側を活写したノンフィクションだ。軸となるのは熾烈な医師会長選挙。それは狡猾な戦略や知略が横行する、まさに「欲張り村」の村長選挙である。また特定看護師問題をはじめ、自らの権益を守る動きも呆れるほど露骨だ。
(10.09.29発行)
青柳いづみこ『水のまなざし』
文藝春秋 1470円
ピアニストである著者ならではの青春“音楽”小説だ。音大附属高校でピアノを学ぶ真琴は突然声を失う。個人レッスンの教師。療養のため訪れた祖母の家で出会う少年。そして父。少女から大人への揺れる季節が、クラシック音楽をバックに細やかに描かれる。
(10.10.15発行)
講談社:編
『西本願寺御影堂「平成の大修復」全記録 一九九九~二〇〇九』
講談社 1470円
10年を費やした修復が完了した西本願寺の象徴。使用する木の切り出しに始まる作業の全貌を伝えるドキュメントだ。屋根裏には当時の門主・良如と並んで棟梁の名前が残る。新たに焼いた瓦と古い物の共存も見事だ。本書はまた西本願寺とその周辺の案内書でもある。
(10.10.20発行)
玄田有史『希望のつくり方』
岩波新書 798円
希望。本来誰もが持っているはずなのに、いつの間にか忘れていた言葉だ。東大教授の著者と仲間が取り組んだのが「希望学」であり、これはその成果発表である。希望とは何か。著者は「何かを実現したいという思い」であり、そのための「行動」だという。
とはいえ、希望の多くは実現せず失望に変わる。大事なのはその経験を踏まえて次の新たな希望へと柔軟に修正していくこと。大きな壁にぶつかった時は「壁の前でウロウロすべし」のアドバイスもユニークだ。希望学とは希望に出会うためのヒントかもしれない。
(10.10.20発行)
森 博嗣『喜嶋先生の静かな世界』
講談社 1680円
この理系青年の静かな成長物語は平成の『三四郎』ともいうべき作品だ。学ぶ喜び、知る楽しさ、そして学問や師の意味を再認識させる秀作である。
理系学部4年生の僕が配属となったのは喜嶋先生の研究室。先生は何時間かの睡眠以外、すべてを学問に投じたシンプルな生き方だ。卒論を書き、大学院へと進んだ僕もまた、修行僧のような生活に悦楽さえ感じるようになる。「もっと深いところまで潜りたい。もっと遠いものを掴みたい」と研究に没頭していくのだ。
純粋な研究者というべきか。先生は地位にも金にも執着はなく、ひたすら「人間の知恵の領域を広げる」ことに専念する。そんな先生との十数年に及ぶ奇跡のような師弟関係が、僕に影響を及ぼしていくプロセスを丁寧に描いている。理系人間ならではの思考や行動が、これほど新鮮に感じられる小説もあまりない。
(10.10.25発行)
四方田犬彦『人、中年に到る』
白水社 1890円
著者はかつて『ハイスクール1968』で自らの青春とその時代を描いた。本書では、57歳になる自分自身の内側だけに目を向け、深い思索を展開している。本文にも登場するモンテーニュになぞらえて、エッセイではなく、『エセー(随想録)』と呼びたい一冊だ。
「本と娼婦」では、書物は読むことはもちろん、その背表紙から醸し出される滋養が人に影響を与えると指摘する。また「わたしはなぜ旅に出るか」では、旅の目的と効用として再生、達観、内省の三つを挙げる。旅は人を自分自身との対話へと向かわせるのだ。
「わたしは世代を標榜するいかなる力にも与したくない」と書くのは「世代について」の項である。人間を個人としてでなく、ひとくくりの束として扱うこと、さらに例外を排除することへの嫌悪だ。こうした著者ならではの感性と論理が、読む者を強く刺激する。
(10.10.10発行)
稲葉なおと『ドクター・サンタの住宅研究所』
偕成社 1260円
森の奥にある奇妙な研究所。所長は工学博士であり、子どもの悩みを解決してくれる「発明家」でもあった。3つの物語からは、住宅がそこに暮らす人間の心をも守る場所であることが伝わってくる。一級建築士で文筆家の著者による、子どもと大人のための寓話集だ。
(10年11月発行)
吉野朔実 『神様は本を読まない』
本の雑誌社 1365円
『本の雑誌』に連載中の、<読書エッセイマンガ>シリーズ最新刊。著者自身をデフォルメした主人公の、ユーモアとシニカルが微妙に配分された読書生活が可笑しい。新刊だけでなく旧作も頻繁に登場するブックガイドでもある。翻訳家・柴田元幸との対談付きだ。
(10.10.15発行)
黒沢 清 『黒沢清、21世紀の映画を語る』
boid 2310円
映画『トウキョウソナタ』などの監督であり、東京芸大教授でもある著者の講演・講義録だ。小津安二郎、大島渚からフェリーニまでを取り上げ、「この映画のここを見ろ」とアジテートする。映画論の師匠は蓮實重彦だが、全編語り言葉であるため分かりやすい。
(10.10.15発行)
西澤保彦 『幻視時代』
中央公論新社 1680円
物語は意外な場面から始まる。文芸評論家の矢渡利悠人と作家の生浦蔵之介が偶然立ち寄った写真展。そこで二人は“あり得ないもの”を見る。展示された一枚に写っていたのは、彼らと高校の文芸部で一緒だった風祭飛鳥だ。写真が撮影されたのは1992年。しかし、彼女はその4年前に遺体で発見されていた。
SFやミステリが好きだった悠人が、高校の文芸部に入ったのは86年ことだ。顧問の国語教師・白洲、早熟な文学少女・飛鳥、そして後輩である蔵之介と知り合っていく。悠人は密かに飛鳥に憧れるが、相手にはされなかった。やがて飛鳥が文芸誌主催の新人文学賞を最年少で受賞。天才女子高生作家の誕生は、飛鳥自身だけでなく周囲の人間の運命をも変えていく。
現在の悠人、蔵之介、編集者・長廻の三人が掘り起こす、22年前と18年前の衝撃の真実とは・・・。
(10.10.25発行)
工藤美代子『悪名の棺 笹川良一伝』
幻冬舎 1785円
「人事は棺を蓋うて定まる」という。ならば死後15年を経た笹川良一の評価は定まっているのだろうか。「政財界の黒幕」「ギャンブル王」などのイメージは今も健在だ。一方、海外では慈善活動家として称えられている。本書はその落差の中にある希有な人物像を描き出す試みだ。
まず驚くのは戦前・戦中の「愛国運動」の資金源。笹川はこれを軍部や企業との関係から生じた金ではなく、相場師として得た巨額の利益、つまり自費で賄っていたという。それでいて日常生活では倹約を通した。
また、あたかも盟友のごとく語られることの多い児玉誉士夫との因縁と確執、背信の真相も明らかになる。さらに、遺族からの証言を踏まえた艶福家として姿。西と東を行き来しながらの「愛の分配」は、その呆れるようなスケールもあって苦笑いしたくなる。人間・笹川良一の真骨頂だ。
(10.10.25発行)
勝目 梓『死支度』
講談社 1680円
今年78歳を迎える著者の老境幻想小説だ。妻を亡くした99歳の男が死を前にして“最期の望み”を遂げようとする。それは女性の体毛を使った奇想天外な企みだった。性への妄執は生への執着なのか。夢と現実の狭間に浮かび上がる、過激にして清冽な物語だ。
(10.10.27発行)
野地秋嘉『昭和のスター王国を築いた男 渡辺晋物語』
マガジンハウス 1680円
4年前の『芸能ビジネスを創った男 渡辺プロとその時代』に加筆。さらに秘蔵写真を掲載した新装版だ。渡辺が芸能プロを近代産業化した功績は大きい。またナベプロ出身の人々が芸能界を動かしてきたことも分かる。出色の昭和芸能史。
(10.10.21発行)
NHK「無縁社会プロジェクト」取材班:編著
『無縁社会~“無縁死”三万二千人の衝撃』
文藝春秋 1400円
NHKスペシャルで放映され、大きな反響を呼んだ秀作ドキュメンタリーの単行本化だ。長期化する不況。揺らぐ仕事や家庭。自殺率世界第2位のこの国で、引き取り手さえ不在の孤独な死が増加中だ。そんな誰ともつながれない「無縁社会」の実体を明らかにする。
(10.11.15発行)
石川輝吉『ニーチェはこう考えた』
ちくまプリマー新書 819円
大学の教壇に立ちながら思索を続ける著者によれば、ニーチェの哲学は「うじうじした小さな人間のための哲学」である。また、「どうしたら苦しみにもかかわらず元気を出して生きられるか」を考え抜いて生まれたものだ。それはまさに現代人が抱える命題でもある。
ニーチェを支えた柱は三つ。ギリシャ悲劇、ショーペンハウアーの哲学、そしてワーグナーの音楽だ。これら「ほんもの」の力を借りて、ニーチェは自身を開放していく。本書でその思想の歩みをたどるうちに、「自分を変えるのは自分」という覚悟が見えてくる。
(10.11.15発行)
三浦しをん『小暮荘物語』
祥伝社 1575円
「小暮荘」は、時代から取り残されたような古い木造アパートだ。住人たちも、ちょっと不思議な人ばかり。本書は、小暮荘とその周辺で繰り広げられるウエルメイドな人間模様の連作集だ。
二階に住む坂田繭の部屋に、突然、瀬戸並木がやって来る。修業中のカメラマンである並木はかつての恋人だが、何年も音信不通だった。今、繭は伊藤晃生とつき合っている。並木が乱入してきた時も部屋には晃生がいた。新旧の男二人が狭い部屋で向かい会う。
同じ二階で暮らす神埼はサラリーマン。金もなく恋人もいない彼の楽しみは、階下の女子大生・光子の生態を覗き見ることだ。いつの間にか、光子本人より彼女のことを知るようになる。
その光子と仲がいいのは大家の小暮だ。妻のいる家を出て自分のアパートで暮らすこの老人には、死ぬ前に思い切りセックスをしたいという秘めた願望があった。
(10.11.10発行)
宮本徳蔵 『文豪の食卓』
白水社 1575円
タイトル通りの本ではない。文豪は登場するが、好物料理を紹介するわけではないからだ。料理は、いわば刺身のつま。同時代作家としての回想と文芸評論が融合した、滋味溢れる文学エッセイである。
たとえば著者が学生の頃。東大正門前の「白十字」で小林秀雄が渡辺一夫、中島健蔵などと歓談している。青年たちは離れたテーブルで珈琲をすすりながら聴き耳をたてた。話はそこから『本居宣長』に移り、宣長と著者の故郷である松坂のこと、恩師・寺田透の小林への評価、さらに小林の「直感」に関するエピソードが語られていく。
また埴谷雄高との京都旅行の思い出も貴重品。寺だけでなく先斗町や祇園を歩く珍道中に、埴谷と三島由紀夫をめぐる逸話が加わる。他にも井伏鱒二と鰻、泉鏡花とうどん、谷崎潤一郎と葛など、“美味そうな話”が目白押しだ。
(10.10.15発行)
渋井哲也
『自殺を防ぐためのいくつかの手がかり~未遂者の声と、対策の現場から』
河出書房新社 1575円
著者は長年自殺をテーマに取材を続けるフリージャーナリスト。年間3万人台という“自殺王国”の背景に何があるのかを、未遂者たちの証言から探っている。さらにネット上での自殺対策や地域で取り組むべき方策についても言及。「支え合う」社会への示唆に富む。
(10.11.30発行)
岡田邦雄 『ル・コルビュジエの愛したクルマ』
平凡社 1680円
建築家として余りに著名なコルビュジエの創造に、新たなスポットを当てた好著。紹介される名建築以上に、クルマ社会の到来を前提とした建物や都市計画の存在に驚く。また彼が設計したマキシマムカーも、小さなボディと大きな機能を両立させたデザインが新鮮だ。
(10.10.15発行)
木原武一 『快楽の哲学~より豊かに生きるために』
NHKブックス 998円
ギリシャ哲学からカント、そしてゲーテまで。『人生に効く漱石の言葉』などで知られる著者が挑む“快楽の思想史”だ。「幸福は状態のなかに、快楽は活動のなかにある」と著者は言う。その活動の原動力は欲望だ。満たされないものへの渇望こそが快楽へとつながる。
(10.10.30発行)