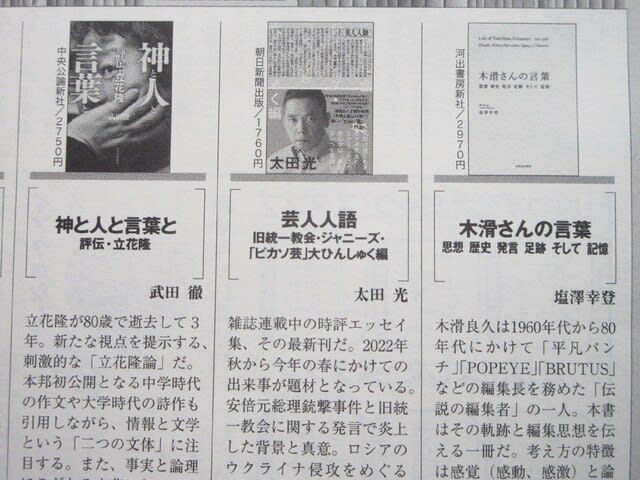池袋発、北三陸経由での〝現在地〟
『新宿野戦病院』は
クドカン流「地元ドラマ」の進化形だ
宮藤官九郎が脚本を担当する『新宿野戦病院』(フジテレビ系)が、早くも「目が離せない作品」となっている。
物語の舞台は新宿・歌舞伎町にある「聖まごころ病院」。ヒロインは元軍医の日系アメリカ人である、ヨウコ・ニシ・フリーマン(小池栄子)だ。英語と日本語(岡山弁)のバイリンガルで、外科医を探していたこの病院で働くことになった。
もう1人の主人公は、院長の甥で美容皮膚科医の高峰亨(仲野太賀)だ。愛車の白いポルシェを乗り回し、夜ともなれば港区女子との「ギャラ飲み」に忙しい。無邪気な“ゆとりモンスター”とも言える30代男である。
この2人を取り巻く人たちもまたクセが強い。アルコールが切れるとメスを持つ手が震える、元外科医で院長の高峰啓介(柄本明)。英語に堪能な看護師長・堀井しのぶ(塚地武雅)はジェンダー不詳。ギャラ飲みとパパ活の区別にこだわる、内科医の横山勝幸(岡部たかし)。さらに地域の支援活動家、南舞(みなみ まい、橋本愛)もかなりのワケアリと見た。
そこに反社、風俗嬢、不法移民、トー横少女など、歌舞伎町に生息する多様な人々がからんでくる。すでに元暴力団の老人による発砲事件もホストの転落事故も起きた。
ヨウコは外科医だが、日本の医師免許は持っていない。しかし、院長のサポート役を装いながら、実際は彼女が患者の命を救っていく。
「目の前の救える命を救うために、私は軍医になった」とヨウコは言う。アメリカでは、患者の貧富の差が、受けられる医療の差になっている。
しかし、戦地では男も女も善人も悪人も命に区別はない。「平等に雑に助ける、それが医者!」が信条だ。「ドクターX」ならぬ、「ドクターY」。手術は雑だが、腕はいい。
◆「池袋」発、「北三陸」経由、「歌舞伎町」行き
当初、新宿・歌舞伎町という「地域限定」の設定から、池袋を舞台にした『池袋ウエストゲートパーク』(TBS系、‘00年)のような「地元ドラマ」を連想した。クドカンの初連ドラ脚本だ。
主人公の真島誠(長瀬智也)は、賭けボーリングなどで小銭を稼ぐ遊び人。実家の果物屋の店番であり、トラブルシュータ―だ。ストリートギャング「Gボーイズ」の安藤崇(窪塚洋介)たちと組んで、面倒な事件を解決していく。
事件の背景にあるのは援助交際、ひきこもり、虐待、ストーカー、マルチ商法といった社会的病理だ。ドラマは見事なハードボイルド・コメディになっていた。
あれから四半世紀が過ぎた現在、クドカンが見つけた、当時の池袋に匹敵するカオス度の高いエリア。それが今回の新宿・歌舞伎町だ。
しかし、誠たちにとって池袋が「地元」だったのに対し、歌舞伎町はヨウコの地元ではない。そこに流れてきた者、入り込んできた者であり、いわば「異分子」である。だが、その異分子が周囲に影響を及ぼし、変えていく。
その構造は、クドカン脚本の朝ドラ『あまちゃん』(NHK、’13年)を思わせる。
一般的な朝ドラのヒロインたちは、さまざまな体験を重ねることで成長し、変化していく。だが、『あまちゃん』の天野アキ(能年玲奈)は違った。成長はしたかもしれないが、基本的に当人の実質は変わらないのだ。
むしろアキという「異分子」に振り回されることで、徐々に変化していくのは周囲の人たちのほうだった。それは北三陸の人たちも、東京で出会った人たちも同様だ。その様子は、文化人類学者・山口昌男が言うところの「トリックスター」を想起させる。
いたずら者のイメージをもつトリックスターは、「一方では秩序に対する脅威として排除されるのであるが、他方では活力を失った(ひからびた)秩序を賦活・更新するために必要なものとして要請される」(山口『文化と両義性』)からだ。
アキが北三陸に現れた時、地元の人たちにとっては「天野春子の娘」という〝脇役〟にすぎなかった。また、アキはアイドルとなるべく上京したが、本当に待たれていたのは「可愛いほう」のユイ(橋本愛!)であり、「なまってるほう」のアキはオマケだったのだ。
ところが、いつの間にか人々の中心にアキがいた。「トリックスターは脇役として登場しながらも、最後には主役になりおおせる」(山口『文化記号論研究における「異化」の概念』)のだ。
◆地元に降臨した「トリックスター」
ならば、ヨウコもまた、歌舞伎町という地元に現れたトリックスターではないだろうか。
日系アメリカ人っぽい英語と、岡山生まれの日本人である母親(余貴美子)から受け継いだ岡山弁が入り交じるヨウコの語り。それはクドカンらしい〝発明品〟だ。見る側を引き込む、独特の迫力と説得力がある。
「(英語で)私は見た。負傷した兵士、病気の子供。運ばれて来る時は違う人間、違う命。なのに死ぬとき、命が消えるとき、(岡山弁で)皆、一緒じゃ!」
続けて、「(英語で)心臓が止まり、息が止まり、冷たくなる。(岡山弁で)死ぬときゃ、一緒。それがつれえ。もんげえつれえ」
もんげえつれえ(すごく辛い)からこそ、「平等に、雑に助ける」のだ。
「Yes」か「No」の判断が難しい時も、英語の“Yeah”と日本語の”いや“のちょうど中間を狙った、「イヤー」で乗り切っていく。
そんなヨウコの存在は、チャラ系医師の亨をはじめ、患者も含めた周囲の人たちを少しずつ、だが確実に変え始めている。
クドカンが30代で書いた「池袋」、40代の「北三陸」、そして50代での「新宿・歌舞伎町」。『新宿野戦病院』は、20年を経たクドカン流「地元ドラマ」の進化形だ。
(FRIDAYデジタル 2024.07.17)