
コロナ禍による医療危機、
北海道で脚本家「倉本聰」が動いた
新型コロナウイルスによる医療危機に対して、現在、北海道で以下のような「取り組み」が行われています。
発端は、脚本家の倉本聰さんが、昨年の12月末に地元の北海道新聞に寄稿した一文でした。
その一部を転載してみます。
医療危機に対し ー(いち)道民として今考えること
新型コロナが発生して以来、医療現場は苛烈を極めている。
元々脆弱(ぜいじゃく)だった北海道の医療は瀕死(ひんし)の状態に追いこまれており、殊にそのしわ寄せは看護師・介護士・事務員を中心とする現場の医療従事者に集中していて、SNSの投稿などを見ても悲鳴に近い彼らの声が溢(あふ)れる。
おまけに心ない風評被害が彼らを直接襲っており、保育所からの子供の預かり拒否、病院へのタクシーの乗車拒否等々聞くに耐えない誹謗(ひぼう)中傷が彼らの周辺で渦まいている。
従って離職者がどんどん増えていて、ベッドの数よりその面からの医療崩壊がささやかれている。
政府はGOTOキャンペーンで経済優先の施策ばかり打つが、命の現場で必死の戦場のただ中にいる彼らの事を、一体どの位本気で考えているのかよく判(わか)らない。
いや。そういう論評をするのはもう止めよう。
恐らく官は官で懸命の努力をしているのだろうから、我々(われわれ)は今、民の立場から出来る行動にふみ出すことを考えようではないか。
本州のことはとりあえず措(お)いて道民としてまず北海道の中でのことを考えよう。
医師・看護師・介護士たちはその使命感から過剰労働に懸命に耐えている。それに対する危険手当、超過勤務手当がどれ程(ほど)出ているのか僕は知らない。
只(ただ)彼らが勿論(もちろん)医師を含めて疲労のどん底にいることは察して余りある。看護師の間に精神的疲労がたまり、ウツが拡(ひろ)まっているという情報も知っている。
そういう時に今、僕ら道民の一人一人が、何か彼らに報いるすべはないのか。
経済的な支援は勿論、何よりも僕らが彼ら医療関係者に心底感謝しているということ。その感謝の気持ちをどう表現したら良いかと、思いつかずにいらついていること。
まずそのことを彼らに伝えて感謝の想(おも)いを伝えたい。僕がこの文を書いているのは純粋にそういう思いからである。
GOTOキャンペーンを中心として政府は観光業・飲食接待業への経済的支援を懸命に考える。それはそれで良い。
だが、官がそのことに重点を置くなら、民である僕らはもう一つの柱である命の救済という大きなテーマとそこに関連する医療従事者に及ばずながら感謝の気持ちを伝えようではないか。
他の都府県がどこも行わない民力の結集を、この北海道から起こそうではないか。
(北海道新聞 2020年12月26日付より)
「民である僕ら」にも出来ること
倉本さんの、黙して眺めているに忍びないという、切実な思いがここにあります。
そして、まさにその思いが、読者にも伝わったのでしょう。この記事に大きな反響があり、それを受けて新聞社や応援する人たちも動き出し、具体的なプロジェクトとして立ち上がったのです。
名前は、北海道医療従事者応援プロジェクト「結(ゆい)」。
発起人は、
岡田武史(サッカー元コンサドーレ札幌監督)
倉本聰(脚本家)
栗山英樹(プロ野球北海道日本ハムファイターズ監督)
中島みゆき(シンガーソングライター)
広瀬兼三(北海道新聞社長)
三浦雄一郎(プロスキーヤー)
の各氏です。
ベースとなるのは募金活動で、1月15日に開始されました。北海道病院協会などを通じて、道内の医師、看護師、介護士といった現場の方々に届けようというものです。
また同時に、医療従事者が受けている、いわれなき差別など、卑劣な行為に対する啓蒙活動。さらに意識向上のための、草の根的な運動も繰り広げようとしています。
3月いっぱいが締切の募金は、本日現在で約1460万円に達しました。
すべては、86歳になる脚本家が、一人の道民の立場から、「民である僕ら」にも出来ることがあるのではないか。出来る形で「医療従事者に報いよう」と呼びかけたことが始まりです。
こういう「街場の取り組み」が、実際に進行中であるということ。
そして、決して北海道だけの話ではなく、他の地域でも展開可能なものであることも含め、多くの示唆に富む事例ではないかと思います。
【解読『おちょやん』】
道頓堀ロミジュリの恋の行方は
東野絢香が「みつえ」を熱演
NHK朝の連続テレビ小説『おちょやん』の第11週(2月15日~19日)は、舞台と現実、2つの「家庭劇」で笑わせて泣かせる劇的展開でした。
道頓堀の『ロミオとジュリエット』
昭和3年(1928)の大阪・道頓堀。芝居茶屋という商売も難しい時代で、「岡安」のライバルだった「福富」も、すでに楽器店になっています。
「岡安」は苦しいながらも頑張っていますが、女将のシズ(篠原涼子)と夫の宗助(名倉潤)は、一人娘のみつえ(東野絢香)を嫁に出すことを考えていました。
そこに老舗料亭の跡取りとの縁談が舞い込みます。しかし、みつえは、いい返事をしません。「福富」の息子・福助(井上拓哉)が好きだったのです。
とはいえ、みつえと福助の結婚は、シズと福助の母であるキク(いしのようこ)の関係を考えると無理筋でした。
2人を何とかしてあげたい千代(杉咲花)。ふと思いついたのが「芝居」です。
チンピラにからまれたみつえを、福助が救ったことにして、「頼りになる男」「みつえにふさわしい青年」としてシズに認めさせようというのです。台本は一平(成田凌)に書いてもらいました。
ところが、シズに仕掛けがばれて大失敗。シズは「今すぐ、別れなはれ。あんたのためだす」と、しずえに迫ります。
「岡安」の女将になることも、福助との結婚もできないと知ったしずえが、思わず大声を上げました。
「これ以上、うちの夢、取り上げんといて!」
さらに、キクが大口のお客を「岡安」に回してくれたことを知ったシズは、「福富」に乗り込んでいきました。
シズから「施(ほどこ)しなんてお断り」だと言われたキクは怒り、「あんたも、この娘も目障りや」と言い返します。さらに、みつえに向って・・・
「人には、ふさわしい居場所がある。あんたは、うちにふさわしくない!」
落胆するみつえ。シズとキクの対立は、どこから来たものなのか。それを、みつえと千代に教えてくれたのは、みつえの祖母でシズの母であるハナ(宮田圭子)でした。
若い頃、「福富」のお茶子だったハナは、暖簾分けしてもらって「岡安」を開きました。その時、何人かの「ごひいき客」を引き抜いてしまったのです。
以来、「福富」の女将となったキクの母と、「岡安」の女将であるハナは、いわゆる犬猿の仲に。そんな母親同士を見て育ったのがシズとキクでした。
そして、打ち明け話をしたハナは、最後に言います。
「おばあちゃんは、あんたの味方や。幸せになり。ええな」
宮田さんの滋味あふれる笑顔が忘れられない、いい場面になりました。
涙と笑いの『マットン婆さん』
一方、千代が所属する「鶴亀家庭劇」では、次の公演のトリで、一平が書いた『母に捧げる記』を上演することになっていました。
そこに千之助(星田英利)が割って入ります。『母に捧げる記』の台本を、大幅に手直ししたものでやると言い出したのです。タイトルも『マットン婆さん』に変更。
この『マットン婆さん』ですが、現実の「松竹新喜劇」でも評判をとった喜劇『ハットン婆さん』を下敷きにしたものです。松竹では、あの藤山寛美も出演した、当たり芝居でした。
『マットン婆さん』の主人公は、奉公先の片桐家で長年にわたって女中をしてきた、お松(演じるのは千之助)。
主(あるじ)である片桐儀平の妻は早く亡くなり、残された3人の子供を育てたのは「マットン」と呼ばれる、お松でした。「お松どん」が「おまつどん」、そして「マットン」に。
30年後、詐欺に遭って、お金に困った長男・正一郎(須我廼家天晴)と長女・満里子(千代)。
父の儀平に頼みますが断られ、実の子には金を出さず、他人のマットンに給金を払い続けるのはおかしいと抗議します。
すると、末っ子の三郎(一平)が、「これを使って」と大金を差し出します。それはマットンがこつこつ貯めてきたものでした。
そこにマットンが現れるのですが、千之助の芝居は、台本から逸脱したものになっていきます。見ている側もスリリングで目が離せません。
マットンは、三郎に自分の金であることは「ないしょに」とささやきながら、つい自分でバラしてしまう。それなのに、「口が軽い!」と三郎を注意して、客を笑わせます。
そして、一同に自分の気持ちを明かすマットン・・・
「これまで、たんと無理言われてきたけど、頼りにしてくれてるんやと嬉しうて。これからも遠慮のう無理言うて、困らせておくれなはれ」
続けて、
「どう逆立ちしたかて、ほんまのお母ちゃんにはなれしまへんけど、ほんまのお母ちゃんの代りに無理聞いてあげるんが、マットンの生きる喜びです」
泣きながら語るマットン。見る側も、もらい泣きです。
思わず「マットン」と呼びかける正一郎に、三郎が・・・
「マットン、違いますやろ」
満里子も「せやな」と応じ、マットンに呼びかけます。
「おおきに、お母さん!」
嬉しいやら、照れくさいやらで、体をゆすって泣くマットン。
「マットン」ではなく、「マットンを演じる千之助」そのものと化した、星田さんに拍手です。
この場面で、一平は、自分が『母に捧げる記』で描こうとしていた「母の無償の愛」を、千之助が見事に芝居にしていることに気づきます。
同時に、千之助が自分の「親代り」になろうとしてくれていたことも。
こういう流れ、八津弘幸さんの脚本が上手い。
因縁の「神社」での奇跡
みつえと福助は「駆け落ち」を決行します。皆は大騒ぎで探しますが、見つかりません。
駆け出した千代が向かったのは神社。2人がいました。
この神社、見たことがある。そう。若い頃のシズの悲恋の舞台。歌舞伎役者の早川延四郎(片岡松十郎)との因縁の場所でした。
みつえに向って千代が言います。
「(シズに)もっと無理言うたったら、ええねん。何べんでも無理言い続けたら、必ず許してくれる」
そんなことがなぜ分かるのかと言い張るみつえに・・・
「なんで分かるか。(シズは)みつえのお母ちゃんさかいな。駆け落ちしたら、会えなくなる。帰る場所が無うなる」
みつえの中に、千代の言葉が浸透していきます。
そこにシズが来ました。神頼みしようと思ったのです。
みつえが訴えます。
「お母ちゃん、堪忍。うちが間違うてた。やぱり、お母ちゃん、お父ちゃん、おばあちゃん、好きや。離れたない。もう二度と駆け落ちなんか、せえへん。うちは一生、お母ちゃんの娘や」
さらに・・・
「せやさかい、無理言います。福助と一緒にならしておくれやす! 何べんでも言います。困らせます。堪忍。我がまま娘やねん。福助のこと、お母ちゃんたちと同じくらい好きなん。家族になりたいんだす!」
東野さんの見せ場、熱演です。
そして、みつえは土下座! もちろん福助も。
それを見たシズは2人の仲を許すことに決め、キクに頭を下げに行きます。
2つの「家庭劇」の先に
昭和4年(1929)の春、みつえと福助の祝言が行われました。
その席で、ハナがキクの盃にお酒を注ぎます。
「あんたのお母さんの代りに」
それを飲み干し、今度はハナに盃を差し出すキク。
「お母さんの代りだす」
いや、泣けますね。さり気ないやり取りでありながら、これまた名場面の一つとなりました。
みつえと福助という「小さな家族」の誕生であり、「岡安」と「福富」が大きな傘の下に集まった「大きな家族」の出現でもあります。
道頓堀のロミオとジュリエットによる「駆け落ち騒動」という、街場で演じられた「家庭劇」。そして、『マットン婆さん』という名の舞台で演じられた「家庭劇」。
どちらも思いきり笑わせて、存分に泣かせてくれました。この2つを同時進行で見せながら、やがて姿を現すはずの、千代と一平による新たな「家庭」を予感させる第11週でした。
”忖度”は一切なし 確信と執念の映画評
蓮實重彦『見るレッスン 映画史特別講義』
光文社新書 902円
これは出版界の事件ではないか。あの蓮實重彦が「新書」を出したのだ。本人によれば、この『見るレッスン 映画史特別講義』は最初で最後の新書である。
驚くのはそれだけではない。難解ではないのだ。むしろ分りやすい。そして読みやすい。まさに新書だ。特別講義はハリウッド映画の現在に始まり、日本映画、ドキュメンタリー、ヌーベル・バーグなど全7講。基礎を学べる概説部分もあるが、醍醐味は確信をもって展開される持論だろう。
蓮實の興味は映画作家にしかない。海外でのイチオシは『セインツ』や『さらば愛しきアウトロー』の監督デヴィッド・ロウリー。構図や光線、被写体との距離など、その「ショット」を絶賛する。日本で注目するのはドキュメンタリーの女性監督。『空に聞く』の小森はるかと『セノーテ』の小田香だ。作り手としての価値を「時間」というキーワードで解説していく。
一方、『ロスト・イン・トランスレーション』のソフィア・コッポラは「演出が下手くそ」で、「工夫が何もできていない人」だと断言している。また国内では、『ホットギミック』などの山戸結希を「映画に対する飢えというものが彼女には全くない」と酷評。蜷川実花も「天性の映画監督ではない人が撮っている」と見事に一刀両断だ。ここまで言える映画評論家など滅多にいない。
伝わってくるのは映画を見ることへの執念だ。「見るからには本気で見ろよ」の言葉が突き刺さる。
(週刊新潮 2021.02.04号)
【解読『おちょやん』】
明日海りお演じる
ルリ子が凄かったアドリブ合戦
鶴亀は次のステップへ
「鶴亀家庭劇」の旗揚げ公演に向けて動く、千代(杉咲花)や一平(成田凌)たち。
しかし、千之助(星田英利)は黙っていません。一平が書いた台本に代って、自作を上演することを主張。しかも舞台では、その台本通りの芝居をせず、皆を混乱させます。
『おちょやん』第10週(2月8日~12日)は、「喜劇」の面白さに目覚めていく千代の奮闘記でした。
「手違い噺(ばなし)」は実在の芝居!
「鶴亀家庭劇」の旗揚げ公演。演目は千之助が書いた『手違い噺』です。
この芝居のポイントは、泥棒に斬り落とされた、旦那(千之助)の腕と使用人(一平)の腕を、ヤブ医者(曾我廼家寛太郎)が取り違えてくっつけてしまったことにあります。
旦那が右手を上げようとすると、使用人の右手が動いてしまう。困った2人の掛け合いが笑いを呼ぶはずでした。
しかし、意気込みだけはあるものの、寄せ集めのメンバーで構成された「鶴亀家庭劇」。とても一枚岩とは言えず、芝居そのものも、お客さんにウケません。
焦った千之助は、「見せ場」になると、台本を無視してアドリブに走ります。
「見せ場」とは、旦那の浮気現場に妻の高峰ルリ子(明日海りお)が踏み込んでくるところです。
千之助は段取りとは異なる場所から登場したり、セリフも瞬間的に作っていきます。他のメンバーは大混乱ですが、お客さんは大笑いでした。
実は、この『手違い噺』という芝居、当時の「松竹家庭劇」で上演された、実在のものなのです。
ドラマの千代は女中さんの役ですが、モデルの浪花千栄子が演じたのは旦那の妻の役でした。
松竹新喜劇は、『手違い噺』を戦後になっても上演を続け、夜の部の最後を飾る演目になったりしていました。創始者たちへのリスペクトを感じますね。
女優・高峰ルリ子の「反乱」
第10週で一段と存在感を高めたのが、新派劇出身の女優・高峰ルリ子であり、それを演じる宝塚出身の明日海りおさんです。
あの強烈な「カメラ目線」からは誰も逃げられません。千之助の芝居観や喜劇観と最も対立したのがルリ子でした。
千之助、いわく・・・
「喜劇はな、お客さん笑かして、なんぼや!」
さらに、
「ホン(台本)なんて、見取り図に過ぎん!」
と豪語します。
「やっぱり喜劇なんてやるんじゃなかった!」と出ていくルリ子。しかし、彼女がいないと芝居が成立しません。
悩んでいる千代にヒントを与えてくれたのは、「岡安」の女将シズでした。
「相手に笑って欲しかったら、まず自分が笑わんとな」
千代はルリ子と2人だけで話をしてみます。
ルリ子が語ったのは、かつて劇団の主宰者で恋人だった男性と主役の座の両方を、映画出身の若手女優に奪われた過去でした。
ルリ子が何より傷ついたのは、若手女優が流した噂(自分を絞め殺そうとしたなど)を、愛した男が信じてしまったことだったのです。しかも、その女優が千代に似ているのだと。
そんなルリ子に向って千代が言います。
「うちは裏切ったりせえへん。こないなことで女優やめたらあかん!」
千代の真情は、ルリ子の凍りついた心を、じんわりと溶かしていきました。
そうそう、このシーンのラストに登場した猫。ほんと、いい芝居してましたね(笑)。
千代たちと千之助の「笑かし勝負」
ルリ子は戻りましたが、一同と千之助の対立は「笑かし勝負」に発展します。客に投票用紙を配り、よかった役者の名前を書いてもらって、その数によっては千之助が座長になるというのです。
ところが、みんながどんなに頑張っても、千之助を超えることは出来ません。ルリ子も「悔しいけど、(千之助は)すごい」と認めます。
そんな千代たちの前に現れたのが、なんと師匠の山村千鳥(若村麻由美)でした。
「なぜ、ここに?」と聞く千代に、
「嫌がらせに決まってるでしょ!」
と千鳥。やはり、いいですねえ、若村さん。
ここで千鳥は、千代たちにとって、決定的なアドバイスの言葉を残します。
「演じるということは、役を愛した時間そのものよ!」
千代たちは、これまで自分たちが演じる人物像について、深く考えてこなかったことに気づきます。それぞれに、役の「深掘り」を始めました。
『手違い噺』の千秋楽。芝居小屋には、「岡安」や「福富」の面々だけでなく、大山社長(中村鴈治郎)や須我廼家万太郎(板尾創路)も来ています。そして、舞台袖には千鳥の姿も。
この日の千之助は、いつも以上に過激でした。旦那が、浮気しているのは自分ではなく、取り巻きの一人でもあるヤブ医者だと言い出したのです。
千代も、ルリ子も「開眼」!
台本と違っているだけでなく、それまでのどんなパターンよりも難しい局面でした。
しかし、千代もルリ子も香里(松本妃代)も、自分自身ではなく、役柄の人物として考え、言葉を発し、動いていきます。みんなが役を生き始めたのです。
火花散る、アドリブの応酬。
千之助が心の中で「さあ、どうする?」と言いながら投げたボールを、千代たちも心の中で「うん、そう来たか!」と言いながら打ち返す。
そんな心の声である「インナーボイス」も炸裂し、みんなが弾けまくります。
特に、ルリ子が凄かった。妻が旦那への思いを語るくだりで、かつて恋人に裏切られた時の気持ちを重ね、役柄を通じて自分をさらけ出したのです。
「首絞めたりしてへん! ただの噂だす。誰に、どない思われようと構しまへん。あなただけは信じて欲しかった」
しかも、つい「彦一郎さーん!」と、かつての恋人の名前を呼んでしまい、「しもた」と漏らします。この瞬間のルリ子が可愛い。
「しもたと言うたら、あきまへんがな」と千代がフォローして、客席は大爆笑。結果的に芝居は大成功でした。
千代たちに声をかけずに去ろうとする千鳥。鶴亀社員の熊田(西川忠志)に呼びとめられて、言います。
「会っても言うことないから」
初めて千代を認めてくれたんですね。おおきに、千鳥はん!
さらに楽屋では、千之助がみんなに告げます。
「わしと一緒にやるねんやったら、次はもっと笑かさな、承知せえへんぞ!」
さすが、『半沢直樹』の脚本家、八津弘幸さん。この第10週も、起伏にあふれた展開と、大事な場面での名セリフが堪能できました。
次週、千代たち「鶴亀家庭劇」は、次のステップへと進んでいきます。
『青天を衝け』の渋沢栄一が、
実際に出会った
幕末・明治の「有名人」は誰?
14日にスタートした、NHK大河ドラマ『青天を衝け』。
先日、初回を見ての感想と今後への期待を、夕刊紙の記者さんから求められました。
30分ほど話をしたのですが、もちろん記事になるのはその一部です。その時に伝えた内容を、ざっくりと記録しておこうと思います。
「意気込み」と「遊び心」の第1回
第1声は、「面白く見ました」。そりゃ、そうです。いきなりの徳川家康(北大路欣也)ですから。
まさか家康による「歴史の講義」を受けるとは思いませんでした。脚本の大森美香さん、そして演出の黒崎博さんの、これまでとは違う新たな大河を創ろうという「意気込み」と「遊び心」を感じました。
次に、速攻で主演の吉沢亮さんを出してきたこと。この人物が主人公の渋沢栄一なのだと印象づけたことです。
しかも、渋沢の登場と、彼の人生にとっての最重要人物である、一橋慶喜(草彅剛)との出会いをセットにして視聴者に見せたことも大きい。
初回の印象は、ドラマ全体の印象に繋がっています。そして初回の冒頭は、初回だけでなく、物語全体の立ち上がりでもあります。その意味で、栄一と慶喜の2人を押し出した、この冒頭は本当に上手い。
さらに、少年時代の栄一を演じる小林優仁くんも、よくぞ探してきたものだと感心するほど、いい面構えです。「強情で、知恵が早く、理知的で、勇気のある少年」だったといわれる栄一にピッタリ。
そんな小林くんの「栄一少年」と、吉沢さんの「渋沢青年」をクロスさせながら見せていく演出が見事でした。しばらくは少年時代の話が続くはずですが、見る側には吉沢さんの顔がしっかりと残っています。
「見どころ」と「期待」
このドラマの今後についてですが、いくつかの興味と期待があります。
渋沢は、一般的に「明治の実業家」としてとらえられがちですが、天保11年(1840)に生まれて、昭和6年(1931)に91歳で亡くなるまで、なんと11もの元号の時代を生きています。
まさに激動の時代を駆け抜けたわけで、これからその時代がどれだけのスケールで、どう描かれていくのかが見どころの一つになります。
次に、青年時代の渋沢は倒幕派でした。一橋家(徳川慶喜)の家臣となることで、倒すはずの幕府側、いわば体制側に入っていった。
いや、だからこそ後の渋沢があるわけですが、ドラマでは、この“渋沢の転向”を見る側にも分かるように描いてくれるはずで、大いに関心があります。
もう一つ、渋沢は「論語」読みの堅物とみられていますが、実は艶福家、つまり女好きという側面がありました。
「文春砲」のなかった時代とはいえ、今、森喜朗氏の失言問題など、女性との関わり方が社会的に注目されている中で、そのあたりをどう描いていくのか。こちらも興味深いところです。
渋沢栄一が実際に出会った「有名人」たち
最後に、幕末から明治にかけて、渋沢が実際に会ってきた歴史上の「有名人」たちと、今後、ドラマを通じて会えることへの期待があります。
たとえば、新選組の土方歳三。
渋沢は、幕末の京都で一緒に「仕事」をしています。それは、「倒幕の陰謀」に関わっていた人物を捕まえるというものであり、ついこの間まで倒幕派だった渋沢にとっては複雑な心境だったはず。
土方について、後に渋沢は「なかなか思慮のある人物だった」と語っていますが、ドラマの中でどう描かれるのか、楽しみです。
また西郷隆盛とも幕末から面識がありました。
西郷が京都の相国寺にいた頃に始まり、明治政府が出来た後も繋がりは続きます。
初めて2人が差し向いで話をした時、渋沢が元々は武士でもなく、関東の農家出身と聞いて、西郷はとても驚いたそうです。
そして明治政府の中枢に入った後、渋沢は職務上や立場上で、より多くの「歴史上の人物」と接することになります。主な名前を挙げれば・・・
伊藤博文、井上馨、大久保利通、木戸孝允、江藤新平、後藤象二郎、大隈重信など。
歴史の教科書に出てくる彼らが、生身の人間として登場してくる。
何を語り、何を行ったのかが、渋沢との関係を軸としながら明らかになる。それだけでも、ちょっとワクワクしませんか。
もちろん、彼らが出てくるのは、まだ先のこと。
しばらくは、武蔵国(むさしのくに)の榛沢郡血洗島(はんざわぐん ちあらいじま)に暮らす栄一少年と、後に一橋慶喜となる七郎麻呂少年(笠松基生)、それぞれの少年時代と日本の動きを見つめていきたいと思います。
高畑充希主演
『にじいろカルテ』に隠された
「色」の謎とは!?
『にじいろカルテ』(テレビ朝日系)を、とても興味深く見ています。
舞台は山奥の村の診療所で、スーパードクターも超絶技巧の手術場面も出てこない、異色の医療ドラマです。
外科医の浅黄朔(あさぎ・さく 井浦新)と看護師の蒼山太陽(あおやま・たいよう 北村匠海)が守る「虹ノ村診療所」。
そこに内科医の紅野真空(くれの・まそら 高畑充希)が新メンバーとしてやって来ました。
しかし、真空自身が難病を抱えています。「他者を助ける」医師でありながら、同時に「他者の助けを必要とする」患者でもあるのです。
「支え合って生きる」ということ
それはヒロインの真空に限りません。たとえば、「にじいろ商店」の橙田雪乃(とうだ・ゆきの 安達祐実)は認知症を患っています。
彼女の記憶は、数カ月のサイクルで「リセット」されてしまう。自分のことや、周囲の人たちのことも分からなくなってしまいます。
一番混乱するのは本人です。いや、混乱というより恐怖を感じる。パニックに陥ります。
しかし、夫である橙田晴信(とうだ・はるのぶ 眞島秀和)は動じません。
当り前のように、その都度、雪乃にプロポーズするのです。これがとても素敵です。
そして、雪乃の友人である緑川嵐(みどりかわ・あらし 水野美紀)も、霧ヶ谷氷月(きりがや・ひづき 西田尚美)もすごい。
毎回、ゼロから雪乃に対して「自己紹介」をして、また友だちとして交際を始めるのです。
晴信も嵐たちも、明るい「マドンナ」である雪乃に元気づけられ、助けられているから。
夫の晴信だけでなく、村のみんなも自然に雪乃を支えるし、雪乃も意識しないままに、みんなを支えているわけです。
そして認知症であることも含めた雪乃を好きだし、大切に思っている。
この村では、認知症も一つの「個性」なのです。これまた、かなり素敵じゃありませんか。
ということは、真空が抱えている難病も個性であり、そんな個性を持った真空が、医師としてみんなを支え、同時に患者としてみんなに支えられていく。
このドラマのポイントは、この「相互性」にあります。生きていくって「お互いさま」なんだよ、ということを伝えていると思うのです。
登場人物の「名前」の謎
いえ、「謎」ってほどのもんじゃないのですが、脚本の岡田恵和さんの「仕掛け」が楽しいので、あえて謎と呼んでみます。
この村の名前は「虹ノ村」で、虹は「七色の虹」といわれるように、(科学的に正確かどうかはともかく)7つの色で構成されています。
それが、赤・橙(だいだい)・黃・緑・青・藍・紫。
赤や黃色が単独で存在していても虹にはなりません。しかし、7色がそろって、互いに支え合えば美しい「虹」になる。
このドラマは、そう言っているのではないでしょうか。
ご存知のように、登場人物の名前の多くが、「色」に関係しています。
・紅野真空→赤
・浅黄朔→黄
・蒼山太陽→青
・橙田雪乃、晴信→橙色(オレンジ)
・緑川嵐→緑
・白倉博(しらくら・ひろし モト冬樹)→白
・筑紫次郎(ちくし・じろう 半海一晃)→紫
・桃井佐和子(ももい・さわこ 水野久美)→桃色(ピンク)
認知症の雪乃(橙色)も、難病の真空(赤)も、妻を亡くしトラウマに苦しむ浅黄(黄色)も、そこにいてくれるおかげで、「七色の虹」になる。
そう思って、名前を見直してみると、実は「藍」だけがありません。
これもまた、岡田恵和さんによる巧妙な仕掛けかと思いますが、考えられる展開は2つでしょう。
1つは、今後、「藍」の字が入った名前の人物が登場する。たとえば「〇〇藍さん」とか、「藍川〇〇さん」とかですね。これ、可能性ありだと思います。
2つ目は、かなり妄想的ですが・・・
「藍」という色を説明する時、一番簡単なのが「濃い青色」という言い方です。
で、もう少し詳しく説明するなら、「ちょっと緑がかった濃い青色」。
この「緑がかった」の部分をヒントに想像すれば、「青」の蒼山太陽と「緑」である緑川嵐が合体、もしくは融合することで「藍」になる、ってのはどうでしょう。
もっと言えば、太陽くんと嵐さんの間に、女の子が産まれたりして、名前が「藍ちゃん」になるとか。これで「7色コンプリート」(笑)。
まあ、実際にどうなるのか分かりませんが、藍色も加わって、虹ノ村の空に「七色の虹」がかかるのを楽しみにしたいと思います。
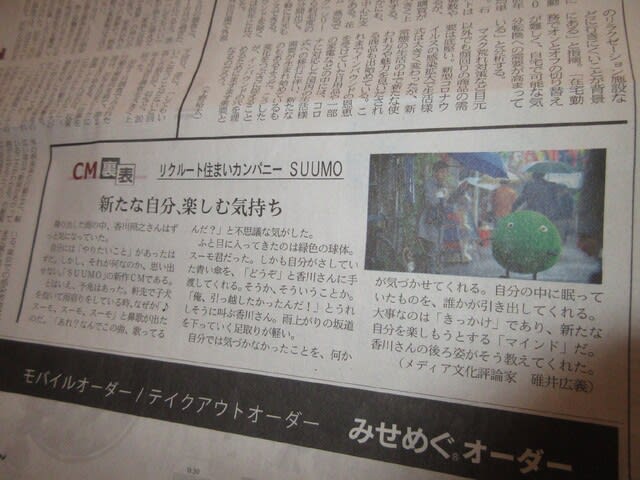
リクルート住まいカンパニー
「SUUMO(スーモ)」
新たな自分、楽しむ気持
降り出した雨の中、香川照之さんはずっと気になっていた。自分には「やりたいこと」があったはずだ。しかし、それが何なのか、思い出せない。「SUUMO」の新作CMである。
とはいえ、予兆はあった。軒先で子犬を抱いて雨宿りをしている時、なぜか「♪スーモ、スーモ、スーモ」と鼻歌が出たのだ。「あれ?なんでこの歌、歌ってるんだ?」と不思議な気がした。
ふと目に入ってきたのは緑色の球体。スーモ君だった。しかも自分がさしていた青い傘を、「どうぞ」と香川さんに手渡してくれる。
そうか、そういうことか。「俺、引っ越したかったんだ!」と嬉しそうに叫ぶ香川さん。雨上がりの坂道を下っていく足取りが軽い。
自分では気づかなかったことを、何かが気づかせてくれる。自分の中に眠っていたものを、誰かが引き出してくれる。大事なのは「きっかけ」であり、新たな自分を楽しもうとする「マインド」だ。香川さんの後ろ姿がそう教えてくれた。
(日経MJ「CM裏表」2021.02.15掲載)
菅野美穂×浜辺美波『ウチカレ』が、
裏技で描く「家族って何?」
10日放送の第5話で、「ずいぶん面白くなってきたなあ」と思わせてくれたのが、『ウチの娘は、彼氏が出来ない‼』(日本テレビ系)。ようやく、「裏テーマ」が見えてきたからです。
母の水無瀬碧(みなせみどり 44歳、菅野美穂)は「恋愛小説の女王」と呼ばれる作家。娘の空(そら 20歳、浜辺美波)はコミック好きの、いわゆるオタク系大学生。
港区のタワマンで2人暮らしですが、微妙に浮世離れした「母娘」を演じる、菅野さんと浜辺さんが完全にハマっています。
これって「ラブコメ」?
しばらく恋愛から遠のいていた碧は、恋愛小説の新作が書けず困っていました。でも、それ以上に恋愛経験のない娘のことが気になって仕方ない。娘のために、取って置きの「恋愛指南」を施したりして・・・。
碧の周辺にも、「恋愛へと発展するのかな」という男性はいるのです。近所でたい焼き屋「おだや」を営む、幼なじみの「ゴンちゃん」こと小田欣次(沢村一樹)。
そして、仕事がらみとはいえ、担当編集者の橘漱石(川上洋平)とも悪くない雰囲気です。
空のほうは、ついに初デートに至った、整体師の渉周一(東啓介)。それから同じ大学に通う、オタク同士でもある入野光(岡田健史)とだって、マンガ制作以上の関係が深まってもおかしくない。
また、その光は、元家庭教師の未羽(吉谷彩子)とつき合っていました。
さらに、漱石の恋人だったはずのサリーこと伊藤沙織(福原遥)が、なんと突然、ゴンの父である俊一郎(中村雅俊)と急接近です。
裏テーマは「家族」?
そんなこんなで、ちょっと誤解していました。このドラマは、母と娘、それぞれの恋愛が同時進行する「ラブコメ」だと思っていたら、違うみたいです。
表向きは「ラブコメ」ですが、本当は異色の「ホームドラマ」というか、裏テーマは「家族」であり、描きたいのは「母と娘の物語」ではないか。これって、脚本家・北川悦吏子さんの裏技と言っていいでしょう。
何しろ第4話の終盤で発生したのが、昔のホームドラマでよくあった、親子の「血のつながり」問題です。
確かに、碧と空の関係性は風変わりで、親子というより年の離れた姉妹、もしくは親友のような感じが、どこか不自然なほどでした。それに、「母ちゃん、私もそう思うぞ!」といった空の口調も独特です。
また、「恋愛は終わっても、親子は終わらない!」とか、「親子最高!」とか、やたらと親子を強調するセリフが乱発されました。それも「血のつながらない親子」という展開の伏線だったのでしょうか。
うーん、親と子。そう思って振り返ってみると、俊一郎とゴンの父子関係にも、まだ見えない奥深さがあります。
光も故郷の父親との関係がこじれているようだし、サリーも自分の母親を「毒親」と呼ぶような過去を抱えているらしい。
全体として、「家族」「親子」というテーマが浮上してきます。
新たな「家族像」「親子像」を探る
親子の「血縁問題」が出てきたとはいえ、決して暗い話にはならないはずです。この第4話の冒頭も、いきなり『徹子の部屋』かと思ったら、タマネギ頭は浜辺さん、いえ空でした。
背景のセットやファッションだけでなく、空の話し方もまんま黒柳さんで、他局番組のパロディも辞さない。
以前には、碧の恋愛指南に対して、「私が広瀬すずだったら立ってるだけでいいのに!」と空。すかさず碧が「私も井川遥だったら、ただ座ってるよ」なんて言うから笑っちゃいました。このドラマ、随所で、この調子です。
ラブコメ風エピソードを散りばめ、笑わせたり泣かせたりしながら、今、「家族」とか「親子」って何だろうと探ってみようとしている。
であれば、これまでにない「家族像」や「親子像」が、物語の中で提示されるかもしれません。
次回が「出生の秘密」的な話になるなら、前半の山場になりそうです。
「青天を衝け」に追い風
「麒麟がくる」光秀の“ナレ死”でも高視聴率
2月7日の放送で最終回をむかえたNHK大河ドラマ「麒麟(きりん)がくる」。シリーズ開始前には、帰蝶(きちょう)役で出演予定だった沢尻エリカの逮捕により、川口春奈を代役として撮り直しするなどし、2週遅れでの波乱スタート。さらに、コロナ禍での収録一時休止も乗り越え、当初予定していた全44回をすべて放送することができた。
長谷川博己主演による明智光秀の生涯は、クライマックスとなる「本能寺の変」を描いた最終回の視聴率は18.4%(ビデオリサーチ調べ 関東地区)という、番組2位の高視聴率を記録。平均視聴率も前作の「いだてん〜東京オリムピック噺〜」を大きく上回った。
「さまざまなトラブルに見舞われた中で、大善戦となったといっていいのではないでしょうか」
と言うのは芸能評論家の三杉武さん。
「麒麟」のラストシーンでは、本能寺の変の数日後に光秀は秀吉率いる軍勢に滅ぼされたことがナレーションで語られる“ナレ死”扱いであったことや、実は生き延びたという光秀生存説を大胆に採り入れたことでも大きな話題を集めた。
メディア文化評論家の碓井広義さんは、「麒麟がくる」で描かれた光秀像について、こう語る。
「今回の光秀は、これまで描かれてきた戦国武将像のイメージとは大きく外れていました。一言でいえば『戦の嫌いな武将』です。今回の大河のテーマであった『麒麟』とは、民の安寧な暮らしの象徴です。戦とはそれを破壊するものであって、信長の世が続くことは、光秀が目指す民の安寧=麒麟がくることにつながらなかったと推測できる作りになっていました」
そして、明智光秀という名前そのものにも注目する。
「“武”の人でなく“智”の人である光秀。世界を広く見渡し、“明”るい“光”を注ぐことに“秀”でていると読んだ場合、理想主義かもしれませんが、“俺が俺が”で出世欲の塊だらけの中、民の安寧な暮らしを望む。そんな信念を持った人物がいたんだということを伝えたいという、まさに今の時代に通ずるドラマ。製作陣の思いも伝わった気がします」
2月14日からは、近代日本資本主義の父とされる渋沢栄一の生涯を描く大河ドラマ「青天を衝(つ)け」の放送がスタートする。前出の三杉さんは期待を込める。
「渋沢栄一という人物そのもののすごさは一般の視聴者は詳しく知らないかもしれませんが、冒頭では人気のある幕末の動乱から描かれていくので、そこは期待できそうです。1980年代に、『独眼竜政宗』から『武田信玄』へという流れで大河ブームが起こったように、『麒麟』がいい追い風になるような気もします」
「麒麟がくる」は、大河ドラマというコンテンツにも、安寧(あんねい)をもたらせてくれただろうか。【本誌・太田サトル】
(週刊朝日オンライン 2021.02.14)




















