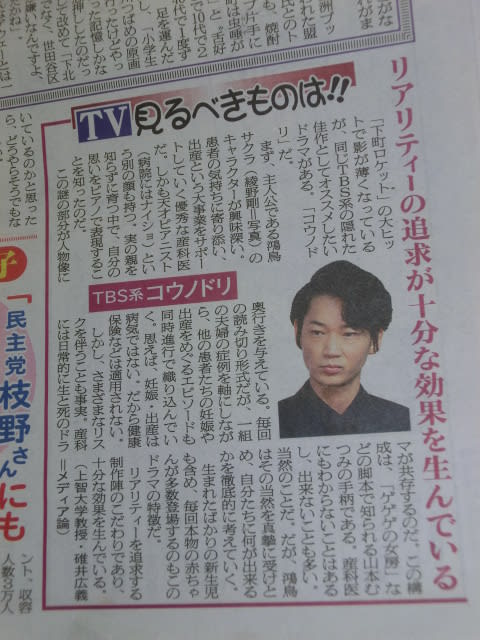「週刊新潮」に、以下の書評を寄稿しました。
工藤美代子 『皇后の真実』
幻冬舎 1836円
日本でテレビ放送が始まったのは昭和28年である。この年のNHK受信契約数は、わずか866。しかし6年後の34年には346万と激増する。4月に行われた「皇太子ご成婚パレード」を見るためだった。そんな皇室人気の中心に当時の美智子妃、現在の皇后がいた。
民間から皇室へ、しかも将来皇后となることが決まっている結婚。正 田美智子さんという一人の女性と家族にとって、どれほどの重圧であり高いハードルであったか。著者は56年前の国家的慶事の舞台裏をはじめ、半世紀を超える美智子妃の歩みを丹念に描いていく。
そこから浮かび上がってくるのは正田家がもつ家風だ。それは「財は末なり、徳は本なり」という家訓であり、「必要なことを粛々とする」合理的習慣であり、「質素の美学」である。いずれも現在に至る皇后の軌跡と重なっている。
一方で、著者は小和田家にも目を向ける。江戸末期に十手を持つ捕り方だった小和田家の宿望は、「さらなる上級職」を目指すことだった。ハーバード大、東大、外務省、そして皇太子妃へと進んだ雅子さんは、祖先からの「社会的地位に付随する価値観」を開花させたことになる。
正田家と小和田家、皇后と皇太子妃。本書はもちろん皇后の半生に迫るノンフィクションだが、合わせ鏡のように雅子妃の姿が挿入される。著者の目は時に鋭く、厳しい。たとえば皇太子と雅子妃の発言には、「私(わたくし)」が極めて頻繁に登場する。だが、両親陛下の会見には「私」が出てこないと指摘する。
皇族にとっての「私」と「公(おおやけ)」の関係を、身をもって示してきたのが皇后ではなかったか。皇太子妃時代に受けた、近くに仕える人間からの“いじめ”であれ、皇室批判を装った執拗な皇后批判であれ、「私」として対処したことはない。皇后が貫いたのは、まさに「愛と犠牲」による生き方だったのだ。
星亮一、一坂太郎 『大河ドラマと日本人』
イースト・プレス 1620円
NHK大河ドラマの第1作は1963年の『花の生涯』。すでに半世紀を超える歴史をもつ。最盛期は『独眼竜政宗』、『武田信玄』、そして『春日局』が放送された80年代末だ。大河ドラマは日本人の精神にどのような影響を与えてきたのか。作家と歴史研究家が探る。
小川隆夫 『証言で綴る日本のジャズ』
駒草出版 5616円
原信夫、秋吉敏子、渡辺貞夫、山下洋輔といった、日本のジャズ界をリードしてきたミュージシャンの肉声が聴こえてくる。また、彼らと併走してきた油井正一、相倉久人、湯川れい子など評論家の証言も収録。戦後日本のジャズが、生きた歴史として立ち現われてくる。
徳岡孝夫 『五衰の人~三島由紀夫私記』
文春学藝ライブラリー 1318円
三島由紀夫は昭和の元号と年齢が重なる。昭和45年11月25日に45歳で自決してから45年が過ぎた。死の直前、覚悟の「檄」を託されたのが新聞記者だった著者だ。3年半の濃密な交友。本書には誰も知らなかった三島像がある。新潮学芸賞受賞作の有意義な復刊だ。
(週刊新潮 2015.11.26号)