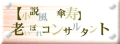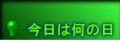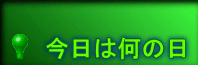■【若狹の生意気言ってすみません!】 知的資産経営について、やっぱり言いたいことがある!
■【若狹の生意気言ってすみません!】 知的資産経営について、やっぱり言いたいことがある!



今回(第2回)は知的資産経営について、次回(第3回)はローカルベンチマークについて、その後は成長デザインシートについて書こうと思っていました。書いているうちに「これは違うぞ(従来の理論ではアカンぞ!)。現実の経営者にとっても、経営を評価して融資や投資をする側にとってもこれは違うのではないか?」という気持ちが湧いて来ました。
知的資産の説明や人的・構造・関係資産の3分類やSWOT分析&戦略策定という流れやKPI設定とか、確かにいろいろあります。確かに様々な論者がいろんな角度、いろんな観点で強みの発見方法等も含めて論じています。
しかし結局、外れていることがあります。事業そのものの目利きの観点が弱いのではないかと。何が儲けの本当のポイント(ビジネスモデルの核心)で、何がお客様から支持されているのか、ここに焦点を相当絞って、もっと分析すべきだと思います。お客様が喜び支持しているその何かを、継続して提供し続けている事実について詳細に学び、実務を担う社員や組織についても深い考察をするのが本来の知的資産の探求だと思います。
が、本当に出来ていますか?という疑問です。ビジネスモデル自体の特徴や限界、ビジネスモデルが実際に機能する為にどう工夫しているかなど、お客様から十分把握出来ていないことが多いのではと感じています。お金を出す側の金融機関や投資機関についてもこれで本当に納得させることが出来るのだろうかと疑問です(彼らが実際には理解しようとすらしていないことが本当の原因ではあります)。
また、KPI一つとっても知的資産経営を支援するコンサルタント側が組織内部の意思決定の深部まで理解しているのだろうかと不思議に感じています。まして、経営理念という概念においては経営者の哲学的な思想がいかに従業員の実際の実務や行動にどう影響し結果が生まれているかなど、相当の時間をかけて分析していかなければ何もわからないハズです。綺麗事でサラッとスルーしているだけの論者や支援者が多い気がします。
ビジネスモデルや儲ける仕組み、お客様が支持する仕組み、それを生産する組織、働く人の協働の問題、さまざまな要因がすべて係るのが知的資産経営の分野ではないでしょうか。非常に手間暇がかかる大変なコンサルタント業務ということがわかります。
さらに、SWOT分析にも言及するなら、「なぜお客様はこの会社が好きなのか?」「どのような顧客提供価値なのか?」という本質がよくわかっていなければ、SWOTの結果導いた戦略もコンサルタントの独りよがりになりかねないと感じます。
私は、建設業の会社に関する知的資産経営分析について発表しているセミナーをいくつか受講しました。その支援者は、建設業に関してあまり深い知見は無いように見えました。お客様の今後の抱負や方針、野心などをきめ細かくヒアリングしているのは素晴らしいと思いました。しかし、基本的な建設業の業界の仕組みや更に社長の案件の獲得方法やその癖などが本当にわかっているのだろうかという気持ちになりました。
建設業の事業性評価をする場合の話をします。事業内容が、土木工事なのか建築工事なのかでビジネスモデルがBtoBかBtoCに分けられ、別分野となります。また、下請か元請かにより、公共工事・民間工事のどちらを中心にしているのか、これだけでも企業の戦略は変わってきます。
民間工事の巨大設備を下請で担当する場合であっても、業務プロセスとして設計前のコンセプト段階から元請と一緒に検討をしているのか否か、コミュニケーションや段取り・スピードなどの違いなどを含めますと、会社によってかなりの差異が出てきます。技術技能水準や工事の効率性や完成検査のレベル、外注管理や資材発注管理、などなど単純に業務フローを追いやすいですが、その中に隠れた見えない差異を発見するのがコンサルの仕事です。
営業一つ取ってもBtoBの工事案件が中心であれば、受注のキーマンにどうやってコンタクトを取り、案件を取り込めるが営業のポイントとなりますが、人脈を使うにしろ、出身大学なのか、地元有力者の紹介なのかなど様々な方法があり、そのスタイルまで踏み込まなければ特徴は見出せません。
癖だってあります。赤字工事が多く、赤字決算が必至の場合、どうやって最終的に黒字決算にする方法(要はなんとかして利幅の高い工事を取って赤字にはしない)など、本当の機密事項を教える訳がありません。こういった事がわかっていなければ例え零細企業であってもその戦略がなんでこうやっているかという基本の所から理解できていないことになります。
更にいいますと、この零細企業は、何が優れており、儲けるポイントになっているのか、そのビジネスモデル(儲ける仕組み)にまで昇華した特徴は「こうです!」と言えなければいくら分析しても的外れではないだろうかと感じます。ストーリーとしての競争戦略が一時期注目された理由でもあります。
しかしながらストーリー(事業の儲ける仕組み)がいくら出来ていても、実際の現場で従業員・仕入れ先・金融機関が力を合わせて協働しなければ何も産み出せません。事業の儲ける仕組みも大事ですし、内部の体制も大事ですが、実際の経営においてさらに大事なことは、組織に経営理念(魂)を吹き込み、現場の従業員の心に火をつけなければ事は成し遂げられないです。経営理念とまで言わなくとも、実際に社員が社長について来てくれなければ仕事は何も完成できません。
歴史を鑑みればその例は幾多もあります。知的資産経営報告書とか成長デザインシートは自分自身を認識するシートでありますが、報告書なりシートを本当に経営に活かしているのだろうか、疑問が残ります。融資・投資の効果であっても必ずしも全面的に利用しているとは言えません。
書類で人は動きません。人を動かすには泥臭いことが多々あって始めて効果があるように感じます。
厳しい事ばかり言いましたが、コンサルティングに、お客様がお金を払う理由というのは。以上のような深い思索が出来て、且つお客様がハッと気づいてくれるまで労を惜しまず頑張るからだと思います。
ここで事業承継の話題に移ります。事業承継で知的資産経営を活用するという論点を言われる方が多いですし、自分もそう考えていますが、それでも肝心な事があります。「承継するものは何?」ということです。
承継の問題に於ける株式や決定権の承継や物的資産の承継はごく自然で当然のことです。悩ましく困難な問題として、従業員の承継であり(従業員に認めてもらう)、金融取引の承継(金融機関に認めてもらう)であり、仕入れ先の承継であり(調達先に認めてもらう)、そしてお客様の承継(利益の源泉であり組織存在の根本となる)が極めて重要だと思います。
お客様が求めて来た商品・サービスを従来通りに、また従来以上に提供する能力がなければ、その組織はお客様にとっては不要です。お客様から支持されているポイントは何かを把握していなければ、出来上がるものは別のものになってしまいます。
組織の力も同じことです。何をもって組織を動かしてきたのか、理解しなければいけませんし、自分自身はどうやって纏めて行き、動かすのかも伝えなければ何もできません。働いて産み出すのは従業員あってのことです。知的資産の3分類で満足したり、自分の会社は良い処があるという自己自慢だけであったりしては、思ったように生産できませんし、売上も伸ばせません。
SWOT分析もお客様にどうやって支持してもらえるのかという観点をもっと考えて分析していかなければ、単に内部外部環境の変化がという論点でボヤけてしまいます。どうやって突破口を開いて苦境を打開してきたのかという苦労と経験の事実や培ってきた価値観がわからなくて何が見えるというのでしょうか。
経営者は日々苦しみ、藻掻いています。伴奏支援というのであれば、我々コンサルタント側も切り込む刀を常に磨かないといけない、と私も猛省しています。
正直に言うと私は、あれは駄目、これも駄目と文句ばかりを言う人間です。戦略ストーリーに走るだけでも駄目、知的資産分析&SWOT分析の分析病でも駄目、適当なKPI設定も駄目、がんじがらめのMBO&収益管理も駄目、流行に走るマーケティング病も駄目、欧米至上主義(欧米師匠主義)の組織改革も駄目、・・・・、こんな感じです。
経営コンサルティング側は、「何か一つを打ち出の小槌にできれば、それを使って盲目的に走る」のではないかと思います。しかし、それをお客様たるクライアントはどう見ているでしょうか。〇〇経営、〇〇戦略、〇〇戦術、〇〇改革、などなど言葉を変え、品を変えて、どうやって売り込むかばかりにしか見えないでしょうか。そんな状態だとお客様は離れていくのではないかと危惧しています。
コンサルティング全盛時代だからこそ言いたいことがあります。
御社の現実をしっかり見つめませんか、御社の状態を定期的に確認してみませんか、やるべきことやらないといけないことを先延ばしにしていませんか、変えたいこと改善したいことがあるのに目先の問題で放置していませんか、本当はこんな夢・野心があるのに躊躇し何もしないままにしていませんか、・・・・。こんな問いも有りではないかと思います。
究極は「当たり前のことが当たり前に出来ていますか?」ではないかと思います。いきなりトヨタにはなれませんし、いきなりテスラにもなれません。強みがなくとも改善して当たり前にできるようになれば、それは強みになります。
健康管理を経営に活かした健康経営も中小・零細企業では殆ど普及していません。お客様の実態・現実、お客様の現場をよく見て、お客様に合わせたメニューになるよう工夫しないとお金を払いたくないでしょう。売れないと嘆く前に、極当たり前のことが出来ていないと思います。当たり前であっても、当たり前をやるべきことをやっていないのがコンサルタントや支援者(組織含む)ではないかと思います。私も出来ていない支援者の一人です。・・・私こそ、コンサルタントとして「当たり前」のことが出来ていません!
結局、またもや反省文になってしまいました。オチが無く申し訳ございません。今回はこれにて終了致します。