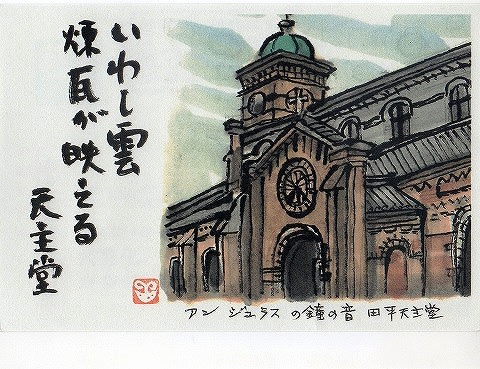
17.中学校の校庭の一角に
関ケ原中学校の校庭の一角に藤堂高虎、京極高知陣跡碑が立てられていました。

ここに陣を配した両隊は大谷隊と小早川隊との壮絶な戦闘の中へ突入大谷隊を撃滅した。

秋です
コキアが色づき

シュウメイギクがここでも真っ盛りでした。
電柱には使番の説明がされていました。

つかいばん
大将の命令を各部隊に伝える伝令役
家康の使い番は 伍 も背旗を差していた
関ケ原中学校の校庭の一角に藤堂高虎、京極高知陣跡碑が立てられていました。

ここに陣を配した両隊は大谷隊と小早川隊との壮絶な戦闘の中へ突入大谷隊を撃滅した。

秋です
コキアが色づき

シュウメイギクがここでも真っ盛りでした。
電柱には使番の説明がされていました。

つかいばん
大将の命令を各部隊に伝える伝令役
家康の使い番は 伍 も背旗を差していた
16.福島正則陣跡に月見宮大杉が
関ケ原では観光ポイント近くの電柱に武将物語が書かれている。

福島正則陣跡近くの電柱には「松尾村に東軍の
最左翼として約6千の軍勢を率いて布陣した正則は五大老で西軍の主力である宇喜多隊
約1万5千と激戦を繰り広げた」と書かれていました。


福島正則陣跡は春日神社境内にあり、天を突くような杉の大木が立っていました。
風雪800年、関ケ原合戦図屏風にも描かれている月見宮大杉です。
目通り5.8M、高さ25M 樹齢800年と記されていました。
関ケ原では観光ポイント近くの電柱に武将物語が書かれている。

福島正則陣跡近くの電柱には「松尾村に東軍の
最左翼として約6千の軍勢を率いて布陣した正則は五大老で西軍の主力である宇喜多隊
約1万5千と激戦を繰り広げた」と書かれていました。


福島正則陣跡は春日神社境内にあり、天を突くような杉の大木が立っていました。
風雪800年、関ケ原合戦図屏風にも描かれている月見宮大杉です。
目通り5.8M、高さ25M 樹齢800年と記されていました。
15.不破関資料館、
不破関は
672年壬申の乱後、8世紀初めに設置された東海道の鈴鹿関、北陸道の愛発関とともに古代三関の1つとされています。
資料館で関所跡から出土した土器が展示されえいました。

資料館から少し東の方に不破関守跡、不破関跡が残されていました。

破関守の館跡でもあるこの場所は、
今も関守の末裔である三輪家が所有する庭園「関月亭」が公開されていました

不破関は
672年壬申の乱後、8世紀初めに設置された東海道の鈴鹿関、北陸道の愛発関とともに古代三関の1つとされています。
資料館で関所跡から出土した土器が展示されえいました。

資料館から少し東の方に不破関守跡、不破関跡が残されていました。

破関守の館跡でもあるこの場所は、
今も関守の末裔である三輪家が所有する庭園「関月亭」が公開されていました

14.チョイの間 中山道を歩く
ここは中山道 間の宿 山中 と書かれた標柱、高札所跡の説明版や
傍を流れる川には黒血川と書かれている。

壬申の乱でここ山中は両軍の激戦が繰り広げられ、両軍兵士の血が川底を黒く染めたことから
この名前がついたと書かれていました。
家並もどこかしら昔のたたずまいを残しているようでもあります。

小川を渡ります。
関の藤川(藤古川)と言って壬申の乱では両軍がこの川を挟んで対峙したり、
関ケ原合戦では大谷吉継が上流で布陣するなど軍事上要塞の地だったようです。

ここは中山道 間の宿 山中 と書かれた標柱、高札所跡の説明版や
傍を流れる川には黒血川と書かれている。

壬申の乱でここ山中は両軍の激戦が繰り広げられ、両軍兵士の血が川底を黒く染めたことから
この名前がついたと書かれていました。
家並もどこかしら昔のたたずまいを残しているようでもあります。

小川を渡ります。
関の藤川(藤古川)と言って壬申の乱では両軍がこの川を挟んで対峙したり、
関ケ原合戦では大谷吉継が上流で布陣するなど軍事上要塞の地だったようです。

13.大谷吉継墓 大谷陣跡へ
南天満山の宇喜多陣跡から山を越え、谷を渡って

大谷吉継墓まで息を切らしながら歩きます。
三成の親友だった大谷は病身を押しての参戦も小早川の寝返りで窮地に落ち入り自害した。


合戦後建てられた墓と大谷吉継陣跡碑
小早川秀秋が陣を置く松尾山眺望地からは


旧中山道、国道21号、新幹線そして小早川秀秋陣跡がある松尾山を眺望することができます。
南天満山の宇喜多陣跡から山を越え、谷を渡って

大谷吉継墓まで息を切らしながら歩きます。
三成の親友だった大谷は病身を押しての参戦も小早川の寝返りで窮地に落ち入り自害した。


合戦後建てられた墓と大谷吉継陣跡碑
小早川秀秋が陣を置く松尾山眺望地からは


旧中山道、国道21号、新幹線そして小早川秀秋陣跡がある松尾山を眺望することができます。
12.西軍副大将 宇喜多秀家陣跡
木立がうっそうと茂る斜面を登ります。
朝からの山路ウォーキングで少々へばってきましたが
水を飲みながら天満山を登ります。

西軍の副大将を務めた 宇喜多秀家陣跡にやってきました。
少々休憩してから説明書きを読みました。

最後まで反徳川を貫いた宇喜多秀家は、

この付近で、兵約1万7千という西軍の主力部隊を指揮したそうだが東軍福島隊の
猛攻に敗れ敗走、八丈島に流された。
宮本武蔵が奮戦したのもこの辺りだそうです。
・・・・宮本武蔵は東西どちらで戦ったのでしょうね?
1昨年八丈島に行ったとき故郷岡山の方を、
望郷のまなざしで見つめる宇喜多像を
見たことを思い出しました。
木立がうっそうと茂る斜面を登ります。
朝からの山路ウォーキングで少々へばってきましたが
水を飲みながら天満山を登ります。

西軍の副大将を務めた 宇喜多秀家陣跡にやってきました。
少々休憩してから説明書きを読みました。

最後まで反徳川を貫いた宇喜多秀家は、

この付近で、兵約1万7千という西軍の主力部隊を指揮したそうだが東軍福島隊の
猛攻に敗れ敗走、八丈島に流された。
宮本武蔵が奮戦したのもこの辺りだそうです。
・・・・宮本武蔵は東西どちらで戦ったのでしょうね?
1昨年八丈島に行ったとき故郷岡山の方を、
望郷のまなざしで見つめる宇喜多像を
見たことを思い出しました。
11.開戦地の碑が立つ
ススキが秋を知らせるかのように白い穂を揺らし、

赤まんまが耕作の済んだ田で咲いている中を快適に歩きます。
幟が見えてきます。

合戦がここから始まったという碑が立っています。
説明書きには、
「慶長5年9月15日、霧が薄くなり視界が広がった午前八時、
先峰の福島正則は松平・井伊隊の動きを見て、先陣の手柄を撮られてなるものかと
宇喜多隊に一斉射撃を浴びせ合戦が始まったとされる場所です」

小西行長陣跡も近くにあったようですが見落として素通りしてしまいました。
ススキが秋を知らせるかのように白い穂を揺らし、

赤まんまが耕作の済んだ田で咲いている中を快適に歩きます。
幟が見えてきます。

合戦がここから始まったという碑が立っています。
説明書きには、
「慶長5年9月15日、霧が薄くなり視界が広がった午前八時、
先峰の福島正則は松平・井伊隊の動きを見て、先陣の手柄を撮られてなるものかと
宇喜多隊に一斉射撃を浴びせ合戦が始まったとされる場所です」

小西行長陣跡も近くにあったようですが見落として素通りしてしまいました。
10.そば畑が広がる中をウオーキング
笹尾山を下ってしばらく歩くと白い花を咲かせるそば畑が見えてきました。

寒さが来る前に収穫できるのでしょうね。
こんもりした森の中に
小池神明社が

そしてその奥に
丸に十字の島津義弘が陣を構えた碑が立っていました。

島津隊は戦況が一変した時、
東軍の中央を突破して逃れた戦国の勇と称えられた武将だと説明書きで知りました。
笹尾山を下ってしばらく歩くと白い花を咲かせるそば畑が見えてきました。

寒さが来る前に収穫できるのでしょうね。
こんもりした森の中に
小池神明社が

そしてその奥に
丸に十字の島津義弘が陣を構えた碑が立っていました。

島津隊は戦況が一変した時、
東軍の中央を突破して逃れた戦国の勇と称えられた武将だと説明書きで知りました。
9.兜の形をしたオブジェ
平成12年、関ヶ原合戦400年祭を記念して行われた、「関ヶ原石彫シンポジウム2000」
のひとつで彫刻家緒方良信氏の作品「無限時空」だそうです。

シッポのようなものも見受けられました。

平成12年、関ヶ原合戦400年祭を記念して行われた、「関ヶ原石彫シンポジウム2000」
のひとつで彫刻家緒方良信氏の作品「無限時空」だそうです。

シッポのようなものも見受けられました。










