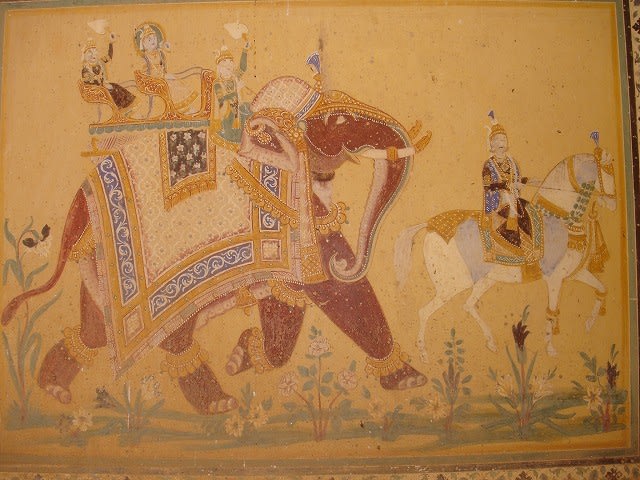2005年《手造の旅》インドより
「ヘイ・ラーム(おお、神よ)」至近距離から銃撃され絶命する直前のガンディーの言葉が刻まれている

死の翌日にここで火葬され、灰はガンジス川ヤムナー川(ガンジスの支流で古都アグラも流れる)と、若き日々をおくった南アフリカの海に撒かれた。
ヒンズー教徒は墓をつくらない。だからここはガンディーの墓ではない。

墓ではないが、ガンディーを悼む人々が集まる場所となっている。

1948年1月30日、滞在していた支援者の家の庭で礼拝に向かう途中、胸に三発の銃弾をうけた。
ヒンズー教徒だった彼を暗殺したのはヒンズー至上主義のゴドセーという男だった。
イスラム教徒と共に新しいインドをつくろうとしたやりかたがイスラム教徒に妥協的だと不満に思い凶行に及んだ。
※近年、ヒンズー教徒優遇政策を推進するインド内でガンディーの暗殺者を英雄として崇拝する集団ができてきたそうだ
産経新聞のページにとびます
インドの国旗の中心にはあるのはガンディーがまわしていた糸車(チャルカ)なのだとずっと信じていたが 調べてみると「アショカ・チャクラ」という仏教由来の法輪にだとわかった。
調べてみると「アショカ・チャクラ」という仏教由来の法輪にだとわかった。
だが、1931年の独立運動のシンボル旗には糸車が画かれている 大英帝国の工業化によって破壊されていったインド社会を、インドの伝統的な綿紡ぎを復活させることで自立させようとしたガンディー。
大英帝国の工業化によって破壊されていったインド社会を、インドの伝統的な綿紡ぎを復活させることで自立させようとしたガンディー。
国旗の上部サフラン色はヒンズー教、下部の緑はイスラム教をあらわす。宗教によって分断された社会を和解できるのは地道な生活なのだと言っているようだ。
イギリスから独立する際にイスラム教徒のパキスタン(現在のバングラデシュも含む)を分裂させてしまったが、ガンディーは最後までジンナー(パキスタンの初代総督となった人物)に分離を思いとどまるように言い続けていた。
現在の国旗にあるシンボルは糸車もあわせて表現しているものと理解したい。
ガンディが火葬されたガートは四方から見下ろせるようにつくられている


1859年にムガール帝国最後の皇帝が廃位されるとインドは独立を失い、第一次・第二次両大戦において多数のインド兵を前線におくった。
↓この「インド門」は1921-1933年にかけて建設された戦没者慰霊碑である


そのすぐ近くにあるこの天蓋には英国王ジョージ五世(現エリザベス女王の祖父)の21メートルの巨像が置かれていた。
※独立後も1968年までそのままだった
ガンディーは暗殺された時、ヒンズー系大富豪のビルラー家の邸宅に滞在していた。
そのファミリーが建設したラクシュミ・ナラヤン寺院

デリー市内でもひときわ立派

観光地のひとつにもなっている

「ヘイ・ラーム(おお、神よ)」至近距離から銃撃され絶命する直前のガンディーの言葉が刻まれている

死の翌日にここで火葬され、灰はガンジス川ヤムナー川(ガンジスの支流で古都アグラも流れる)と、若き日々をおくった南アフリカの海に撒かれた。
ヒンズー教徒は墓をつくらない。だからここはガンディーの墓ではない。

墓ではないが、ガンディーを悼む人々が集まる場所となっている。

1948年1月30日、滞在していた支援者の家の庭で礼拝に向かう途中、胸に三発の銃弾をうけた。
ヒンズー教徒だった彼を暗殺したのはヒンズー至上主義のゴドセーという男だった。
イスラム教徒と共に新しいインドをつくろうとしたやりかたがイスラム教徒に妥協的だと不満に思い凶行に及んだ。
※近年、ヒンズー教徒優遇政策を推進するインド内でガンディーの暗殺者を英雄として崇拝する集団ができてきたそうだ
産経新聞のページにとびます
インドの国旗の中心にはあるのはガンディーがまわしていた糸車(チャルカ)なのだとずっと信じていたが
 調べてみると「アショカ・チャクラ」という仏教由来の法輪にだとわかった。
調べてみると「アショカ・チャクラ」という仏教由来の法輪にだとわかった。だが、1931年の独立運動のシンボル旗には糸車が画かれている
 大英帝国の工業化によって破壊されていったインド社会を、インドの伝統的な綿紡ぎを復活させることで自立させようとしたガンディー。
大英帝国の工業化によって破壊されていったインド社会を、インドの伝統的な綿紡ぎを復活させることで自立させようとしたガンディー。国旗の上部サフラン色はヒンズー教、下部の緑はイスラム教をあらわす。宗教によって分断された社会を和解できるのは地道な生活なのだと言っているようだ。
イギリスから独立する際にイスラム教徒のパキスタン(現在のバングラデシュも含む)を分裂させてしまったが、ガンディーは最後までジンナー(パキスタンの初代総督となった人物)に分離を思いとどまるように言い続けていた。
現在の国旗にあるシンボルは糸車もあわせて表現しているものと理解したい。
ガンディが火葬されたガートは四方から見下ろせるようにつくられている


1859年にムガール帝国最後の皇帝が廃位されるとインドは独立を失い、第一次・第二次両大戦において多数のインド兵を前線におくった。
↓この「インド門」は1921-1933年にかけて建設された戦没者慰霊碑である


そのすぐ近くにあるこの天蓋には英国王ジョージ五世(現エリザベス女王の祖父)の21メートルの巨像が置かれていた。
※独立後も1968年までそのままだった
ガンディーは暗殺された時、ヒンズー系大富豪のビルラー家の邸宅に滞在していた。
そのファミリーが建設したラクシュミ・ナラヤン寺院

デリー市内でもひときわ立派

観光地のひとつにもなっている