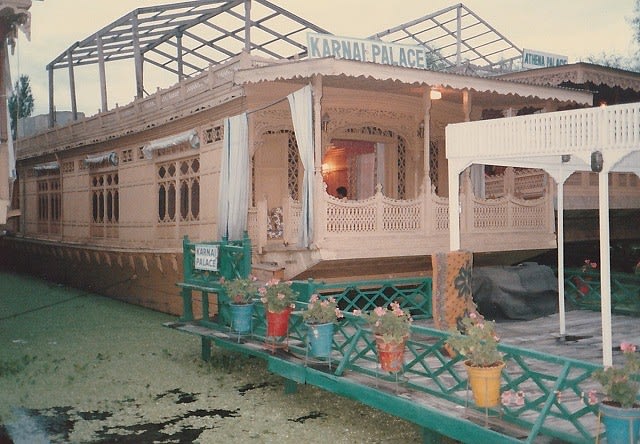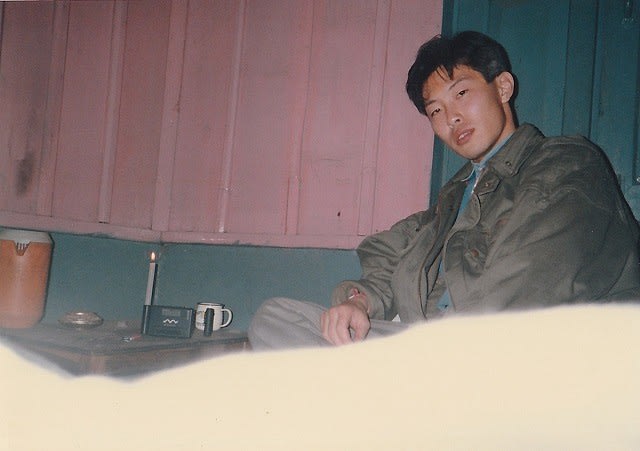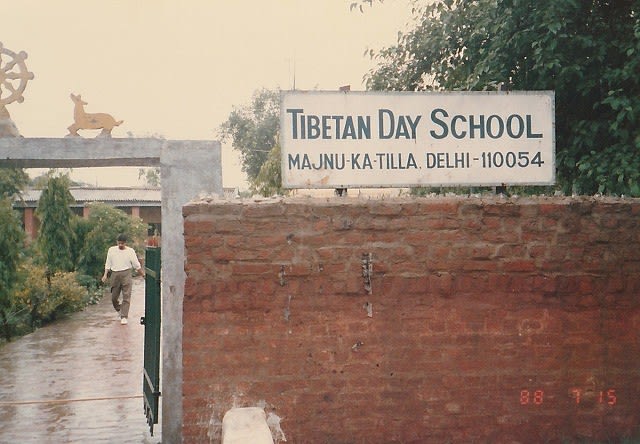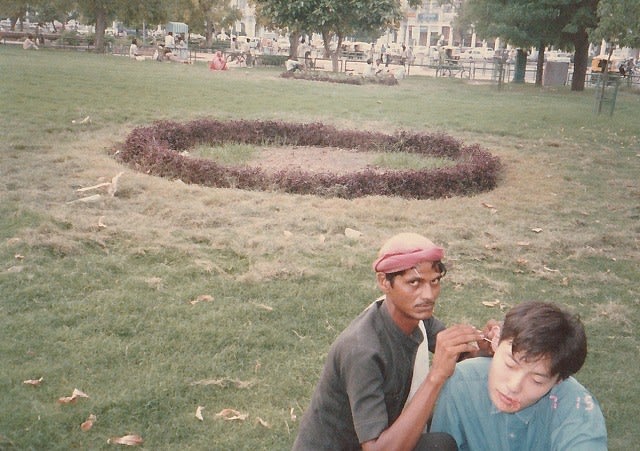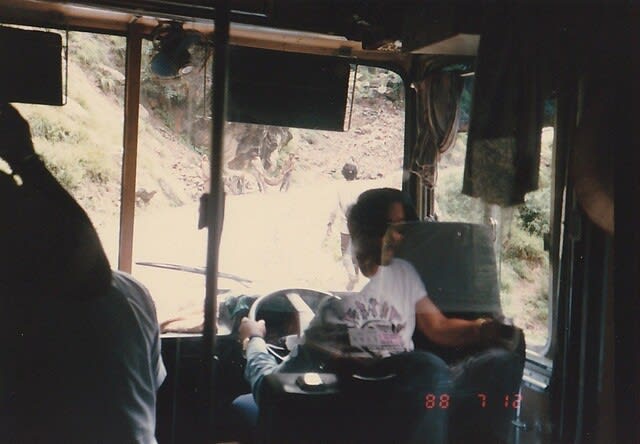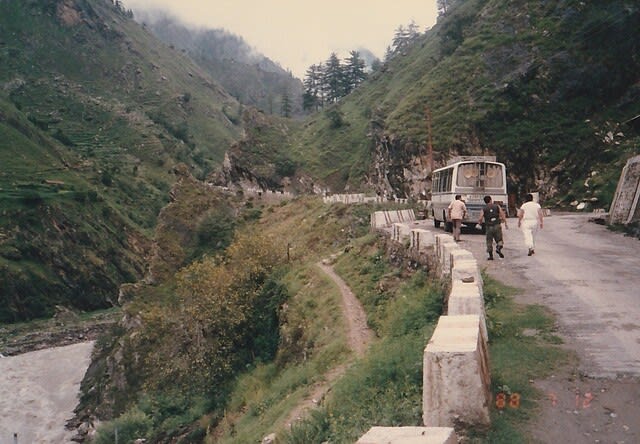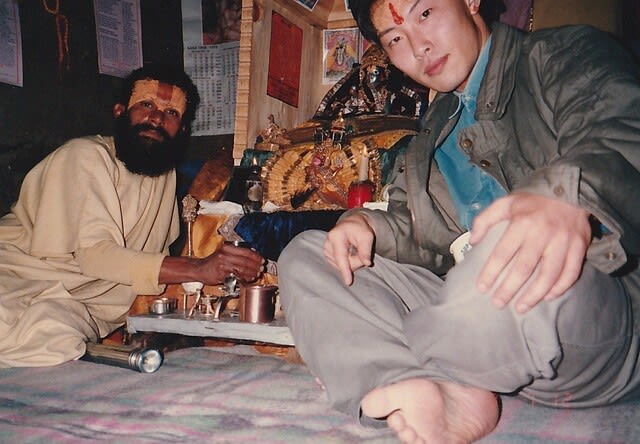寛永十年(1633年)と刻まれた灯篭を覗くと対岸の「近江富士」がぴったり見えた。

芭蕉がここへやってきたのは貞亨2年(1685年)だから、この灯篭はすでにあった。
覗くためにとりつけられたように見える階段を上って、同じように「近江富士」を覗き見たかもしれない(^^)
*
4/6-8で催行することにした近江長浜と比叡山の旅で、
この近くのホテルに宿泊することに決めたので周辺リサーチに来た。
実際に現地を見ておくことで、旅の本番に役立つことが今まで何度もあった。
オンライン検索の情報と合わせることで旅の価値を何倍にも高めることができる。

唐崎は万葉集にも出てくるほど古くからの港で、初代の松は平安時代にはあった。
天正元年(1573)に倒れ、二代目が植えられたのが天正十九年(1591)
※日吉大社のHPに解説されています
芭蕉がやってきた時には植えられてから九十年を超えた「老木」になっていた。

↑この句ははじめ「辛崎の松は小町が身の朧」だったそうな。
年老いた小野小町のことだと解説されたものもある。
小野道風、小野妹子、で知られる小野家のルーツはここから北へ十キロほどの同名の地だとされている。
二代目の松は芭蕉が訪れた後も江戸時代を通じて大きくなり続け、枯れたのは大正十年(1921年)だそうだ。
枯れきる前の明治二十年(1887年)に三代目が植えられ、
↓それも百五十年近くたった令和の今↓枯れかけている。

2008年に撮影された写真が載せられているページにリンクします
2017年からさらに老いがすすみ、
2020年には高い枝は切られた。
※その時の様子が朝日新聞に載っています
かつて横にひろがっていた枝を支えていた石台がそこここに残されている。

「唐崎の松」はもう「インスタ映え」する場所ではなくなってしまったかもしれない。
それでもここには、芭蕉をはじめ飛鳥奈良平安といった時代から訪れた人々の残り香を感じられる。

鳥居の目の前にある、鎌倉時代から続くという「みたらし団子」発祥の店も、

開いていれば味わってみたかった(^^)

芭蕉がここへやってきたのは貞亨2年(1685年)だから、この灯篭はすでにあった。
覗くためにとりつけられたように見える階段を上って、同じように「近江富士」を覗き見たかもしれない(^^)
*
4/6-8で催行することにした近江長浜と比叡山の旅で、
この近くのホテルに宿泊することに決めたので周辺リサーチに来た。
実際に現地を見ておくことで、旅の本番に役立つことが今まで何度もあった。
オンライン検索の情報と合わせることで旅の価値を何倍にも高めることができる。

唐崎は万葉集にも出てくるほど古くからの港で、初代の松は平安時代にはあった。
天正元年(1573)に倒れ、二代目が植えられたのが天正十九年(1591)
※日吉大社のHPに解説されています
芭蕉がやってきた時には植えられてから九十年を超えた「老木」になっていた。

↑この句ははじめ「辛崎の松は小町が身の朧」だったそうな。
年老いた小野小町のことだと解説されたものもある。
小野道風、小野妹子、で知られる小野家のルーツはここから北へ十キロほどの同名の地だとされている。
二代目の松は芭蕉が訪れた後も江戸時代を通じて大きくなり続け、枯れたのは大正十年(1921年)だそうだ。
枯れきる前の明治二十年(1887年)に三代目が植えられ、
↓それも百五十年近くたった令和の今↓枯れかけている。

2008年に撮影された写真が載せられているページにリンクします
2017年からさらに老いがすすみ、
2020年には高い枝は切られた。
※その時の様子が朝日新聞に載っています
かつて横にひろがっていた枝を支えていた石台がそこここに残されている。

「唐崎の松」はもう「インスタ映え」する場所ではなくなってしまったかもしれない。
それでもここには、芭蕉をはじめ飛鳥奈良平安といった時代から訪れた人々の残り香を感じられる。

鳥居の目の前にある、鎌倉時代から続くという「みたらし団子」発祥の店も、

開いていれば味わってみたかった(^^)