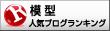模型倶楽部の展示会の一連の準備について整理してみます。
これから倶楽部の展示会を始めようという方のご参考になれば幸いです。
(既に何度も展示会を経験されているベテランの方は無視して下さい。)
ひとつの倶楽部単独で「展示会をやるぞ!」と決めた事を前提にします。
※文中の「会員」は倶楽部会員=出品者のことです。
1.日程と会場決め
いつ頃開催するかという大凡の日程(第1~第3候補くらいまで)を決めて、会場を絞り込みます。
<会場選びのポイント(事前の確認ポイント)>
①費用・広さ・設備(イス、テーブル、展示台などが借りられるかどうか、数や費用は、等)と立地(アクセスの良さや人が集まるかどうか)
当然と言えばそれまでですが、立地と費用は逆相関になるようです。
自治体などが運営する公共施設の方が民間施設より費用が安い傾向です。
②予約の単位(日単位、時間帯単位など)と付帯条件の内容(「最低でも3日間借りる」とか、万一汚した場合の補償等々)。
③展示会の期間、夜間も作品を展示したままにしておけて、きちんと施錠できること。
④作品を車で持ち込む方が多い場合は近隣に安価な駐車場(1日上限金額が低く設定されている等)があるかどうか。
⑤必須ではありませんが、スポットライトがあると作品の見栄えがグッと良くなります。 又、電源が必要な展示作品がある場合には電源コンセントの有無の確認が必要になります。
<日程決めのポイント>
①当然土日ということになると思いますが、集客という観点からは大型連休真っ只中や行楽トップシーズン(家庭サービスや遠出レジャーなどで忙しい)は避けた方がベターだと思います。(会員が全員参加できる日程であることは当然です。)
②関連する大きなイベント(例えば基地祭とか静岡HSなど)と重ならないように注意することも重要です。
会場が公共施設の場合は選挙投票日なども要注意です。
③会場と候補日が決まったら、会場の確保(予約)を行ないます。
第1希望日が空いているとは限らないので、第2・第3候補日を決めておくことが大切です。
※後述する事前告知や諸々の準備のことを考えると展示会開催の3ケ月位前には会場確保=日程確定まで持って行くことが理想です。(もっと早く決められればそれに越したことはありません。)
<展示会実施時間決め(当日の時間割)>
会場を借りた時間帯から展示・撤収作業に必要な時間を差し引いて以下を決めます。
①会員の集合時刻、解散時刻
②来場客向けの開場時刻・終了時刻
この為に展示会の大凡の個人別出品作品数を把握し、展示の仕方と大雑把なレイアウト(個人別展示orテーマ別展示orジャンル別展示等など)を決めておく必要があります。
一番単純でやり易いのは個人別展示です。
2.テーマ決め
無理にテーマを決める必要は無く、テーマを決めるかどうかは倶楽部のポリシー次第で会員の総意で決めれば良い事ですが、テーマを決めた場合には以下のようなメリットが期待できます。
①展示内容に統一感が出る。
②どんな作品を制作・出品するかを決めやすくなる。
私個人の意見としてはテーマを決めたとしても、これに従うことを強要するのではなく、「テーマは決めますが、テーマ以外の制作・出品も自由ですよ」という「緩い」やり方が良いのではないかと思います。
テーマを決める場合は、会員の制作の都合があるので1年くらい前に決めておいた方が良いです。
3.告知
せっかく手間と費用を掛けて展示会を行なうのですから、少しでも多くの方に観て頂けるのが良いので、会場・日程・テーマが決まったら、事前告知が必要です。
①会場での告知
事前告知が掲示できる会場の場合は、ポスター・チラシなど会場のルールに従って告知しましょう。
②模型雑誌での告知
モデルアートやモデルグラフィックス等の雑誌のイベント告知覧に掲載してもらう方法です。
各雑誌毎に決められた方法で原稿を送付して掲載を依頼します。
殆どが月刊誌なので、展示会の2ケ月前までには原稿を送付する必要があります。
③SNSでの告知
倶楽部のHPやブログ・ツイッターや会員個人のツイッターやブログで告知する方法です。
かなり効果があると思います。
4.会員間のルール決め
安全・円滑・快適に展示会を進めるために、最低限のルールを決めて、会員全員で合意しておくのが良いです。
①受付(後述)、食事の取り方 ・・・ 交代制が基本
②入会希望者への対応
③トラブル発生時の対応(必ず2名以上で対応など)
④不要キットの放出、来場者からの差入れ・お土産などへの対応
⑤展示会開催期間の会員の出欠予定の事前確認 ・・・ 蓋を開けたら午前中一人しか居ないなんてことが無いように。
⑥ゲスト出品者への対応(ゲスト出品を受け入れるのかどうか、出品料はどうするか、予約無しの飛び入り参加を認めるかどうか・・等々)
5.道具立てと役割分担決め
展示を行なうための諸々の道具立てを、役割分担を決めて準備します。
必ず必要になる主な道具立ては以下の通りです。
②~④は一度用意すれば、何度でも繰り返し使えます。
①展示台、テーブル、イス
既述の通り、基本的には会場で借りる事になりますが、数が足りるか、大きさは大丈夫かなどを事前に詳しく会場管理者と確認しておく必要があります。
もしも足りない場合は、追加交渉などが必要です。
会員の私物や作品運搬箱などを来場客から見えないようにしまっておく為の「パーテーション」も借りられるとベターです。
②敷布
会場で借りる展示台の色によっては敷布が必要になる場合があります。
この場合は敷布を台に固定するための布製ガムテープがあると良いです。(紙製ガムテープは綺麗に剥がれないので駄目です)
③作品カード(名刺サイズか、それより一回り大きいくらいが一般的)
倶楽部統一の作品カードを作って使用すると統一感が出ますし、来場客にも解り易くなります。
エクセルやワードで作るのが良いと思いますが、PCが使えない会員さんが居られる場合は手書き用も必要です。
会員は基本的に各自が事前に用意しておくのが良いでしょう。
ゲスト出品(飛び入り出品)を受け入れる場合は、手書き用無地の「ゲスト用作品カード」を用意しておく必要があります。
記載内容は作品名、作者、メーカー、スケール、作者コメントなどです。
④「作品にお手を触れないで下さい」カード
来場客が不用意に作品に触って破損させるような事故を防ぐために、必ず必要になります。
展示会の規模にもよりますが、100点くらいの出品であれば20枚は必要かと思います。
言葉だけでは外国人の来場客には解りませんので、目立つシンボルマークが必須です。
(それでも破損事故が起こることはあります・・・)
⑤休憩スペース
来場客から見えないように、会員の私物や作品運搬箱を仕舞って置いたり、会員が座って休憩したりするためのスペースが必要になります。
会場でパーテーションを借りて、仕切ることができれば理想的です。
⑥名札
会場で来場客と会員を識別するために必要になります。
来場客が作品について質問したい場合に大切な手掛かりになります。
100円ショップで売っている首掛け式の透明ケースに作品カードと同じ要領で作ったネームカード(倶楽部名と氏名が入った物)を入れて、会員全員に配れば良いと思います。
⑦受付
会場入り口に180cmの長テーブル一つくらいのスペースで受付を作り、常時会員1~2名が着席するようにします。
来場者のカウント、来場客の質問への対応、ゲスト出品希望者への対応などを行ないます。
来場者に「いらっしゃいませ」、「ありがとうございました」のご挨拶も大切です。
6.その他
必ず必要という訳ではありませんが、「有ると良い」物です。
①・②は一度作っておけば毎回使えます。
①倶楽部を紹介する小さなチラシのような物
倶楽部の歴史やポリシー、活動拠点、連絡先などが解るような物です。
入会希望者が来られた場合にはこれがあると便利です。
②ノボリ又は立て看板
アイキャッチとして会場入り口にあると良いです。
③感染症対策
一概には言えませんが、ある程度の人が集まる以上、その時々の感染症の状況や会場管理者からの要請(事前打ち合わせが望ましい)に応じて対応が必要です。
7.記録
せっかく倶楽部としての展示会を開くのですから、役割分担を決めて最低限のことは記録に残したいものです。
①出品者数、出品作品数(ゲスト出品者も含めて)
②日別の来場客数
③会場のレイアウト
④写真(会場の全景と作品)
これらは、倶楽部のHPやブログがあれば、これにアップしておくと良いでしょう。
展示会の回を重ねてくると慣れてきてドンドン楽になってくると思いますが、最初はやはり大変かと思います。
でも、皆さんでワイワイ言いながら、役割分担して進めるのも楽しみのひとつだと思いますし、達成感も味わえて制作のモチベーションアップに繋がること間違いなしです。
積極的に展示会を開催して模型の楽しさを多くの方々に知っていただけると良いですね。