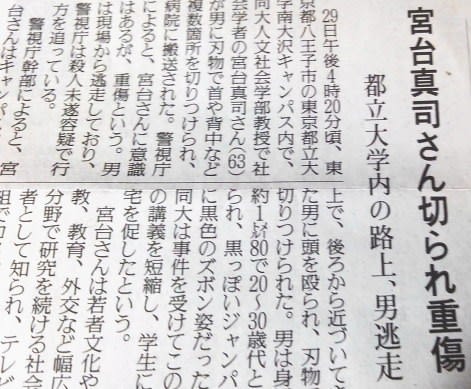校庭にきちんと整列した子どもたちの足元は、幾度となく、巨大な余震によって揺らいだ。
そのたびごとに、一、二年生の低学年の子どもたちは悲鳴をあげた。
五、六年生の高学年の女児たちは、互いに抱き合って怯(おび)えた。
新卒の若い女性教師も、泣きたい、逃げ出したい気持ちを殺して、子どもたちを護ることに必死だった。
グワァーッ…という、地鳴りが何度なく校庭を襲った。
震度5もある余震が、数分おきに起こってくるのである。
今ここで、絶え間なく続く一連の余震が、これが尋常の災害ではないことを、教員たちの誰もの胸に去来した。
この日は、生憎と、学校長が私用で不在であったため、教頭が各学年の主任を集め、在校する子どもたちの避難誘導についての協議を迫られていた。
生徒指導主任が口火を切った。
「このまま、裏山に逃げましょう」
「いや。土砂崩れや、倒木でケガをする恐れがありますよッ!
山道なんてないんですよ。
それに、うっすら雪が積もってるようですし、転んで将棋倒しにでもなったら…」
と、教務主任がそれに応えた。
ベテラン教諭が
「それでは、ハザードマップに従って、橋の向こうの三角地帯に避難しましょうか…」
と言った。
並み居る教員たちは、指揮者である教頭の決済を仰いだ。
「うん。とりあえず、校庭からは移動することにしましょう。
先生方。各学年の引率、よろしくお願いします」
「はい」
と、それぞれの担任が返事をすると、体育座りさせていた子どもたちの処へと銘々小走りで戻った。
A教諭だけは独り、
(やっぱり、山の方が安全なのでは…)
という、思いを抱きながらも、教頭の決断に従い、まだ、校舎内に残っている児童がいないか、見回りに戻った。
そして、小雪がちらつき寒がっていた薄着の子どもたちにと、何着かのジャンパーを無造作に両脇に抱えて出た。
すでに、子どもたちは列をなして校庭を後にするところだった。
A教諭は小走りにその最後列に駆け寄った。
八十名ほどの隊列の前方はかなり前の方であった。
時計を見ると、あの最初の地震感知からすでに五十分近くが経っていた。
その時、何処やらを走っている役所の広報車のスピーカーから、
「巨大津波が迫っています。住民の方は早く高台に避難して下さい」
と、何度も何度も割れんばかりの叫び声でふれ回っていた。