14日はちょっと面白い峰の山に登る予定でした
しかし13日、千畳敷へ行ったあと天気は急変し雨が降り出してしまったのです
仕方なく山は諦めて串本へ向かいますと車窓に雨滴が・・・無い
もしかしたら・・・一縷の望みを託して・・・・・これは行くっきゃないでしょう
R42からR371に入り名勝一枚岩に向けレッツゴーです





しかしそうは甘く有りませんでした
明けて14日
目覚めると雨は昨日より勢いを増し山には雲が低く垂れ込めているでは有りませんか
非常に滑りやすい山で有ると聞いておりましたので、これではどうしようも有りません

早起きの雄さんが幻の滝を見つけたと駆け寄ってきます
道の駅でトーストのモーニングセットを戴きながら店員さんに尋ねますと
岩の上に池が有り雨で増水すると落ちるのだと教えて下さいました
まさに雨が降る日しか見られない幻の滝
雨降って運が良いのか悪いのか・・・
明日、出直そうか諦めようか・・・答えが見つかりません
コーヒーを飲みながらパンフレットに目を向けますと
近くに興味をそそる滝が写真入りで載っていました
滝の拝です

和歌山の旅は驚きの連続
20万分の一の地図にも載っていない山奥の名瀑と言って良いでしょう
お決まりの土産屋も無く川に沿って数件の民家が並んでいるだけ
訪れる人の姿もない仙境の地です




(本流の右に魚が遡上出来る仕組みも見られます)
怒涛の如く流れ落ちる水は橋を境に静まり
浸食された深い淵を緑色に変えて流れ下って行きます




川に下りた雄さんは石の上は良く滑ると言っていました
しかし何と表現したら良いのでしょう
水と岩とが織りなす妙とでも言えば良いのでしょうか


こんな所で滑っては只では済まないと思った私は橋の上から無数の穴が穿たれた岩礁を捉えました
水流により流された石が回転し窪み部分を削って出来るポットホールがアチコチに見られます
群馬県の四万温泉を流れる川でもこの現象は見られるのですが近くに居ながら
其れを見たのは初めてでした





里の景色も長閑です
桃が咲き白木蓮が咲き春らしい空気が満ち満ち
流れる古座川は如何にもゆったりと蛇行を繰り返していました

山桜が車窓に飛び込んできました
もうこんな季節になったんですね
山は残念でしたが今日は思いもかけない出だしに満足、串本へと車を走らせます

R42に出、本州最南端の標識を見つけた私達は迷わずハンドルを右に切りました
続く
人気ブログランキングへ




































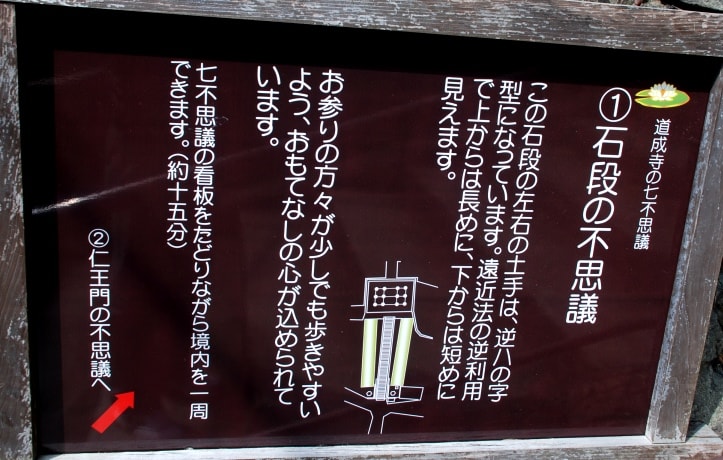


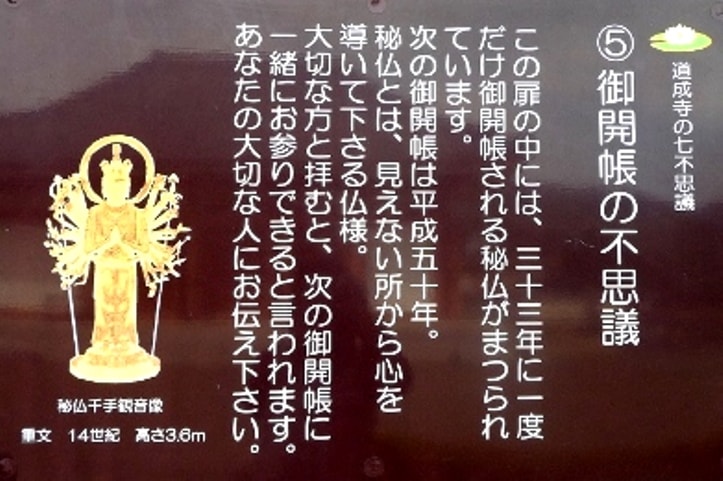
































 」
」
























